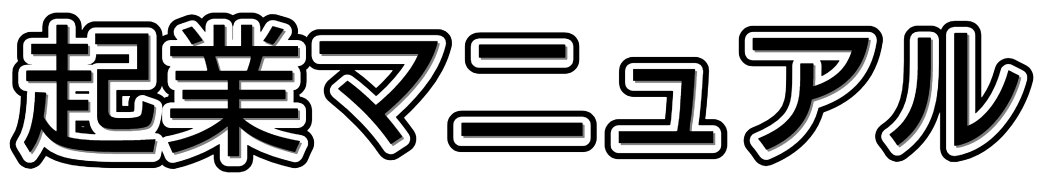1人で株式会社を設立する人が増えている背景
近年の起業動向と1人株式会社のトレンド
近年、日本国内で1人で株式会社を設立する人が増加している背景には、起業家精神の高まりや副業解禁など社会構造の変化が関係しています。
かつては会社設立といえば数人以上の創業メンバーが必要でしたが、2006年の会社法改正によって、出資者・取締役ともに1人でも株式会社設立が可能となりました。
これにより、フリーランスやクリエイター、ITエンジニア、コンサルタント、士業など個人で活動をしていた人を中心に、法人化の動きが広がっています。
また、2020年以降の新型コロナウイルス感染症の拡大も、大企業に頼らない自立した働き方を模索する風潮を後押ししています。
リモートワークの普及や副業解禁といった労働環境の変化が、「個人でビジネスを立ち上げ会社を持つ」という選択肢のハードルを下げ、1人株式会社設立の動向を加速させました。
実際、日本政策金融公庫の調査では、20代・30代の若年層を中心に「まずは1人で起業する」ケースが増えていることが明らかになっています。
| 時期 | 背景となった出来事・法改正 | 影響 |
|---|---|---|
| 2006年 | 新しい会社法の施行(最低資本金制度の撤廃、1人設立可能に) | 1人で株式会社設立が現実的に |
| 2020年 | 新型コロナウイルス感染拡大・リモートワーク普及 | 独立・起業志向が高まり1人起業も増加 |
| 2022年〜 | 副業解禁・フリーランス保護など個人の働き方多様化 | 副業からの法人化、事業拡大志向が強まる |
会社設立手続きのハードルと環境の変化
かつて株式会社の設立は、「複数人の発起人」「1,000万円の最低資本金」「煩雑な手続き」が大きな障壁でした。
しかし、2006年の会社法施行により、資本金1円から設立でき、発起人・取締役とも1人で会社を立ち上げられる仕組みが整いました。
さらに、インターネットでの商業登記電子申請、マイナンバーカードの普及、電子定款の認可などによって手続きが効率化・簡素化されています。
設立費用や手続き負担の低下により、個人でも「株式会社」を選択しやすくなったのが現状です。
特に、各種専門家(司法書士・行政書士・税理士)による設立サポートや、起業をサポートする自治体や金融機関、クラウド会計システムの登場が1人株式会社設立のハードルをさらに低くしています。
これらの環境の変化が、1人で株式会社を設立しやすい時代背景を作り出しているのです。
1人で株式会社を設立できるのか

株式会社の設立要件とその緩和
かつては株式会社を設立するためには、複数の取締役や株主が必要とされていましたが、2006年の会社法改正以降、たった1人でも株式会社を設立できるようになりました。
現在では、「発起人」(設立時株主)や「取締役」を1名だけに設定することが可能で、実際に1人で全ての会社の意思決定ができる「1人株式会社」が増加しています。
監査役の設置も必要ありません。
このように、設立のハードルが大幅に下がったことから、1人起業家やフリーランスにも株式会社設立の道が広がっています。
必要な資本金や設立費用の目安
株式会社の設立資本金に関しては、最低資本金制度が撤廃され、1円からでも設立が可能です。
ただし、実際には運転資金や信用力を考慮し、数十万円〜100万円以上を用意するケースが一般的です。
設立の際には、資本金以外にも登録免許税や定款認証費用などがかかるため、イメージしやすいように下表にまとめます。
| 項目 | 株式会社 | 備考 |
|---|---|---|
| 資本金 | 1円以上 | 実務上は数十万円以上推奨 |
| 登録免許税 | 15万円 | 設立時必須 |
| 定款認証費用 | 約5万円〜6万円 | 公証人役場で認証が必要 |
| 実印作成・印紙代等その他 | 1万円〜3万円 | 合計設立費用は20万〜30万円が目安 |
1人で株式会社を設立する場合も、複数人の場合と同様の設立費用がかかるため、事前に資金計画をしっかりと立てておくことが大切です。
1人で設立できる会社形態と比較
日本では「1人株式会社」以外にも、1人で設立できる法人形態として「合同会社(LLC)」や「個人事業主」があります。それぞれの特徴と、1人株式会社との違いを整理します。
| 会社形態 | 設立可能人数 | 設立時コスト | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| 株式会社(1人株式会社含む) | 1人以上 | 約20万~30万円 | 信用度が高く、資本調達も容易 |
| 合同会社(LLC) | 1人以上 | 約6万~10万円 | 設立費用が安く、運営が柔軟 |
| 個人事業主 | 1人 | 無料(開業届のみ) | 手軽だが信用力や節税面で不利 |
1人で設立できる会社形態を比較した場合、株式会社は他の形態と比べて信用度・社会的信頼が高い一方、設立コストや運営の手間もかかります。
自分のビジネスモデルや将来的な目標に合わせて最適な形態を選ぶのが重要です。
1人株式会社のメリットを詳しく解説

信用力の向上と取引先の拡大
株式会社という法人形態は、個人事業主や合同会社と比較して社会的な信用度が高いと言われています。
株式会社は設立登記を行い、取締役や代表取締役といった役職も明確になるため、取引先や銀行などから安心して取引相手として認識されやすくなります。
そのため、法人名義での契約や業務提携、大手企業との取引など、ビジネスチャンスの拡大が期待できるのが1人株式会社の大きなメリットです。
有限責任によるリスク軽減
株式会社は「有限責任」です。
これは、会社の借入金・債務超過など経営上のトラブルがあった場合でも、出資した資本金の範囲内で責任を負う仕組みです。
個人事業主の場合、自身の全財産で無限に責任を負いますが、株式会社にすることで、事業リスクが個人の資産に直結しにくいのが大きな安心材料となります。
節税対策や社会保険加入の可能性
株式会社になると、課税方法が「法人税」となり、所得が一定以上になる場合には個人事業主時代よりも大きな節税メリットが得られる可能性があります。
また、「給与所得控除」や「役員報酬」の設定など、節税手段の幅も広がります。
さらに、代表取締役も厚生年金・健康保険など社会保険に強制加入となるため、将来の保障や信用性の面でもプラスとなります。
事業拡大時の資金調達や出資募集の容易さ
株式会社は、将来的な資金調達の方法として「銀行融資」「株式発行」「第三者割当増資」「クラウドファンディング」など多様な方法が選択できるという大きな強みがあります。
合同会社や個人事業主の場合は出資募集に限界がありますが、株式会社化することで外部からの資金導入や出資者の増加も容易となり、スムーズな事業成長が期待できます。
自分だけの意思決定ができる自由度
1人株式会社は設立者自身が株主かつ代表取締役となるため、自分の判断で迅速な意思決定が可能です。
複数人の合議や調整を必要とせず、スピード感のある経営が叶います。会社の方針や事業内容も自身のビジョンで柔軟に展開できるため、ベンチャー・スタートアップや個人事業のスケールアップにも最適です。
| メリット | 具体的な内容 |
|---|---|
| 社会的信用力の高さ | 金融機関や取引先との契約で信頼されやすく、事業拡大に有利 |
| 有限責任 | 万一会社が負債を負っても、出資額以上の個人資産が守られる |
| 節税対応 | 法人税や役員報酬の活用で個人事業主に比べ節税の制度が豊富 |
| 社会保険適用 | 厚生年金・健康保険に加入でき、将来的な社会的保障も充実 |
| 資金調達手段の多様化 | 融資や投資を受けやすく、株式発行など成長フェーズに対応 |
| 意思決定の迅速さ | オーナー1人でスピード感ある経営判断が可能 |
1人株式会社のデメリットと注意点

設立や運営のコスト負担
1人で株式会社を設立する場合、設立時にかかるコストや運営にかかる維持費用が大きな負担となることがあります。
株式会社は登記手数料や定款認証費用、印紙代などが発生し、個人事業主や合同会社と比べて初期費用が高額です。
また、毎年の決算公告義務や法人住民税(均等割)など、運営を継続するためのコストが必ずかかる点に注意が必要です。
| 項目 | 株式会社 | 個人事業主 | 合同会社 |
|---|---|---|---|
| 設立費用(概算) | 20〜25万円 | 0円 | 6〜10万円 |
| 法人住民税(均等割) | 最低7万円/年 | なし | 最低7万円/年 |
| 定款認証 | 必要 | 不要 | 不要 |
経理・税務作業の煩雑さ
株式会社は、複式簿記による帳簿の記帳、決算書作成、税務申告などの事務作業が個人事業主に比べて格段に煩雑になります。
特に1人で株式会社を運営する場合、経理担当者が不在のため、これらを自らこなす必要があります。
専門的な知識や経験がない場合、税理士など外部の専門家への依頼が不可欠となり、その分のコストも発生します。
主な経理・税務作業
- 日々の帳簿付け(複式簿記)
- 決算書・損益計算書・貸借対照表の作成
- 法人税・消費税・地方税の申告と納付
- 税務調査や指導への対応
社会保険義務とそのコスト
株式会社の場合、代表取締役1人だけでも社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が原則義務付けられています。
社会保険料は個人事業主の場合と比べて高額になりやすく、売上が不安定な初期段階では特に資金繰りの圧迫要因となります。
報酬額に応じて保険料が増加するため、どの程度の役員報酬にするかも慎重に検討する必要があります。
| 比較項目 | 株式会社(1人) | 個人事業主 |
|---|---|---|
| 社会保険(健康保険・厚生年金) | 原則加入義務あり | 国民健康保険・国民年金 |
| 保険料 | 報酬に応じて高額になる | 定額 |
公私混同のリスクや資金管理の注意点
1人株式会社では、会社のお金と個人のお金をしっかり区別することが法的にも経営的にも重要です。
プライベートな支出を会社経費として処理した場合、税務署の調査で否認されるなどのリスクも高くなります。
また、意図せず資金の流用や精算の漏れが生じやすいため、専用の銀行口座を開設し、全ての取引を記録・管理する体制づくりが求められます。
- 役員報酬の一貫性を持った支給
- 私用の支出を経費計上しない
- 会社資産と個人資産の明確な分離
信用崩壊や経営悪化時の問題点
1人だけで経営判断を行うため、客観的な視点や牽制が働きにくく、戦略ミスや意思決定の偏りから経営悪化を招くリスクがあります。
また、代表取締役が病気や事故などで事業を続けられなくなった場合、そのまま会社活動が停止してしまうケースも少なくありません。
債務超過や倒産時には、個人保証を求められることもあり、最終的に個人資産に影響が及ぶ可能性も否定できません。
- 事業継続性の確保が課題
- 万が一のためにビジネス保険や外部サポート体制の検討
- 客観的アドバイスを得られる顧問の活用や定期的な経営チェックが推奨される
個人事業主や合同会社との違いを徹底比較

各法人形態の特徴と設立コスト
株式会社を1人で設立する場合、個人事業主や合同会社(LLC)と比較して、設立時の手続きやコスト、社会的信用などに大きな違いがあります。
それぞれの特徴と設立にかかる主な費用を以下の表で整理します。
| 形態 | 設立費用 | 設立手続きの難易度 | 設立にかかる期間 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 個人事業主 | 無料 | 非常に簡単(税務署に開業届を提出) | 最短1日 | 手軽に始められ、コストもかからないが、信用力は限定的 |
| 合同会社(LLC) | 約6万円(登録免許税+定款認証不要) | やや簡単(登記のみ) | 1~2週間 | 設立コストを抑えられるが、知名度は株式会社より低い |
| 株式会社 | 約20万円(定款認証+登録免許税等) | 標準的(定款認証・登記必要) | 2週間程度 | 社会的信用が最も高く、資金調達も有利 |
このように、個人事業主は圧倒的に安価かつ速く開業でき、合同会社は株式会社よりも低コストで法人格を取得できるのが特徴です。
株式会社は手間とコストがかかる分、社会的な信用力や資金調達の面で優れています。
税金と社会保険面での違い
税制や社会保険の面でも、それぞれ大きな違いがあります。以下の表で主な比較ポイントを示します。
| 形態 | 課税所得の扱い | 税率体系 | 社会保険加入 | 節税のしやすさ |
|---|---|---|---|---|
| 個人事業主 | 全所得が個人の所得に | 累進課税(所得税15%~45%) | 任意(国民健康保険・国民年金のみ) | 限界あり(経費認定範囲が狭い) |
| 合同会社 | 法人所得として法人税 | 約23.2%(中小企業の実効税率) | 原則、社会保険強制加入 | 役員報酬などの分離が可能で節税幅が広い |
| 株式会社 | 法人所得として法人税 | 約23.2%(中小企業の実効税率) | 原則、社会保険強制加入 | 役員報酬・退職金・経費など活用法が多彩 |
個人事業主は所得に応じて税率が大きく上昇しますが、合同会社や株式会社は一定の税率で法人税が課されます。
社会保険についても、法人の場合は強制加入が基本となるため、保険料の負担増の一方で将来的な保障も手厚くなります。
経営の自由度と信用力の違い
経営判断の自由度や、金融機関や取引先からの信用力という点も重要な違いのひとつです。
個人事業主や合同会社は、意思決定のスピードや柔軟性に優れる一方、株式会社はガバナンスや信用面で有利です。
| 形態 | 意思決定の自由度 | 社会的信用力 | 資金調達のしやすさ | 銀行融資の有利性 |
|---|---|---|---|---|
| 個人事業主 | 極めて高い | 低い | 難しい | 不利 |
| 合同会社 | 高い | 中程度 | やや難 | やや不利~中程度 |
| 株式会社 | 中程度(会社法による手続あり) | 高い | 有利 | 有利 |
株式会社は一般的に銀行や大手企業との取引において有利であり、第三者からの出資や株式発行による資金調達の選択肢も広がります。
一方、個人事業主や合同会社はスピーディーな経営判断が可能ですが、信用力や拡大時の資金調達面で株式会社に劣ることが多いです。
おすすめの会社形態と選び方
どの形態が自分に適しているかは、「目的」「規模」「成長イメージ」によって変わってきます。
たとえば、まずは小さく始めたいなら開業手続きがシンプルな個人事業主や合同会社、将来的な事業拡大や信用力を重視したいなら株式会社がおすすめです。
特に、対外的な信用が重要、将来的に投資や出資、法人設立後の雇用や規模拡大を視野に入れている場合は、最初から株式会社を選ぶメリットは大きいでしょう。
一方、試験的に事業をスタートしたい場合は、コスト面や経営の柔軟性を重視して合同会社や個人事業主の形態を選ぶのも合理的です。
目的の明確化、将来的なビジョンと成長戦略、それぞれの形態の特徴の理解が、後悔しない選択に繋がります。
1人で株式会社設立を成功させるポイント

株式会社設立手続きの具体的な流れ
株式会社は1人でも設立できますが、手続きには法的な手順を確実に踏むことが重要です。
まず、会社基本事項の決定(商号・本店所在地・事業目的・発行株式数など)を行い、定款を作成します。
定款は公証役場で認証を受ける必要があり、電子定款の場合は印紙税4万円が不要になります。
その後、資本金の払い込みを個人名義の口座で実施し、必要書類を準備して法務局へ設立登記を申請します。
株式会社設立は全体で1~2週間程度の期間が必要です。
登記や印鑑証明など必要書類の揃え方
株式会社設立時には、正確な書類作成と取得が大切です。主に必要となるのは以下の書類です。
| 書類名 | 作成・取得方法 | 注意点 |
|---|---|---|
| 定款 | 自作または司法書士等に依頼、公証役場で認証 | 目的や商号に誤りがないか要確認 |
| 発起人の印鑑証明書 | 住民登録地の市区町村役場で発行 | 発行から3か月以内の原本が必要 |
| 設立登記申請書 | 法務局テンプレートを利用可 | 記入漏れや押印ミスに注意 |
| 資本金払込証明書 | 通帳コピー+払込証明書作成 | 設立時の発起人名義口座であること |
| 役員就任承諾書 | テンプレートを利用して作成 | 誤字脱字に注意 |
| 印鑑届出書 | 法務局で取得またはWEBから印刷 | 会社実印を必ず作成しておく |
これらの書類は公的書類として、一本の流れですべて抜けなく準備することが設立成功のカギとなります。
開業後の銀行口座開設と届出
株式会社登記完了後は、会社名義の銀行口座開設が重要なステップです。
金融機関によって求められる書類や審査基準が異なるため、事前に必要書類(登記簿謄本、印鑑証明書、会社実印、代表者の本人確認書類など)を確認しましょう。
創業間もない場合は、事業計画書や事業内容説明資料を求められることもあります。
また、税務署への法人設立届出書、都道府県税事務所・市町村役場への法人設立設置届、年金事務所への新規適用届など、各種役所への開業届出を遅滞なく行いましょう。
専門家(司法書士・税理士)の活用方法
1人で株式会社を設立する場合、業務が多岐にわたり負担となることが多いため、専門家のサポート活用が有効です。
司法書士は定款作成・認証、設立登記をスムーズに進めることができ、法的なミスを防げます。
また、税理士は設立後の会計・税務処理だけでなく、消費税や法人税の各種届出の相談にも乗ってくれます。
専門家を選ぶ際は、料金体系だけでなくアフターサービスや経営サポート体制も比較して選びましょう。
特に初めて会社設立を行う場合、「自分だけで何とかしよう」とせずプロに頼る判断も経営者の大事な資質です。
設立後の経理・税務・法務管理のコツ
株式会社経営は設立後の運営が肝心です。
日々の会計記帳はクラウド会計ソフト(マネーフォワード、freeeなど)を活用して効率化し、現金や銀行取引と領収書の整理を徹底しましょう。
給与や役員報酬の決定、社会保険の加入・届け出も初期段階でクリアにしておく必要があります。
経理ミスを防ぐため、税理士と定期的に相談し、決算・申告時期に備える体制を整えましょう。
また、会社運営には法務管理も重要です。株主総会議事録の作成や商号変更、目的変更などの「変更登記」などについても忘れず管理しましょう。
特に1人株式会社では代表者に業務負担が集中するため、「ルール化」と「デジタル化」で業務負荷を減らす工夫が成功の秘訣です。
1人株式会社を実際に経験した人の体験談・後悔事例
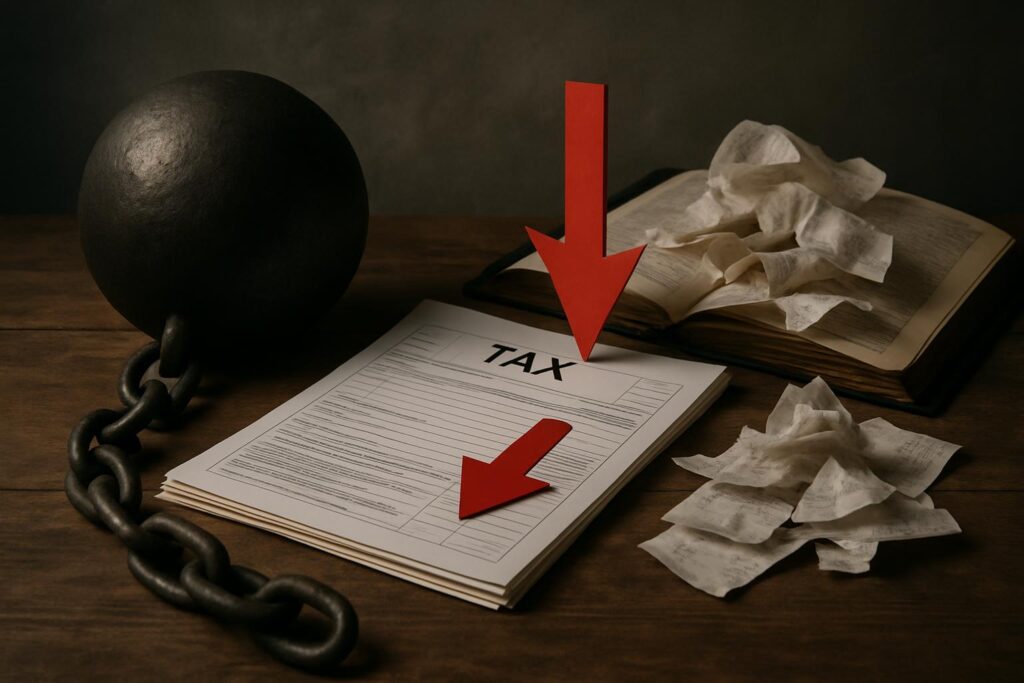
失敗したケースとよくある落とし穴
1人株式会社を設立した方の中には、「設立後に想定していなかったリスクや不便さに直面した」という声も多く聞かれます。
特に最も多い後悔は、経理・税務管理の煩雑さや社会保険料負担の重さを甘く見ていたことです。
下記のようなケースがよく報告されています。
| 事例 | 具体的な内容 | 主な落とし穴 |
|---|---|---|
| 社会保険義務化によるコスト増 | 1人で設立したにもかかわらず、法人化により健康保険・厚生年金の加入が強制され、個人事業主時代よりも手取りが減った。 | 保険料負担を試算せずに設立 |
| 経理・税務の知識不足 | 経費処理や決算書類の作成に苦労し、税理士への外注費が想像以上に発生した。 | 経費や外注コストの見込み誤り |
| 公私混同による信用低下 | 個人的な口座と会社口座の区別が曖昧になり、資金管理でトラブルが発生した。 | 会計分離や資金管理の軽視 |
| 意思決定の孤立 | 相談相手がいないことで事業判断を誤り、トラブルに発展したケース。 | 相談体制やセカンドオピニオンの不足 |
また、設立当初の費用や手続き以上に、日々の管理業務の労力を過小評価してしまい、結果として「専門家への相談を怠った」ことで後悔するケースも顕著です。
後悔しないために事前準備で気をつけたいポイント
1人株式会社のオーナーの多くが設立後に感じた「知らなかった」「準備すれば良かった」と思いがちなポイントを、事前に押さえておくことが極めて重要です。
- 社会保険料や税金のシミュレーションは必須です。特に年収500万円程度の場合、個人事業主時代より手取りが減るケースがあるため、明確な試算をしておきましょう。
- 経理・税務のスケジュール(決算期、税務署や法務局への届け出期限など)を事前に把握し、想像以上に事務作業が多いことを認識する必要があります。
- 資本金の入金、設立登記、会社印鑑作成、銀行口座開設など、手続きの順序を間違えると余計な時間とコストがかかるため、事前に流れ全体を紙やデータで整理しておきましょう。
- 相談できる税理士や司法書士を最初から頼れる体制にしておくことで、不明点が出た際でも迅速に解決できます。
- 業務と私生活の「分離」を徹底し、プライベート支出が事業経費と混在しないように細心の注意が必要です。
こうした事前準備を怠ると、せっかくのチャレンジが想定外のトラブルに変わってしまうため、慎重な計画立案が成功の鍵となります。
成功した起業家のエピソード
ネガティブな体験だけでなく、1人株式会社として着実に成長を遂げているオーナーも多数存在します。
その共通点は、「専門家の助言を積極的に活用した」「経理や法務の基本だけは起業前に学んだ」「日々の業務をルール化し、習慣として運営した」など、準備や仕組み化への工夫にあります。
たとえば、東京都でITコンサルティング業を営むA氏は、設立直後からクラウド会計ソフトを導入し、税理士と顧問契約を結んでいました。
この体制のおかげで経理や納税のストレスが解消され、事業本来の業務に集中しやすくなったことで、1年目から安定した売上と信用を獲得できたと語っています。
また、デザイン制作業を行うBさんは、設立初期段階で複数の金融機関に相談し、資金調達や口座開設で有利な条件を引き出せたことが経営の安定化に直結したとのこと。
「最初は不安だったが、法人化による信用力で大手取引先との契約が実現し、会社としての拡大戦略を描きやすくなった」と実感しています。
このように、1人株式会社は適切な準備と外部リソース活用により、個人事業では得られない自由と発展の機会も広がります。
体験談を参考に、自身の事業計画とライフスタイルに合った最適な選択を心掛けましょう。
まとめ
1人で株式会社を設立することは、信用力や資金調達の面で大きなメリットがある一方、運営コストや経理面の負担、社会保険の義務などのデメリットも存在します。
自分に合った会社形態を選び、事前準備と専門家の活用で後悔しない起業を目指しましょう。