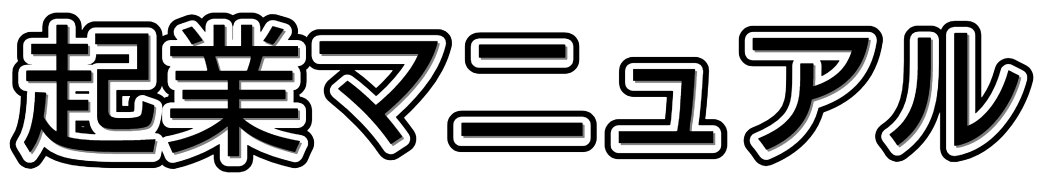株式会社設立に必要な人数の基本知識
株式会社を設立する際、何人の役員や発起人が必要かは、会社設立の第一歩として非常に重要なポイントです。
会社設立を検討する際には、日本の現行法令で定められた最低限必要な人数について正しく理解し、適切な手続きを進めることが求められます。
設立時の人数要件は、事業内容や組織形態の違いによる影響がほとんどなく、すべての株式会社で共通する基本的な条件となっています。
現在の会社法における最低人数
2024年現在、日本で株式会社を設立する場合、発起人および株主は1名から設立可能となっています。
また、取締役も1名のみで足ります。
この規定は2006年の会社法施行以降、個人でも気軽に株式会社を設立できるよう改正されたため、少人数での起業やスモールビジネスにも対応可能です。
| 役割 | 必要な最低人数 | 備考 |
|---|---|---|
| 発起人(株主) | 1名 | 法人・個人ともに可 |
| 取締役 | 1名 | 発起人と兼任可 |
| 取締役会 | 3名以上 | 設置する場合のみ必要 |
| 監査役 | 任意 | 取締役会設置会社は1名以上必要 |
多くの場合、発起人=最初の株主=設立時取締役を1人で兼任することができます。
ただし、将来的に組織を拡大したい場合や、取締役会を設置したい場合は、それぞれ人数要件が異なるため注意が必要です。
以前の法律(商法)と会社法改正による変更点
2005年以前は「商法」によって株式会社設立には最低でも7人の発起人と3人以上の取締役が必要とされていました。
しかし、2006年5月の会社法施行により、株式会社設立に必要な人数が大幅に緩和されました。
この法改正によって起業のハードルが下がり、個人や小規模グループでの株式会社設立が一般的になり、スタートアップやベンチャー企業の増加も後押しされています。
従来の商法と現行会社法の違いを以下の表でまとめます。
| 法律 | 発起人の最低人数 | 取締役の最低人数 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 旧商法(2005年まで) | 7名 | 3名 | 設立コスト・手続きが煩雑 |
| 現行会社法(2006年以降) | 1名 | 1名 | 個人でも設立可、手続きが簡素化 |
このように、現在は1名から株式会社の設立が可能であるため、設立コストや管理面でも柔軟な選択肢が与えられています。
ただし、発起人や取締役が複数の場合には、それぞれの責任や権限分配にも注意が必要となります。
発起人の役割と必要人数

株式会社を設立する際に欠かせないのが「発起人」の存在です。
発起人とは、設立する会社の基本事項を決定し、出資を行い、設立手続きを主導する人のことを指します。
発起人は会社の「設立を企画し、設立登記完了まで責任を持って活動する主体」であり、会社設立プロジェクト全体を推進する重要な役割を担います。
発起人と取締役の違い
株式会社設立にあたって、「発起人」と「取締役」の役割の違いを把握しておくことが重要です。
発起人はあくまで会社設立の過程で中心となる存在ですが、取締役は会社設立後の経営全般を担う執行機関です。
| 区分 | 発起人 | 取締役 |
|---|---|---|
| 役割 | 設立企画・手続き主導・出資 | 会社経営・意思決定・業務執行 |
| 設立時の責任 | 設立手続き全般を完了させる責任 | 設立後の業務執行責任 |
| 人数要件 | 1名以上 | 1名以上 |
| 兼任可否 | 発起人と取締役の兼任は可能 | 全く同一人物でも構成可 |
このように、発起人は設立時限定の「起業プロデューサー」とも言える存在ですが、取締役は会社経営を担う継続的なポジションとなります。
ほとんどの中小企業では、発起人がそのまま設立時の取締役に就任するケースが多いのが実情です。
発起人が複数の場合の注意点
株式会社の発起人は1名でも設立可能ですが、複数で設立する場合にはいくつか注意点があります。
特に、出資比率や設立に関する決定権の所在など、初期段階から明確化しておかないと将来的なトラブルの原因となりかねません。
- 発起人が複数の場合、各発起人の出資比例で株式が割り当てられる
- 定款の作成、資本金の払い込み、設立登記に至るまで、全発起人が連帯して義務を負う
- 決定事項について意見が分かれた場合の調整が必要
また、定款認証の際、公証役場に発起人全員が署名押印しなければならないなど、実務的な手間が増える点にも注意が必要です。
さらに、発起人同士の関係を明確化するため、事前に合意書の取り交わしを行うと、設立後の持分や権利関係のトラブル防止に役立ちます。
発起人が複数いる場合は、出資額・株式数・会社運営の方向性などについて、事前にしっかり合意形成を図ることが、円滑な会社設立と将来の安定経営の礎となります。
取締役・株主の人数要件

株式会社を設立する際には、取締役および株主の人数要件が法律で明確に定められています。
2006年の会社法改正以降、株式会社設立時の要件が大幅に緩和され、最低人数に関する規定も変更されました。
ここでは、現在の会社法に基づく人数要件と実務上の注意点について詳しく解説します。
取締役の人数と選任方法
会社法第326条にもとづき、株式会社設立時には最低1名の取締役を置けば設立が可能です。
従来は3名以上の取締役が必要でしたが、法改正により小規模な会社設立が容易になりました。
取締役の選任方法は定款で定められ、発起人が設立時取締役を選出することが一般的です。
なお、監査役や代表取締役を置くかどうかは、会社の組織形態によります。
| 役職 | 最低必要人数 | 備考 |
|---|---|---|
| 取締役 | 1名 | 設立時から1名でOK。複数でも可。 |
| 代表取締役 | 1名以上 | 取締役会を設置しない場合、取締役=代表取締役とすることが多い。 |
| 監査役 | 0名 | 取締役会非設置会社では必須ではない。 |
取締役会を設置する場合は、取締役3名以上・監査役1名以上が必要となりますが、小規模事業者の場合は取締役会を設けず、1人または2人での運営が主流です。
株主の人数と出資比率
株式会社の設立には1名以上の株主(発起人)が必要です。
会社法上、法人・個人問わず株主になれます。
発起人は設立時に最低1株以上を引き受ける必要があり、出資比率は柔軟に設定可能です。
| 株主数 | 出資の条件 | 備考 |
|---|---|---|
| 1名 | 発起人1名のみでも設立可能 | 単独出資でも設立可。親族や法人でも可。 |
| 2名以上 | 出資比率は自由(例 50%:50%など) | 複数株主の場合、株主間契約で権利義務を明確にするケースも多い。 |
なお、株主が複数名になる場合、出資割合によって経営権や議決権の行使に影響が及ぶため、あらかじめ定款や株主間契約などでトラブルを防止する工夫が重要です。
また、上場を前提とする場合は複数株主が必要となるなど別途規程が存在しますが、通常の設立時には株主も取締役も「1名」から構成することが可能です。
株式会社設立前に知っておきたいその他の要件

資本金の最低額について
株式会社を設立する際の資本金については、2006年の会社法改正により最低資本金制度が撤廃され、1円から設立が可能となりました。
それ以前は「1,000万円以上」という要件がありましたが、現在では自由な資本金設定が認められています。
ただし、事業開始直後の運転資金や社会的信用、金融機関との取引のしやすさ、税務調査での実態審査などに配慮し、十分な資本金額を準備することが実務上は重要です。
また、資本金額によって消費税の課税事業者判定や、官公庁・自治体の入札資格などに影響が出る場合もあります。
| 資本金額 | 消費税の取扱い | 社会的信用 |
|---|---|---|
| 1円〜99万円 | 原則2年間は免税事業者 | 信用面で不利な場合あり |
| 100万円〜299万円 | 原則2年間は免税事業者 | 小規模会社として認識されやすい |
| 300万円以上 | 原則2年間は免税事業者(一部例外あり) | 一定の信用を得やすい |
| 1,000万円以上 | 原則初年度から課税事業者 | 社会的信用が高い |
会社設立登記における必要書類
株式会社の設立登記には、法務局へ必要書類を一式提出することが求められます。
各書類の提出漏れや記載誤りは、設立手続きの遅延や受理拒否につながるため、十分に注意しながら準備しましょう。
| 書類名 | 概要 | 作成者 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 発起人決定書 | 本店所在地や役員選任等を決議 | 発起人 | 複数発起人の場合は連名 |
| 定款 | 会社の根本規則 | 発起人 | 公証人による認証が必須 |
| 設立時取締役・監査役就任承諾書 | 役員への就任同意 | 各役員本人 | 就任予定者が直筆署名 |
| 設立時取締役の印鑑証明書 | 本人確認のため必要 | 取締役本人 | 3か月以内発行分を用意 |
| 資本金の払い込みを証する書面 | 出資金が払い込まれた証明 | 発起人 | 金融機関の通帳コピー等 |
| 登記申請書 | 法務局への申請用書類 | 設立代表者 | 専用の様式あり |
この他にも、設立時の会社印(実印)の届け出や、場合によっては事業内容に必要な許認可関係書類の提出も必要となる場合があります。
求められる書類や証明書の種類・内容は、会社の事業目的や構成役員によって異なるケースがあるため、事前確認が非常に重要です。
<あわせて読みたい>
人数変更時の手続きや注意事項
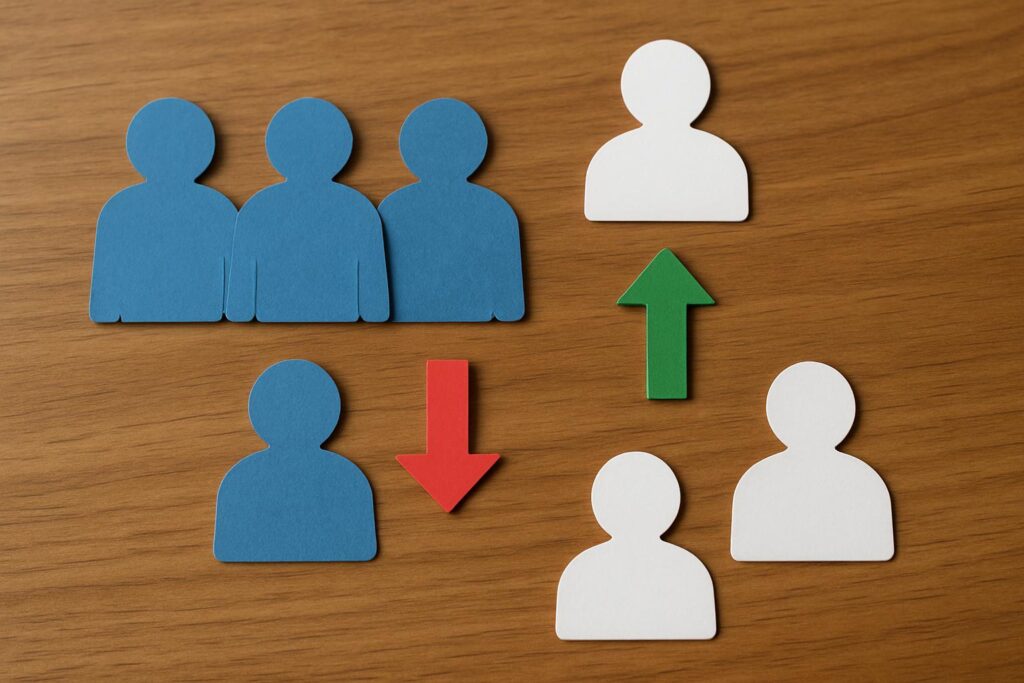
株式会社を設立した後、事業拡大や経営方針の変更等により、取締役や株主など役員や関係者の人数が増減するケースは少なくありません。
これらの人数変更には、法律上および実務上、適切な手続きが求められます。
人数変更は組織体制や経営管理の透明性、安定性とも密接に関わるため、以下のポイントをしっかりと押さえておくことが重要です。
取締役や株主が増減する場合の対応
株式会社では、事後的に取締役や株主の人数を変更する場合、社内での決議や法務局への登記など、所定の手続きが必要です。
特に、役員の増員・退任・交代や新たな株主の加入・退社が発生した場合は、その都度会社法に基づく適切な手続きを踏む必要があります。
| 変更対象 | 主な手続き | 必要な社内決議 | 登記義務 |
|---|---|---|---|
| 取締役の増減 | 株主総会での選任・解任決議、辞任届の提出等 | 株主総会普通決議 | 必要(2週間以内) |
| 代表取締役の変更 | 取締役会または株主総会での選定・解職決議 | 取締役会または株主総会 | 必要(2週間以内) |
| 株主の増減 | 株式譲渡契約、株主リストの更新等 | 基本的には不要(譲渡制限会社は取締役会の承認等) | 不要(登記事項ではない) |
人数変更に伴う議事録の作成や、必要に応じて株主名簿の整備も必須とされるため、法令や会社定款の定めに沿って手続きを進めましょう。
役員変更登記とその手順
取締役や監査役など、法定役員の人数が変わるときには、会社法および商業登記法に基づき、変更登記が義務付けられています。
この手続きを怠ると、過料(罰金)などの行政処分を受ける可能性があります。
以下に一般的な役員変更登記の流れを示します。
- 変更となる取締役や監査役に関する事項を株主総会または取締役会で決議する。
- 必要な場合、辞任届や就任承諾書を取得する。
- 議事録を作成し、署名または記名押印する。
- 登記申請書に必要書類(議事録、印鑑証明書、本人確認書類等)を添付。
- 法務局へ登記申請を行う(原則2週間以内)。
- 登記が完了したら、新メンバーを含めた最新の登記事項証明書を取得する。
取締役の変更登記は、人数増減だけでなく役職変更(例:代表取締役の交替)も対象となるため、うっかり手続きを忘れてしまわないよう注意しましょう。
また、定款で定められた取締役数の範囲内で適切に増減させる必要があります。
人数変更にあたっては、関係者との適切な連携・事前説明を怠らないことや、手続き漏れがないかをダブルチェックすることも、スムーズな会社運営のために不可欠です。
株式会社設立の人数に関するよくある質問
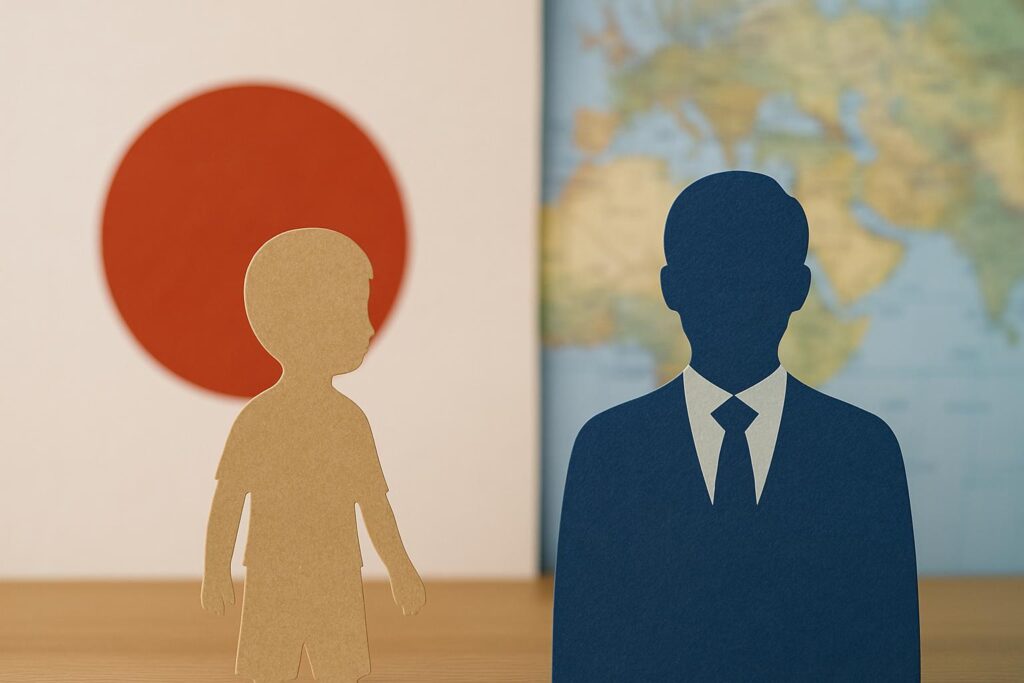
未成年や外国人も発起人や取締役になれるのか
株式会社設立にあたって、「未成年者」や「外国人」も発起人や取締役になることは法的に可能です。
ただし、いくつか留意点があります。
まず、未成年者が取締役等に就任する場合、親権者の同意を得る必要があります。
また、「未成年後見人」が必要となるケースもありますので、書類の準備を慎重に行いましょう。
外国人の場合は、日本国内に住所の有無を問わず登記手続きができます。
ただし、日本で生活するためには在留資格などの入国・滞在に関連する法的な制約があり、会社設立登記自体には制限はありませんが、ビザ申請や業務運営に関しては注意が必要です。
加えて、外国法人または海外在住者が設立メンバーになる場合、印鑑証明書やサイン証明など、日本語以外の証明書の翻訳や追加資料が求められる場合があります。
| 項目 | 未成年 | 外国人 |
|---|---|---|
| 発起人可否 | 可能(親権者等の同意要) | 可能 |
| 取締役可否 | 可能(親権者等の同意要) | 可能 |
| 必要書類 | 戸籍謄本、親権者同意書等 | 印鑑証明書、サイン証明等(翻訳含む場合あり) |
| 留意点 | 親権者の同意 成年後見制度の確認 | 在留資格等の確認 登記時の追加書類 |
家族や親族で設立する場合の注意点
家族や親族で株式会社を設立するケースも多く見受けられますが、その際にはいくつか特有の注意点があります。
- 意思決定や議決の際に私情が入りやすくなったり、「経営の透明性」や「責任区分」が曖昧になるリスクが考えられます。そのため、役割分担と意思決定プロセスを明確にし、定款や株主間契約による取り決めをしておくことが大切です。
- また、取締役や監査役の人数が少なくなりがちなため、重要な決議の手続きや義務に注意する必要があります。特に家族のみで構成される場合でも、適切な議事録の管理や役員登記の実施が求められます。
- 将来的な事業承継や株式の相続時にトラブルが生じないよう、「出資比率」「議決権」「権限」といった点について設立段階から合意形成し記録しておくことが望ましいです。
| リスク・ポイント | 対策方法 |
|---|---|
| 意思決定の偏りや対立 | 経営権限や決議方法を定款等に明記する |
| 責任区分の曖昧化 | 役割、職務分掌規程を策定・共有する |
| 将来的な相続・承継トラブル | 株主間契約の締結や、株式譲渡制限の設定 |
| 役員登記忘れ | 役員変更事項の漏れのない登記・議事録作成 |
まとめ
株式会社設立に必要な人数は、現在の会社法により発起人・取締役・株主すべて1名から設立が可能です。
資本金の下限も撤廃され、柔軟に起業できる環境が整っています。
ただし、設立後の役員構成や登記手続きには注意が必要ですので、最新の法律や必要書類を十分に確認しましょう。