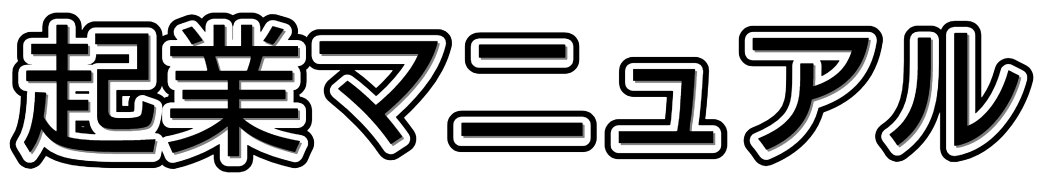合同会社の「出資しない社員」とは、結論から言うと出資をせずに業務執行権のみを持つ「業務執行社員」を指します。
本記事を読めば、業務執行社員の役割や権限、出資する社員との責任範囲の違いが明確になります。
専門スキルを持つ人材を経営に加えるメリット・デメリットや、定款で定める具体的な手続き、報酬の扱いまで、実務に役立つ知識を分かりやすく解説します。
合同会社における「出資しない社員」の正体
「合同会社に出資しない社員は置けるのか?」という疑問は、合同会社の設立や運営を検討している方からよく寄せられます。
結論から言うと、この「出資しない社員」という言葉は、実は少し誤解を含んだ表現です。
この章では、まずその言葉の本当の意味、つまり「正体」を明らかにしていきます。
合同会社の仕組みを正しく理解するためには、まず会社法で定められている「社員」という言葉の定義から知る必要があります。
一般的な会社員(従業員)とは意味が異なるため、ここを混同しないことが重要です。
原則として合同会社の社員は全員出資者
会社法において、合同会社の「社員」とは、会社への出資者であり、同時に会社の経営者を指します。
これは、株式会社における「株主」に近い立場と考えると分かりやすいでしょう。
つまり、合同会社を設立する際に資金を出した人が「社員」となり、原則として会社の経営に関する権利(業務執行権)と責任を負います。
このため、大原則として「出資をしていない人物」は、会社法上の「社員」にはなれません。
一般的な意味で使われる「社員(従業員)」と、会社法上の「社員(出資者)」は明確に区別されます。
両者の違いを以下の表にまとめました。
| 項目 | 会社法上の「社員」(合同会社) | 一般的な意味での「社員」(従業員) |
|---|---|---|
| 定義 | 会社の出資者であり、経営を担う構成員。 | 会社と雇用契約を結び、労働力を提供する労働者。 |
| 出資義務 | あり。出資をしなければ社員になれない。 | なし。出資義務は一切ない。 |
| 経営への関与 | 原則として業務執行権を持ち、経営に参加する。 | 業務命令に従い、定められた職務を遂行する。 |
| 立場 | 経営者 | 労働者 |
このように、法律上のルールでは「出資」と「社員であること」は一体不可分です。
この原則を踏まえると、「出資しない社員」という存在は矛盾しているように聞こえます。
では、なぜこのような言葉が使われるのでしょうか。
「出資しない社員」とは業務執行権を持つ社員を指す
検索キーワードにもなっている「出資しない社員」の正体、それは多くの場合、出資はしていないものの、会社の経営を執行する権限を持つ「業務執行社員」を指しています。
合同会社では、原則として出資者である全社員が業務執行権を持ちます。
しかし、会社の憲法ともいえる「定款」で特別な定めを置くことで、業務を執行する社員を特定の人に限定することが可能です。
この、業務執行権を持つ社員のことを「業務執行社員」と呼びます。
そして、会社法の重要なポイントとして、定款で定めることで、出資者ではない第三者を「業務執行社員」として迎え入れることが認められています。
つまり、「出資しない社員」とは、厳密には会社法上の「社員(出資者)」ではないものの、定款の定めによって業務執行権を与えられ、経営の中核を担う人物のことなのです。
この人物は、出資をしていないため法律上の社員ではありませんが、経営に深く関与することから、俗に「出資しない社員」と呼ばれているのです。
この仕組みにより、資金力はないものの、卓越したスキルやノウハウ、人脈を持つ専門家を経営陣に加えることが可能になります。
合同会社の業務執行社員とは何か

前の章で触れた「出資しない社員」の正体は、多くの場合、この「業務執行社員」を指します。
合同会社の経営において中心的な役割を担う業務執行社員とは、具体的にどのような存在なのでしょうか。
ここでは、その役割や権限、そして業務執行権を持たない社員との明確な違いについて詳しく掘り下げていきます。
業務執行社員の役割と権限
業務執行社員とは、その名の通り、合同会社の業務を執行する権限を持つ社員のことを指します。
会社の経営方針を決定し、日々の事業運営を担う、いわば会社のエンジン部分です。出資しているだけの社員とは異なり、会社の経営に直接的に関与します。
主な役割と権限は以下の通りです。
- 業務執行権:会社の事業運営に関する一切の行為を行う権限です。これには、商品の仕入れや販売、サービスの提供、従業員の採用や管理、資金調達の計画などが含まれます。
- 代表権:会社を代表して、外部と契約を締結したり、訴訟を提起したりするなど、法的な行為を行う権限です。原則として、業務執行社員は全員がこの代表権を持ちます。ただし、定款で特定の業務執行社員のみを「代表社員」と定めることで、代表権を限定することも可能です。
つまり、業務執行社員は会社の「経営者」としての立場であり、その行動が会社の成果や信用に直結する重要なポジションなのです。
業務執行権を持たない社員との違い
合同会社には、業務執行社員の他に「業務執行権を持たない社員」が存在します。
これは、出資はしているものの、会社の経営には直接関与しない社員のことです。投資家やサイレントパートナーのような立場と考えると分かりやすいでしょう。
業務執行社員と業務執行権を持たない社員の違いを、以下の表にまとめました。
| 比較項目 | 業務執行社員 | 業務執行権を持たない社員 |
|---|---|---|
| 経営への関与 | 積極的に経営に関与する(経営者) | 原則として経営には関与しない(出資者) |
| 主な役割 | 事業計画の立案・実行、契約締結、資金管理、従業員の監督など、会社の運営全般 | 会社の経営状況を監視する(業務・財産状況の調査権など) |
| 主な権限 | 業務執行権、代表権(原則) | 会社の業務および財産の状況を調査する権利、利益の配当を受ける権利など |
| 定款での定め | 定款で「業務執行社員」として定める必要がある(定めない場合は全社員が業務執行社員となる) | 業務執行社員を定款で定めた場合の、それ以外の社員 |
このように、両者は会社の経営における立ち位置が全く異なります。
業務執行社員は会社の舵取りを担う「船長」や「航海士」であり、業務執行権を持たない社員は、その航海に必要な資金を提供する「スポンサー」のような関係性と言えるでしょう。
出資しない社員(業務執行社員)とその他の社員との違いを比較
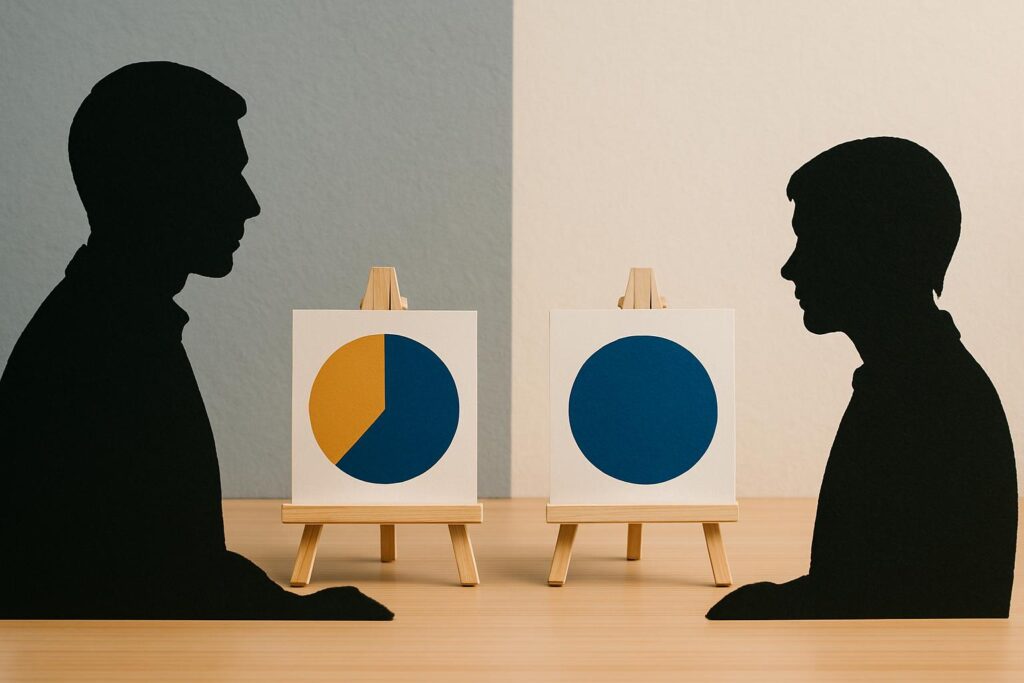
合同会社における「社員」は、一般的に使われる「従業員」とは意味が大きく異なります。
会社の所有者である出資者と、経営を担う業務執行者という二つの側面を持ちますが、定款の定めによってその役割は細分化されます。
特に「出資しない社員」を置く場合、その権限や責任は他の社員とどう違うのでしょうか。
ここでは、それぞれの立場を3つの重要なポイントで比較し、その違いを明確にします。
まずは、それぞれの社員の立場と役割の違いを一覧表で確認しましょう。
| 比較項目 | 出資しない社員(業務執行社員) | 出資する業務執行社員 | 出資のみを行う社員 |
|---|---|---|---|
| 出資義務 | なし | あり | あり |
| 業務執行権 | あり | あり | なし |
| 代表権 | 定款の定めや互選により就任可能 | 定款の定めや互選により就任可能 | なし |
| 会社債務への責任 | 有限責任(直接的な個人責任は負わない) | 有限責任(出資額の範囲内) | 有限責任(出資額の範囲内) |
比較1 出資義務の有無
合同会社の社員における最も根本的な違いは、会社への出資義務があるかどうかです。
通常の社員は、会社法に基づき、会社の設立時または加入時に定款で定められた金額を出資する義務を負います。
この出資金が会社の資本となり、事業活動の元手となります。つまり、原則として合同会社の社員は会社の所有者(オーナー)の一人なのです。
一方、「出資しない社員」は、その名の通り、金銭的な出資義務を一切負いません。
彼らは資金を提供する代わりに、経営に関する専門的な知識、技術、あるいは豊富な人脈といった無形の価値を提供することを期待されています。
これは、定款に「金銭以外の財産のみをもって出資の目的とすることができる」という規定や、業務執行社員を社員の中から定める規定を設けることで可能になります。
比較2 業務執行権と代表権
次に出資の有無と並んで重要なのが、会社の経営にどこまで関与できるか、という権限の違いです。
「業務執行権」とは、会社の事業運営に関する意思決定を行い、それを実行する権限のことです。
定款に特別な定めがなければ、合同会社では社員全員が業務執行権を持ちます。
しかし、定款で特定の社員を「業務執行社員」と定めた場合、業務執行権はその業務執行社員に限定され、他の社員は経営に関与できなくなります。
「出資しない社員」は、経営への参画を目的として迎え入れられるため、必ず業務執行社員として定められます。
したがって、彼らは必ず業務執行権を持つことになります。
さらに、「代表権」は会社を法的に代表し、契約などの法律行為を行う権限を指します。
業務執行社員が複数いる場合、原則として各自が代表権を持ちますが、定款や社員の互選によって特定の「代表社員」を定めることもできます。
出資しない業務執行社員も、他の業務執行社員と同様に代表社員に選任される資格がありますが、必ずしも代表権を持つわけではない点に注意が必要です。
比較3 経営に対する責任の範囲
会社の経営に関わる以上、その結果に対する責任は避けて通れません。
合同会社の社員が負う責任の範囲は、会社の形態を特徴づける重要な要素です。
まず、合同会社の最大の特徴として、社員全員が「有限責任」である点が挙げられます。
これは、会社の債務に対して、社員が負う責任が出資額の範囲内に限定されるという原則です。
万が一会社が倒産しても、出資した金額以上の返済を求められることはなく、個人の資産まで差し押さえられることはありません。
これは株式会社の株主と同じ考え方です。
では、出資をしていない社員の責任はどうなるのでしょうか。
出資額がゼロであるため「出資額の範囲内」という基準が適用できません。
しかし、この場合でも有限責任の原則は維持されます。
つまり、出資しない社員も、会社の債務に対して直接的な個人責任を負うことはありません。
ただし、これはあくまで会社の外部の債権者に対する責任の話です。
業務執行社員である以上、会社に対しては「善管注意義務(善良な管理者の注意をもって業務を行う義務)」や「忠実義務」を負っています。
もし重大な過失や法令違反によって会社に損害を与えた場合は、会社に対して損害賠償責任を負う可能性があります。
これは出資の有無にかかわらず、すべての業務執行社員に共通する経営者としての責任です。
有限責任社員と無限責任社員
ここで、責任の範囲についてより深く理解するために、「有限責任社員」と「無限責任社員」の違いを明確にしておきましょう。
前述の通り、有限責任社員は、会社の債務に対して自分が出資した額を限度として責任を負います。
合同会社の社員は、出資の有無にかかわらず、この有限責任社員にあたります。
これに対して「無限責任社員」は、会社の債務に対して返済の限度額がなく、会社の財産で返済しきれない場合は個人の全財産をもって返済する義務を負う社員のことです。
この無限責任社員は、合名会社(全社員が無限責任)や合資会社(無限責任社員と有限責任社員で構成)といった他の持分会社に見られる形態です。
結論として、会社法上、合同会社に「無限責任社員」は存在しません。
したがって、「出資しない社員」が無限の責任を負わされるのではないかという心配は不要です。
すべての社員が有限責任の範囲内で保護されている点が、合同会社の大きなメリットの一つと言えるでしょう。
合同会社に出資しない社員を置くメリット

合同会社において、出資を伴わない業務執行社員を設置することは、会社の成長戦略上、非常に有効な選択肢となり得ます。
資金的な制約を超えて、経営の柔軟性と専門性を高めることができるためです。
ここでは、出資しない社員を置くことによって企業が得られる具体的なメリットを3つの側面から詳しく解説します。
専門的な知識やスキルを持つ人材を経営に加えられる
最大のメリットは、出資という金銭的なハードルなしに、特定の分野で高度な専門性や豊富な経験を持つ人材を経営陣に迎え入れられることです。
会社の成長フェーズにおいて不足している知識やスキルを、外部の専門家を業務執行社員として登用することで直接的に補強できます。
例えば、以下のようなケースが考えられます。
- 革新的な技術を持つが、マーケティングや営業戦略に課題を抱えるITベンチャーが、マーケティングのプロを業務執行社員として迎える。
- 優れた製品を開発したが、法務や財務の知識が不足している製造業が、弁護士や公認会計士を経営メンバーに加える。
- 事業拡大を目指す中で、組織マネジメントの経験が豊富な人材を招き入れ、強固な組織基盤を構築する。
このように、会社の弱点を的確に補い、事業の成長を加速させるための「切り札」として、専門スキルを持つ業務執行社員の存在は極めて重要になります。
出資義務がないため、相手にとっても参画のハードルが低く、交渉を進めやすい点も大きな利点です。
資金がなくても優秀な人材を確保できる
特に創業期のスタートアップや中小企業にとって、自己資金が潤沢でないことは珍しくありません。
このような状況下で、経営手腕や実績を持つ優秀な人材を確保しようとしても、「出資」が条件となると、候補者が限られてしまいます。
しかし、業務執行社員の制度を活用すれば、候補者の資金力に関わらず、その人物の能力や経験、ビジョンへの共感を基準に経営チームを構築できます。
手元に資金はないものの、経営者としての優れた資質を持つ人物や、特定の業界で強力なネットワークを持つ人物を仲間に引き入れることが可能になるのです。
これにより、資金調達力に左右されることなく、事業成功の可能性を高める理想的な経営体制を目指せます。
人材獲得の選択肢が格段に広がることは、競争の激しい現代市場において大きなアドバンテージとなるでしょう。
外部からの信頼性が向上する
業界内で著名な人物や、特定の分野で高い評価を受けている専門家が業務執行社員として経営に参画している事実は、会社の対外的な信用力を大きく向上させます。
出資者である社員だけでなく、客観的な実績を持つ専門家が経営判断に関わっているという事実そのものが、金融機関や取引先、顧客、そして将来の従業員に対する強力なアピールポイントとなるのです。
これにより、以下のような具体的な効果が期待できます。
| 信頼性向上の対象 | 期待される具体的な効果 |
|---|---|
| 金融機関 | 事業計画の説得力が増し、融資審査において有利に働く可能性があります。 |
| 取引先 | 安定した経営基盤があると判断され、新規取引の開始や有利な条件での契約締結につながりやすくなります。 |
| 採用候補者 | 魅力的な経営陣がいる企業として認知され、優秀な人材の採用競争において優位に立てます。 |
このように、業務執行社員の存在は、単なる社内の役割分担に留まらず、会社のブランド価値や社会的信用を高めるための重要な経営戦略の一環と言えるのです。
合同会社に出資しない社員を置くデメリット

専門的なスキルを持つ人材を経営陣に加えられるなど、多くのメリットがある「出資しない社員(業務執行社員)」の設置ですが、その一方で慎重に検討すべきデメリットやリスクも存在します。
メリットの裏返しともいえるこれらの課題を事前に理解し、対策を講じておくことが、安定した会社経営の鍵となります。
社員間の意見対立が起こりやすい
合同会社に出資しない業務執行社員を置く場合、最も懸念されるのが社員間の意見対立です。
この対立は、それぞれの立場の違いから生じることが多く、経営の根幹を揺るがす問題に発展する可能性があります。
対立の主な原因は、会社経営における金銭的なリスクを負っているか否かという根本的な違いにあります。
出資している社員(出資者)は、自身の資金を投じているため、投資の回収や短期的な利益確保を重視する傾向があります。
一方で、出資していない業務執行社員は、自身の専門性を活かした事業の成長や、長期的なブランド価値の向上、理想の追求などに重きを置くことがあります。
例えば、以下のような場面で意見が衝突する可能性があります。
- 多額の先行投資が必要な新規事業の提案(業務執行社員)に対し、リスクを懸念して反対する出資者
- 短期的な売上向上策を求める出資者と、品質やブランドイメージを重視し、安易な値下げに反対する業務執行社員
- 利益の内部留保を主張する出資者と、自身の報酬引き上げを求める業務執行社員
こうした価値観の違いが顕在化すると、社員間の信頼関係が損なわれ、円滑な会社運営が困難になるリスクがあります。
意思決定のスピードが遅くなる可能性がある
合同会社の強みの一つに、迅速な意思決定が挙げられます。
しかし、出資しない業務執行社員がいることで、このメリットが損なわれる可能性があります。
合同会社の業務執行は、定款に別段の定めがない限り、社員の過半数をもって決定します。
しかし、会社の事業目的の変更や定款の変更といった会社の根幹に関わる重要な事項については、原則として総社員の同意が必要です。
業務執行社員が提案した経営戦略について、その他の出資者が納得せず、同意が得られない場合、議論は平行線をたどり、意思決定は停滞してしまいます。
特に、出資者側が「リスクが高い」「リターンが見合わない」と判断した場合、業務執行社員がいくらその専門的見地から必要性を説いても、合意形成は難航するでしょう。
市場の変化が激しい現代において、意思決定の遅れは致命的な機会損失につながりかねません。
業務執行権を持つ社員と持たない社員との間で、経営方針を巡るコンセンサス形成に時間がかかり、結果としてビジネスチャンスを逃してしまうリスクがあることは、大きなデメリットと言えます。
責任の所在が曖昧になるリスク
出資しない業務執行社員を置くことで、「業務執行の責任」と「経営結果に対する金銭的な責任」の所在が複雑になり、曖昧になるリスクがあります。
合同会社の社員は、出資額を限度として会社の債務に対して責任を負う「有限責任社員」です。
つまり、会社が倒産した場合、最終的な金銭的損失を被るのは、あくまで出資している社員です。
一方、出資していない業務執行社員は、業務を遂行する上での善管注意義務や忠実義務は負いますが、会社の債務に対して直接的な金銭的責任を負うことはありません。
この構造の違いをテーブルで比較してみましょう。
| 責任の種類 | 出資しない業務執行社員 | 出資しているその他の社員 |
|---|---|---|
| 業務執行に関する責任 (善管注意義務など) | 負う | 原則として負わない |
| 会社の債務に対する金銭的責任 | 負わない | 負う(出資額が限度) |
| 経営判断の失敗による損失 | 直接的な金銭負担はない | 出資額の範囲で損失を被る |
このように、業務執行社員の経営判断ミスによって会社に多大な損害が生じた場合でも、その金銭的なダメージを直接的に負担するのは出資者となります。
この状況は、出資者側から見れば「リスクは我々が負うのに、決定権は彼にある」という不公平感につながりやすく、社員間の溝を深める原因となり得ます。
トラブルが発生した際に、責任の所在を巡って深刻な対立に発展するリスクを内包しているのです。
出資しない社員を業務執行社員にするための手続き

合同会社において、出資を伴わない専門家などを経営に参加させる「出資しない社員(業務執行社員)」を置く場合、法的な手続きを正確に踏むことが不可欠です。
この手続きは大きく分けて「定款の変更」と「法務局への登記申請」の2つのステップで構成されます。
これらの手続きを怠ると、法的な効力が認められないだけでなく、後々のトラブルの原因にもなりかねません。
ここでは、具体的な手続きの流れと注意点を詳しく解説します。
定款への記載が必須
合同会社では、原則としてすべての社員が業務を執行する権利を持ちます。
しかし、特定の社員のみを業務執行社員と定め、その他の社員には業務執行権を与えないようにするためには、その旨を会社の憲法ともいえる「定款」に明確に定める必要があります。
これは会社法第591条第1項で規定されている要件です。
定款の変更には、原則として「総社員の同意」が必要となります。
既存の社員全員が、新たに出資しない業務執行社員を迎え入れること、そしてそれに伴う定款の変更内容について合意形成をすることが、最初の一歩となります。
定款への具体的な記載例
定款には、誰が業務執行社員であるかを第三者から見ても明確にわかるように記載します。
以下に具体的な記載例を挙げます。
| 【記載例1:特定の社員のみを業務執行社員とする場合】 (業務執行社員) 第〇条 当会社の業務は、社員〇〇〇〇及び社員△△△△が執行する。 2 前項以外の社員は、当会社の業務を執行しない。 【記載例2:出資しない外部の専門家を業務執行社員として迎える場合】 (業務執行社員) 第〇条 当会社の業務を執行する社員(以下「業務執行社員」という。)は、次の者とする。 (1)住所 東京都千代田区〇〇一丁目一番一号 氏名 〇〇 〇〇 (2)住所 神奈川県横浜市〇〇区〇〇一丁目二番三号 氏名 △△ △△ 2 社員□□□□は、当会社の業務を執行しない。 |
このように、業務を執行する社員と執行しない社員を明確に区別して記載することが重要です。
また、業務執行社員の中から会社の代表者となる「代表社員」を定める場合は、その旨も定款に記載するか、業務執行社員の互選によって定める旨を規定します。
法務局への登記手続き
定款で業務執行社員を定めただけでは、手続きは完了しません。
その変更内容を法務局に届け出て、商業登記簿に反映させる「変更登記」を行う必要があります。
登記を行うことで、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)に業務執行社員の氏名や住所が記載され、取引先などの第三者に対してその権限を公的に証明(対抗)できるようになります。
この変更登記は、定款変更の効力が発生した日(通常は総社員の同意があった日)から2週間以内に、会社の本店所在地を管轄する法務局へ申請しなければなりません。
登記申請には、以下の書類が必要となります。
司法書士に依頼することも可能ですが、ご自身で手続きを行う際の参考にしてください。
| 書類名 | 概要と注意点 |
|---|---|
| 合同会社変更登記申請書 | 法務局のウェブサイトでテンプレートを入手できます。変更内容や登録免許税(収入印紙)を貼付して提出します。 |
| 総社員の同意書 | 定款変更について、総社員が同意したことを証明する書面です。総社員が記名押印します。定款自体を「総社員の同意書」として援用することも可能です。 |
| 業務執行社員の就任承諾書 | 新たに追加された業務執行社員が、その就任を承諾したことを証明する書面です。個人の実印を押印するのが一般的です。 |
| 印鑑証明書 | 就任承諾書に押印した実印の印鑑証明書です。市区町村役場で発行されたもの(通常は発行後3ヶ月以内)を添付します。 |
| 委任状 | 手続きを司法書士などの代理人に依頼する場合に必要となります。 |
登記申請にかかる登録免許税は、原則として1万円です(資本金の額が1億円を超える場合は3万円)。
これらの書類を揃え、期限内に法務局へ提出することで、出資しない社員を正式に業務執行社員として迎え入れる手続きが完了します。
出資しない社員の報酬と社会保険の扱い

合同会社において、出資をせずに経営に参加する「業務執行社員」。その法的な立場は、従業員とは大きく異なります。
そのため、報酬の税務上の扱いや社会保険の加入についても、特別なルールが適用されます。
ここでは、業務執行社員の報酬と社会保険について、具体的な取り扱いを詳しく解説します。
報酬は役員報酬として扱われる
出資しない社員、すなわち業務執行社員へ支払われる報酬は、従業員に支払う「給与所得」ではなく、税法上の「役員報酬」として扱われます。
会社法上、合同会社の業務執行社員は「役員」とは定義されていませんが、税法上では法人の経営に従事していることから「みなし役員」に該当するためです。
この「役員報酬」という扱いが、税務上非常に重要なポイントとなります。
従業員の給与は、原則として全額を会社の経費(損金)に算入できます。
しかし、役員報酬は、利益操作を防ぐ目的から、原則として損金に算入することができません。
ただし、以下のいずれかの要件を満たすことで、例外的に損金への算入が認められます。
- 定期同額給与: 毎月決まった時期に、同額の報酬を支払う方法です。事業年度開始から3ヶ月以内に金額を決定し、その事業年度中は原則として金額を変更できません。多くの会社で採用されている最も一般的な方法です。
- 事前確定届出給与: 賞与(ボーナス)のように、特定の時期にまとまった金額を支払う場合に利用します。事前に「誰に」「いつ」「いくら」支払うかを税務署に届け出る必要があります。届出た内容と異なる金額や時期に支給した場合は、全額が損金不算入となるため注意が必要です。
- 業績連動給与: 会社の利益などの業績指標に連動して報酬額が変動するものです。算定方法が客観的かつ公正である必要があり、有価証券報告書での開示が求められるなど、主に上場企業で用いられる制度です。
したがって、業務執行社員に報酬を支払う際は、定款または総社員の同意によって報酬額を決定し、上記のいずれかの方法に沿って支給しなければ、法人税の負担が大きくなるリスクがあることを十分に理解しておく必要があります。
社会保険の加入義務について
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入についても、業務執行社員は役員と同様の扱いを受けます。
法人の代表者や役員は、たとえ一人社長であっても、法人から報酬を受けている限り、原則として社会保険への加入が義務付けられています。
同様に、出資しない業務執行社員も、法人から労務の対償として報酬を受けている場合、常勤・非常勤の別を問わず、原則として社会保険の被保険者となります。
たとえ報酬が少額であっても、加入義務が発生するのが基本です。
一方で、労働保険(雇用保険・労災保険)の扱いは異なります。
以下の表で、保険の種類ごとの加入義務について整理します。
| 保険の種類 | 出資しない社員(業務執行社員)の加入義務 |
|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険 (社会保険) | 原則として加入義務あり。法人から労務の対償として報酬を受けていれば、常勤・非常勤を問わず被保険者となります。ただし、代表権がなく業務執行への関与も限定的で、報酬が社会通念上役員報酬とは認められないほど低額な場合など、ごく例外的に加入対象外となるケースもあります。 |
| 雇用保険 | 原則として加入不可。雇用保険は「労働者」を対象とするため、経営者側の立場である業務執行社員は原則として被保険者になれません。ただし、業務執行社員でありながら、同時に部長や課長など従業員としての身分も併せ持つ「兼務役員」で、労働者性が強いと認められる場合は加入できる可能性があります。その際は、ハローワークへ「兼務役員雇用実態証明書」などの書類を提出し、判断を仰ぐ必要があります。 |
| 労災保険 | 原則として対象外(特別加入制度あり)。労災保険も労働者の保護を目的とするため、業務執行社員は原則として対象外です。しかし、業務の実態が労働者に近い場合など、一定の要件を満たせば「特別加入制度」を利用して任意で加入することができます。 |
このように、出資しない社員(業務執行社員)を置く場合、その報酬や社会保険の取り扱いには専門的な知識が求められます。
税務や社会保険の手続きを誤ると、追徴課税や加入指導などのペナルティを受ける可能性もあるため、不明な点があれば税理士や社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
合同会社の「出資しない社員」とは、定款の定めによって業務執行権のみを持つ社員(業務執行社員)を指します。
原則として合同会社の社員は出資者ですが、この制度を活用することで、資金がなくても専門知識を持つ優秀な人材を経営陣に加えることが可能です。
ただし、社員間の意見対立などのリスクも伴います。
出資しない業務執行社員を置く場合は、定款への記載と法務局への登記が必須となるため、メリットとデメリットを理解した上で慎重に検討しましょう。