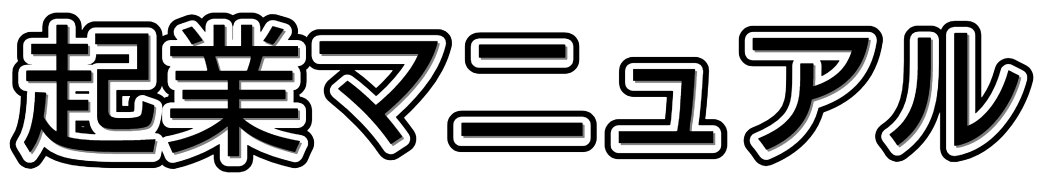「合同会社の設立を自分で行いたい」とお考えの方へ。
この記事では合同会社と株式会社の違いや、自分で設立するための具体的な流れ、必要書類、手続きの注意点まで初心者にも分かりやすく徹底解説します。
この記事を読めば、主要な失敗を避けてスムーズに手続きできる知識と実践的なノウハウが身につき、専門家に依頼すべきケースまで判断できるようになります。
合同会社とは何かと株式会社との違い
合同会社の基本的な特徴
合同会社(LLC:Limited Liability Company)とは、2006年の会社法改正によって新たに設けられた会社形態であり、1名からでも設立可能な小規模事業者に適した法人組織です。
合同会社は出資者全員が業務執行権限を持つ「社員」となり、経営と所有が一致している点が最大の特徴です。
また、構成員は有限責任であり、出資した範囲でのみ責任を負います。
合同会社は定款自治の度合いが高く、出資比率にかかわらず利益配分比率などを自由に定めることができます。
設立費用が比較的安価で、運営の柔軟性に優れていますが、一般的な認知度や社会的信用という点では株式会社に比べてやや劣る場合があります。
株式会社との主な違い
合同会社と株式会社にはいくつかの明確な違いがあります。
特に設立手続き、経営体制、利益分配、社会的信用、コスト面などで相違しています。
以下の表に主な違いをまとめます。
| 項目 | 合同会社 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 設立時の費用 | 約6万円(登録免許税のみ) ※定款認証不要 | 約20万円(登録免許税・定款認証代が必要) |
| 出資者の責任 | 有限責任 | 有限責任 |
| 経営の意思決定 | 社員全員で原則決定。定款で取り決め可能 | 取締役・株主総会など、法定の機関設計が必要 |
| 利益配分 | 出資比率に関係なく定款で自由に決定 | 原則、出資比率(株式数)に応じて分配 |
| 社会的信用度 | やや低い場合もある | 高い(ビジネス取引や金融機関などで有利) |
| 機関設計 | 自由度が高く、取締役会や監査役の設置は不要 | 取締役会、監査役等の法定機関が必要な場合あり |
| 決算公告義務 | なし | あり(官報などで公告が必要) |
| 設立後の運営コスト | 比較的低い | やや高め |
| 株式発行 | 不可 | 可能 |
合同会社は出資者=経営者であり、運営のシンプルさと合理性が魅力ですが、株式会社は社会的信用や資金調達面で有利です。
それぞれの特徴を理解したうえで、自分の事業に最適な会社形態を選ぶことが重要です。
合同会社のメリットとデメリット
合同会社の主なメリットは次の通りです。
- 設立費用が安い・手続きが簡単(定款認証不要、登録免許税も安価)
- 意思決定が迅速で柔軟(経営者自身が直接事業運営に携わるため)
- 利益配分の自由度が高い(出資割合に関係なく定款で自由に決定可能)
- 決算公告義務がない(官報掲載などの公告コストが発生しない)
- 維持コストが抑えられる(運営の自由度が高く、煩雑な手続きも少ない)
一方で、合同会社のデメリットには以下の点が挙げられます。
- 対外的な信用度が株式会社に比べて劣る場合がある(大企業や金融機関、取引先によっては株式会社を優先するケースもある)
- 株式発行ができないため、広範な資金調達やストックオプション発行が不可能
- 出資者全員が原則として経営に関与する必要がある(投資専門の社員だけの設置が難しい)
- まだ比較的新しい会社形態であり、認知度が十分でない
自分で合同会社を設立する場合、こうした特徴と株式会社との主な違いを把握したうえで、事業の規模や目的に合わせた選択を行うことが非常に重要です。
合同会社設立を自分で行う前に準備すること

事業計画と会社の基本事項の決定
合同会社を自分で設立する場合、まずは事業内容や将来のビジョンを明確にした事業計画書を作成しましょう。
事業計画の立案は、資金調達や金融機関・取引先への説明の際にも役立ちます。
また、会社設立に必要な基本事項を下記のように整理することが大切です。
| 決定事項 | 内容のポイント | 注意点 |
|---|---|---|
| 商号(会社名) | 他社と重複しない独自性のある名称を選ぶ(漢字・カタカナ・ひらがな使用可) | 商標登録や法務局での類似商号チェックが必要 |
| 本店所在地 | 活動拠点となる住所を決定(レンタルオフィス、自宅可) | 現実の使用権がある住所か確認 |
| 事業目的 | 具体的かつ将来拡張を意識した表現で記載 | 法務局が不明確と判断すると訂正要請あり |
| 資本金額 | 1円以上で可能(資本金の額により信用や融資の可否に影響) | 登記後の変更は手続きが複雑 |
| 出資者(社員)構成 | 1人でも設立可、複数人の場合は出資比率を決定 | 社員間のトラブル防止のため契約内容を明確化 |
| 決算期 | 事業に適したタイミング(月末など)で決定 | 変更には登記が必要な場合あり |
代表社員・社員・本店所在地などの決め方
合同会社設立には、代表社員(代表者)や社員(出資者)の決定が不可欠です。
代表社員は会社を対外的に代表し、業務執行社員として実務も担います。
1名設立も可能ですが、複数名で設立する場合は、業務分担や意思決定方法もしっかり協議しましょう。
本店所在地については、賃貸物件(オフィスビル、シェアオフィスなど)の場合、契約時に事務所利用許可や登記可否の確認が重要です。
自宅を利用する際は、賃貸契約などで事業利用の制限がないか事前に確認します。
出資方法についても、金銭のみならず現物出資(パソコン、事務機器など)をする場合は、現物出資物件の評価や登記方法について、明確な資料や証明を用意しましょう。
さらに、設立後の運営やトラブルを未然に防ぐため、社員間の合意内容(業務執行権限、利益配分、退社時の扱いなど)を「社員間契約書」や「覚書」として書面化することが推奨されます。
これは後々の紛争回避に役立ちます。
自分でできる合同会社設立の具体的な流れ

定款作成のポイント
合同会社設立でもっとも重要なステップの一つが定款(ていかん)の作成です。
定款とは、会社の基本的なルールや組織運営の仕組みを定めた書面で、会社の設立後も経営の根幹となるものです。
自分で作成する場合にも、公序良俗に反しない内容とすることが必須です。
なお、合同会社の場合は株式会社と異なり、公証役場での認証は不要です。
定款に記載すべき内容
合同会社の定款に記載する絶対的記載事項は、以下の通りです。
これらの事項を定めていない定款は無効となります。
| 記載項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社の目的 | どのような事業を行うかを具体的に示す(複数記載可能) |
| 商号 | 会社名(必ず「合同会社」を含める必要あり) |
| 本店所在地 | 会社の住所(詳細な住所ではなく、最小行政区まで記載可能) |
| 社員の氏名または名称及び住所 | 出資者全員(個人・法人)の氏名/名称および住所 |
| 社員の有限責任 | 社員は出資額の範囲で責任を負う旨 |
| 社員の出資の目的と価格 | 現金出資か物的出資か、その額や内容 |
これに加え、任意的記載事項として業務執行社員の決定方法や利益配分、決算期、公告方法などを規定することで、将来のトラブル防止につながります。
定款サンプルと雛形について
定款サンプルや雛形は、法務局や各種専門書、インターネット上の信頼できるサイトで公開されています。
内容をコピーするだけでなく、自社の事業内容や運営方針に合わせてアレンジすることが大切です。
定款は登記申請時に提出するため、印刷した後に1通に製本した上で全社員の捺印が必要となります。
定款認証は必要か
合同会社の設立においては、株式会社と違い公証役場で定款認証を受ける必要はありません。
そのため、手続きが簡略でコストが抑えられるというメリットがあります。
ただし、定款の記載内容に不備があると法務局での登記申請時に補正を求められるため、記載内容には十分注意しましょう。
資本金の払い込み方法
定款の作成が完了したら、資本金を払い込みます。
手順は以下の通りです。
- 代表社員個人名義の銀行口座を準備(設立前なので会社名義口座は使えません)
- 各社員が出資金額を口座に振り込み
- 通帳の表紙、最初のページ、資本金の振込みが記載されたページのコピーを用意
- 資本金の払込証明書を作成(後述の登記書類で提出)
会社設立時点の銀行振込明細や通帳コピーは必須書類です。
登記申請書類の準備と作成
合同会社の設立登記に必要な書類は多岐にわたります。
ミスや漏れがあると補正や再提出が必要になるため、提出前に複数回チェックしましょう。
登記申請書、代表社員の就任承諾書、印鑑届書など
主な提出書類と内容は以下の通りです。
| 書類名 | 内容・ポイント |
|---|---|
| 登記申請書 | 法務局に提出する主要な書類。会社の基本事項を記載。 |
| 定款 | 作成・捺印済みの定款原本(謄本提出)、コピーも用意。 |
| 代表社員の就任承諾書 | 代表社員が就任を承諾したことを示す書面。 |
| 資本金の払込証明書 | 資本金振込の事実を証明。通帳コピーが添付資料となる。 |
| 印鑑届書 | 会社実印(法人印)を登録するための書類。 |
| 本人確認書類(印鑑証明書など) | 発起人・代表社員の身元・住所等確認のため。 |
これらのほか、場合によっては委任状や住所証明書などが必要なケースもあります。
必要な印鑑や印鑑証明について
合同会社設立には、以下の印鑑が必要です。
- 会社実印(法人印)
- 銀行印
- 角印(認印)
会社実印は必ず事前に作成し、印鑑届書とともに法務局で登録します。
代表社員個人の印鑑証明書も必須書類なので、早めに準備しましょう。
法務局への登記申請手続き
準備した書類一式を、本店所在地を管轄する法務局に提出します。
提出方法は「窓口持参」「郵送」「オンライン申請(商業登記・電子認証登記)」のいずれかを選べます。
登記申請日は会社の設立日となるため、記念日等の希望日があれば申請方法や締切に注意してください。
申請にかかる費用と登録免許税
| 項目 | 金額(2024年時点) | 概要 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 60,000円 | 合同会社設立の最低額。資本金の0.7%が60,000円を上回る場合は高い方。 |
| 印鑑作成費用 | 約5,000~20,000円 | 会社実印、銀行印、角印の費用(業者により変動) |
| その他 | 数百円~ | 定款印紙(合同会社は不要)、郵送費用など |
なお、合同会社の定款には収入印紙は不要です。
オンライン申請の可否
合同会社の設立登記申請は、商業登記・電子認証登記システム(登記・供託オンライン申請システム、いわゆる「申請用総合ソフト」)を利用してオンライン申請が可能です。
電子証明書やPDF化した書類の準備が必要となるため、電子環境が整っている場合は活用すると手続きが簡易化されます。
オンライン申請の場合でも登録免許税の金額は変わりませんが、窓口や郵送でのやりとりが省略できるというメリットがあります。
ここまでの流れを正確に踏むことで、専門家に依頼せず自分自身で合同会社を設立できます。
書類一つひとつに注意を払い、設立にかかる期間や費用、書類の正確性を意識して進めることがスムーズな設立へのコツです。
合同会社の設立時に必要な書類一覧と入手方法

合同会社の設立を自分で行う際には、正確で漏れのない書類準備が不可欠です。
申請ミスを防ぎ、スムーズに登記ができるよう、必要な書類とその入手方法をしっかり把握しておきましょう。
下記では、設立登記申請に必要な代表的な書類と、各書類の役割、取得・作成方法について解説します。
合同会社設立時に必要な書類一覧
| 書類名 | 概要 | 入手・作成方法 | 提出先 |
|---|---|---|---|
| 定款(原本) | 会社の基本的な規則や運営方針を定める書類。 | 自分で作成。ひな形を活用可。認証不要(合同会社の場合)。 | 法務局 |
| 登記申請書 | 会社設立登記を申請する際のメイン書類。 | 自分で作成。法務局HPや市販の書式を利用可。 | 法務局 |
| 代表社員の就任承諾書 | 代表社員が役職を引き受ける意思を表明する書類。 | 自分で作成。雛形を利用可。 | 法務局 |
| 社員全員の印鑑証明書 | 個人の場合は本籍地の市区町村役所、法人の場合は登記上の所在地の法務局で取得。 | 各市区町村役所・法務局で取得(発行後3か月以内が目安)。 | 法務局 |
| 資本金の払い込みを証明する書類 | 資本金の払込が行われたことを証明(預金通帳のコピーや払込証明書など)。 | 自分で作成、もしくは通帳のコピー・Web明細の印刷。 | 法務局 |
| 本店所在地決議書(必要な場合) | 設立時に本店所在地を決議したことを明らかにする書類。合同会社では原則不要だが、定款で記載が無く決議が必要な場合のみ提出。 | 自分で作成。雛形利用可。 | 法務局 |
| 印鑑届書(会社の代表印) | 会社の実印(法人成印)を登録するための書類。 | 法務局の窓口、または法務局HPから入手し記入。 | 法務局 |
| 払込証明書(必要に応じて) | 資本金の払い込みがあったことを証明。合同会社では通帳コピーでも可。 | 自分で作成。フォーマット利用可。 | 法務局 |
各書類の役割と書き方
各書類は、合同会社が法律的に適正に設立されたことを証明するための重要な役割を持ちます。
以下に主要書類の書き方ポイントをまとめます。
- 定款:会社名・目的・本店所在地・社員およびその出資額・業務執行社員の定めなど漏れなく記載します。シンプルな内容でOKですが、目的は具体的に(将来事業拡大も想定)。
- 登記申請書:会社名、所在地、設立年月日、代表社員氏名と住所などを正確に記載します。日付けや社名、住所の間違いに注意。
- 就任承諾書:代表社員本人が「就任を承諾する」旨を明記し、自署・押印します。
- 印鑑届書:会社実印を捺印し、他の必要事項も記入。印影はきれいに、薄すぎやかすれに注意。
- 払い込み証明書:会社設立時の資本金として払い込まれたことを証するもので、振込日・振込額・振込先を明記。通帳コピーを添付する場合は「表紙・表紙裏・記帳部分」の該当箇所が必要。
法務局や行政機関で取得する書類と入手方法
合同会社設立のためには、市区町村役場や法務局で発行される書類も必要です。
代表的な入手先とポイントは以下の通りです。
- 印鑑証明書:個人の場合は住所地の市区町村役場の窓口、マイナンバーカードをお持ちであればコンビニ交付対応自治体もあり。法人の場合は登記簿謄本を取得する際の法務局で発行。
- 印鑑届書:法務局の窓口または法務局ホームページからダウンロードし、所定事項を記入します。
- 定款の写し(控え):提出後、収入印紙不要ですが、控えを自己保管。電子定款の場合もPDFデータで保管します。
また、登記申請書や就任承諾書等は、法務局のウェブサイトや専門書籍、信頼のおける行政書士のホームページ等で雛形を入手できます。
これらを活用して漏れなく作成しましょう。
なお、書類の内容やフォーマットは各法務局で異なる場合もあるため、申請先法務局にあらかじめ確認するのが確実です。
書類準備の際は、「全ての書類で記載内容の整合性が取れているか」、「必要な印鑑が全て正しく押されているか」、「発行日や有効期限が過ぎていないか」など細かな点まで注意しましょう。
誤りがあると再提出や補正が必要となり、設立登記に遅れが生じる場合があります。
設立手続きを自分で行う場合、書類作成にあたってはひな形の忠実な活用と、法務局や専門機関の最新情報を必ず参照することが失敗を防ぐポイントです。
自分で合同会社設立手続きを行う際の注意点とよくある失敗例

書類不備による補正や再提出
合同会社設立を自分で行う場合、最も多いトラブルが提出書類の不備や記載ミスによる「補正」や「再提出」です。
特に、定款や登記申請書の記載漏れ・誤字脱字、添付書類(印鑑証明書や就任承諾書など)の不足、会社実印の不鮮明な押印などが原因となります。
書類が不完全なままでは登記が完了せず、法務局から訂正・追加を求められることになります。
これにより商業登記のスケジュールが遅れ、銀行口座の開設や事業開始にも影響が生じます。
また、法務局によっては細かい書式やポイントに違いがある場合があるため、提出前に必ず所轄法務局のホームページや電話などで最新の情報を確認することが重要です。
よくある失敗例の一覧
| 失敗例 | 主な原因 | 回避策 |
|---|---|---|
| 定款の目的欄が曖昧・不十分 | 許認可に必要な詳細が不足 | 主な業務内容・将来の事業も記載 |
| 印鑑証明書の有効期限切れ | 取得日から3ヶ月超を提出 | 提出直前に印鑑証明書を用意 |
| 資本金の払込口座名義誤り | 代表社員個人名でないと無効 | 発起人個人口座で払込 |
| 代表社員の就任日誤記載 | 会社設立日と食い違い | 他書類と同一日付で統一 |
| 書類の押印漏れ・印影不鮮明 | 会社実印、個人印押し忘れや薄い印影 | 押印箇所を複数回チェック |
定款・書類の内容確認と専門用語の理解不足
定款や登記申請書に使用される専門用語や法的根拠の理解不足による誤記入も頻発します。
「代表社員」と「業務執行社員」、「本店所在地」と「事務所所在地」など、似て非なる表現の区別を誤ると、法務局で受理されません。
また、定款の作成においては、「公告の方法」や「社員の責任範囲」などの必須事項を漏らす失敗も散見されます。
雛形のいわゆる「コピペ」だけに頼らず、自身の事業内容・目的に即した記載が必要です。
法務局提出時の注意点
提出時に必要となる書類が法務局ごとに異なることがあるため、必ず事前にチェックしてください。
特に、オンライン登記申請の場合は紙の提出が不要な書類もあれば、逆に電子署名が必要な場合もあります。
窓口で提出する際、原本と写し(コピー)を両方提出しなければならない書類や、収入印紙の貼付箇所を誤るといったケアレスミスもあります。
必ずチェックリストや法務局の案内を見ながら準備しましょう。
登記完了後の失念しがちな手続き
会社設立登記が完了した後も、税務署・各自治体への設立届出、社会保険・労働保険の届出など重要なアフターフォロー業務が多数残っています。
これらを失念し期限を過ぎてしまうと、罰則や追徴課税のリスクもあるので注意しましょう。
電子定款と紙定款の違いによる申請ミス
電子定款を自分で作成・申請する際は、Adobe Acrobatや電子署名サービス、ICカードリーダー等の専用機器が必要であり、慣れていないと形式エラーで申請できない事例もあります。
逆に紙定款は認証が不要ですが、印紙税4万円が必要となるなど費用面の違いも見落とされがちです。
| タイプ | 必要な準備 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 電子定款 | 電子署名・機器などIT知識 | エラー発生時の対応法を要確認 |
| 紙定款 | 印紙税4万円分 | 費用負担増加に注意 |
日本語の表現・住所表記にも注意
本店所在地の住所表記の仕方を誤る事例(建物名まで記入、番地の省略、通称名での記載など)も多く、登記が通りません。
住民票や公共料金の領収書等と同じ表記を正確に転記し、余計な情報を書かないように注意をしましょう。
業種・事業目的による特別な手続き漏れ
食品営業・古物商・運送業・建設業など特定の許認可が必要となる事業を行う場合、定款作成段階で事業目的欄に正しく明記しなければ、会社設立後に行政庁から許可を得られなくなる事例があります。
自身のビジネスが「許認可事業」に該当するか十分下調べを行いましょう。
設立日付の設定に注意
設立日当日に登記申請が間に合わなかったり、登記完了までに数日かかった場合、事業展開・契約締結・助成金申請時に支障が生じることがあります。
事業の開始タイミングや会計年度に合わせ、登記申請のスケジュールと余裕を持った設立日設定を心がけるべきです。
まとめ:セルフ設立時の自己管理の徹底
自分で合同会社を設立する場合は、書類内容・提出フロー・期限・必要書類の種類などを、自ら管理・確認しながら一つずつ進めていく慎重さが不可欠です。
設立時のミスは、後から訂正するほど手間や費用が増大します。
「わからないことは法務局や専門家に相談する」「複数回チェックする」など、万全の準備で臨みましょう。
設立後に必要な届出や業務の流れ

税務署・都道府県・市区町村への届出
合同会社設立後は、税務署・都道府県税事務所・市区町村役場へ各種届出が必要です。
これらの手続きは会社として事業活動を行う上で義務であり、遅延や不備があるとペナルティとなる場合がありますので注意が必要です。
| 提出先 | 主な届出書類 | 提出期限 | 主な注意点 |
|---|---|---|---|
| 税務署 | 法人設立届出書 青色申告承認申請書 給与支払事務所等の開設届出書 | 設立から2ヶ月以内(青色申告は3ヶ月以内) | 提出期限厳守。 青色申告承認申請書は早めの提出推奨。 |
| 都道府県税事務所 | 法人設立・設置届出書 | 設立から15日〜2ヶ月以内(自治体により異なる) | 各都道府県でルールや書式が異なるため確認必須。 |
| 市区町村役場 | 法人設立届出書 | 設立から15日以内(自治体により異なる) | 会社所在地の自治体に要確認。 |
これらの提出の際には会社の履歴事項全部証明書や定款のコピーなどが必要となる場合があります。
前もって必要書類を整理しておきましょう。
社会保険・雇用保険の手続き
合同会社が従業員(アルバイト含む)を雇う場合や、代表社員自らが社会保険に加入する場合、社会保険(厚生年金・健康保険)および雇用保険の加入手続きが必要です。
| 手続き | 提出先 | 主な書類 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 社会保険新規適用届 | 日本年金機構 (年金事務所) | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 被保険者資格取得届 | 従業員1名でも加入義務。 5日以内の提出が原則。 |
| 雇用保険適用事業所設置届 | ハローワーク | 雇用保険適用事業所設置届 被保険者資格取得届 | 従業員を新たに雇用する場合。 10日以内に提出。 |
社会保険は原則として会社設立と同時に手続きが必要であり、未加入のまま事業を開始すると行政指導や遡及徴収の対象となる可能性があるため必ず行いましょう。
銀行口座開設の流れ
合同会社設立後、法人名義の銀行口座の開設を行うことで、会社としての資金管理や取引先との信用が高まります。
一般的な流れは以下の通りです。
- 銀行を選定し、事前にWebや電話で必要書類や手順を確認する
- 必要書類を準備する(代表的な書類を下記表にまとめます)
- 銀行に来店し、口座開設手続きを行う
※金融機関によっては事前予約や審査が必要な場合があります - 審査を経て、口座開設が完了しキャッシュカード等が交付される
| 必要書類 | 注意点 |
|---|---|
| 会社の履歴事項全部証明書(登記簿謄本) | 最新のもの(発行後3か月以内)が必要 |
| 会社の定款 | 原本またはコピー |
| 代表社員の本人確認書類(運転免許証等) | 会社登記簿と一致している必要がある |
| 会社の印鑑証明書 | 金融機関によっては2通必要な場合あり |
| 法人の実印 | 口座開設書類へ捺印するため必要 |
| 設立後の事業内容が分かる資料(ホームページや事業計画書など) | 審査時に求められることがある |
口座開設は不正利用防止のため厳格化が進んでおり、審査に時間がかかる場合や、希望通りに開設できないこともあるため、事業目的や会社の所在などを明確に説明できるよう準備しておきましょう。
なお、主要メガバンク(みずほ銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行)や地方銀行、ゆうちょ銀行など、複数の銀行から用途や利便性を比較して選ぶことが重要です。
また、ネットバンク(楽天銀行、住信SBIネット銀行等)は手続きが簡便ですが、条件やサービス内容も事前によく確認しておきましょう。
自分で行う場合と専門家(行政書士・司法書士)に依頼する場合の比較

費用面・手間・安全性の比較
合同会社を設立する際、自分で行う方法と専門家(行政書士・司法書士など)に依頼する方法のそれぞれには、費用や手間、手続きの安全性といった観点から大きな違いがあります。
下記の表で主要なポイントを比較します。
| 比較項目 | 自分で設立 | 専門家に依頼 |
|---|---|---|
| 費用 | 登録免許税などの法定費用のみ(約6万円)。 専門家報酬なし。コストを抑えられるが、書類作成や調査にかかる時間的コストが発生。 | 法定費用+専門家報酬(平均5万〜10万円前後)が必要。 総額では自分で行うより高くなるが、書類に不備があった場合の対応や追加提出のリスク軽減。 |
| 手間・作業量 | 定款作成・書類作成・法務局への提出などすべて自力で対応。 必要な知識・情報収集が求められ、場合によっては何度も役所へ足を運ぶ必要がある。 | 多くの作業を専門家に任せられるため手間が大幅に軽減。 定款や登記書類の作成も指示通り進めばよく、進行管理・申請業務も一元的にやってもらえる。 |
| 正確性・安全性 | 自分で情報収集や確認が必要。 記入ミスや添付漏れなどで補正命令や設立日の遅延が起こるリスクが高い。 | 豊富な実績・専門知識に基づきリスクを回避。 書類不備や法的要件の見落としを防ぎ、スムーズな設立につながる。 |
| スピード | 慣れない場合は、準備や確認で想定以上に時間がかかることも。 訂正や再申請が必要な場合は期間がさらに伸びる。 | 短期間で正確に設立できるケースが多い。 スケジュール管理や対応も万全。 |
どんな場合に専門家依頼が適しているか
自分で合同会社設立を行う場合、コストを抑えられる反面、情報収集・書類作成・役所対応といった手間とリスクがついて回ります。
そのため、設立が初めてで知識が十分でない方や、何度も法務局に通う時間が取れない方には専門家への依頼が有効です。
また下記のようなケースでは、特に行政書士や司法書士などの専門家に頼るメリットが大きくなります。
- 設立手続きを短期間で確実に完了させたい場合業務開始日が決まっている、契約や融資など「設立日」の厳守が求められる場合は、プロによるサポートでスピード・正確性が高まります。
- 複数人での設立や、出資・人事に複雑な条件がある場合合同会社の設立時、社員(出資者)や業務執行社員が複数いる場合や、特殊な取り決めが必要な場合は、専門家が双方の利益を調整しながら法的に正しい書類を準備します。
- 時間やリソースに余裕がない経営者・創業者の場合本業に集中したい場合や、設立手続きに煩わしさを感じたくない場合は、ワンストップサービスを利用することで設立作業を丸ごとアウトソース可能です。
- 書類作成や登記手続きに自信がない場合自分で調べた内容に不安がある場合は、専門家が書類の作成・不備防止・法的アドバイスまでトータルで支援します。小さなミスが大きなトラブルにつながるリスクを最小限に抑えられます。
- 数年後の運営や変更に備え、長期的に相談できる専門家が欲しい場合設立後の変更登記や運営サポートも含めて、継続的な相談先を設けておきたい場合は依頼する価値が高いです。
自分で設立手続きを進める場合、基礎知識や注意点をしっかり押さえることが重要です。
一方、設立のプロセスや登記書類の正確性・手続きの効率性を重視する場合や、設立後の各種手続きまで見越して安心と確実性を求める方にとっては、専門家への依頼がおすすめです。
ご自身の状況・設立の重要性・費用対効果をよく比較して、最適な方法を選択しましょう。
まとめ
合同会社は設立費用が低く、柔軟な経営ができるため、個人での設立にも適しています。
手順や書類を正しく理解し、自分で手続きすることでコストを抑えられますが、不安があれば司法書士や行政書士への依頼も検討しましょう。
失敗を防ぐためにも、事前準備と各手続きの確認をしっかり行うことが成功のポイントです。