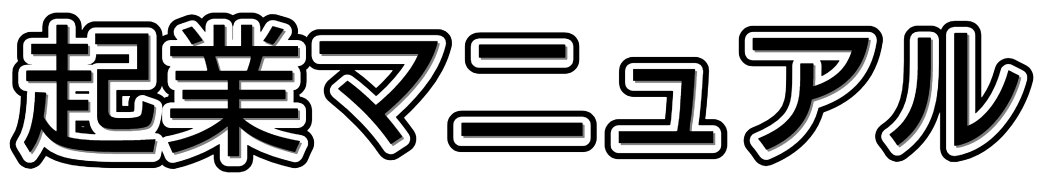個人事業主から合同会社への移行を検討中の方必見!
この記事では、合同会社の特徴や個人事業主との違い、移行によるメリット・デメリット、設立手順から必要書類・費用、注意点・よくある質問まで網羅的に解説します。
移行する理由や法人化の最適なタイミングなど、実務に役立つ具体的な情報が分かります。
個人事業主から合同会社に移行する理由とは
近年、個人事業主としてビジネスを運営している方が、合同会社へと法人化するケースが増えています。
その背景には、税務面や信用力の向上、事業成長への対応など、さまざまな理由があります。
本章では、個人事業主から合同会社への移行を考える際に知っておくべき基本事項や両者の違い、移行に適したタイミングについて詳しく解説します。
合同会社とは何か
合同会社(LLC:Limited Liability Company)は、2006年に施行された会社法によって創設された新しい会社形態です。
出資者自身が経営に参加できる点や、設立費用が比較的安価である点が特徴です。
| 会社形態 | 特徴 | 該当法令 |
|---|---|---|
| 合同会社 | 出資者が経営に直接参加・内部自治が柔軟・有限責任 | 会社法第576条以下 |
| 株式会社 | 株主と経営者が分離・意思決定が多数決・有限責任 | 会社法第2条以下 |
合同会社は「有限責任」であるため、万が一事業が失敗した場合でも、出資額を超える借金の責任を負うことはありません。
また、株式会社に比べて設立手続きやランニングコストが低く抑えられる点も魅力です。
個人事業主と合同会社の基本的な違い
| 項目 | 個人事業主 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 法的地位 | 自然人(個人) | 法人格を持つ |
| 責任範囲 | 無限責任(全財産で責任) | 有限責任(出資額まで) |
| 税制 | 所得税 | 法人税 |
| 社会的信用 | 比較的低い | 高い(法人名義で契約可能) |
| 設立・運営コスト | 低い | やや高いが株式会社より安価 |
合同会社へ移行することで、対外的な信用や融資の受けやすさ、節税の選択肢といったメリットが生まれます。
ただし、社会保険の加入義務や法人税の申告など、新たな責任や手続きが発生することも理解しておく必要があります。
移行する主なケースとタイミング
個人事業主から合同会社へ移行するべき代表的なタイミングとして、次のようなケースが挙げられます。
- 売上高や利益が一定以上になり所得税率が高くなってきた場合 :法人化することで法人税の節税メリットが享受できます。
- 取引先から法人格を求められる、または大手企業との取引を拡大したい場合 :社会的信用力の向上を図れます。
- 事業の規模拡大や従業員の雇用を本格的に検討する場合 :法人名義での雇用や社会保険への対応に合理性が生まれます。
- 事業承継や経営リスクを限定したい場合 :会社名義での資産管理や有限責任の活用が可能です。
上記の条件に該当する場合は、合同会社への移行を積極的に検討することが、長期的な事業発展にとって有効です。
個人事業主から合同会社になるメリット

節税効果や経費計上の幅について
合同会社になることで、個人事業主よりも法律上認められる経費範囲が広がり、さらに税制面でも大きなメリットが生まれます。
具体的には、役員報酬や退職金の計上が可能になるほか、法人の場合は経費にできる範囲が拡大し、自動車や通信費、交際費などプライベート利用と事業利用の切り分けもしやすくなります。
法人税と所得税の違いによって、利益が一定以上になると節税効果が大きくなる場合も多いです。
| 項目 | 個人事業主 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 税率 | 累進課税(最大45%) | 法人税(約23.2%) |
| 経費計上範囲 | 限定的 | 広い |
| 役員報酬 | 不可 | 可(経費算入可能) |
| 退職金 | 不可 | 可 |
利益が増えた場合には、合同会社に移行することで実質的な手取り額が増加するケースが多くなります。
社会的信用の向上
合同会社は法人格であるため、取引先や金融機関、自治体からの信頼性が高まります。
法人名義で契約ができるほか、法人名義で銀行口座を開設でき、融資や補助金の申請などもスムーズになります。
特にBtoB(法人間取引)が多い業種では、個人事業主より合同会社の方が契約や見積もり、請求書の信頼性が格段に上がります。
事業拡大や人材採用における有利点
合同会社は複数名での経営や従業員の採用がしやすく、将来的な事業拡大に適した組織形態です。
人材募集の際にも「法人である」ことが大きな安心材料となるため、有能な人材を採用しやすくなります。
また、出資者を増やす場合も柔軟に対応でき、社員(出資者)の追加や招集もしやすい構造になっています。
有限責任によるリスク軽減
合同会社のメリットとして特に重要なのが、出資者(社員)は出資額までしか責任を負わない「有限責任」である点です。
個人事業主の場合、万一事業で大きな負債を抱えた場合には私財まで責任を負いますが、合同会社なら原則として会社の債務は会社の資産で対応し、出資者個人の資産まで及ぶことはありません。
これは万が一のリスクへの備えとしても非常に心強い制度です。
個人事業主から合同会社になるデメリット

設立や運営コスト・手続きの増加
合同会社を設立する場合、設立にかかる費用や事務手続きが増加します。
例えば、法務局への設立登記申請時には登録免許税や専門家へ依頼する場合の報酬が発生します。
さらに、設立後も毎年の決算書作成や事業報告書の作成など、手続きが個人事業主よりも複雑になります。
法人名義での契約や許認可取得にも追加手続きが必要となる場合があり、これまでと比べ事務作業の負担も増加します。
| 内容 | 個人事業主 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 開業・設立費用 | ほぼ無料(自治体へ開業届のみ) | 約6万円前後(法定費用)+専門家報酬 |
| 書類作成・手続き | 開業届等のみ | 定款作成、登記申請、会社印鑑作成など多数 |
社会保険加入義務とその影響
合同会社を設立すると、原則として法人の代表者や従業員は社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務付けられます。
個人事業主の場合は従業員が5人未満であれば社会保険の加入義務がないケースもありますが、合同会社として法人化することで強制加入となります。
その結果、保険料負担が増加することがあり、特に少人数の事業の場合、手取り収入が減ることや経営上の資金繰りに影響を与えることも考えられます。
| 項目 | 個人事業主 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 社会保険加入 | 原則任意 | 代表・従業員ともに原則強制加入 |
| 保険料負担 | 国民健康保険・国民年金(個人が負担) | 法人・従業員が折半で負担 |
事務手続きや決算報告等の事務負担
合同会社を運営する場合、決算申告や法定調書・労働保険申告など定期的な事務手続きが増えます。
個人事業主では確定申告のみで済みますが、合同会社では年次の決算が必須であり、複式簿記による記帳や会計書類の整備が求められます。
また、税理士など専門家への依頼が必要なケースも増加し、これらによるコストや時間的負担も無視できません。
帳簿管理や税務申告が複雑化するため、経営者自身が事務作業に追われることも考慮する必要があります。
個人事業主から合同会社への移行手順

事業計画と会社設立の準備
個人事業主から合同会社へ移行する際は、まず事業内容や今後のビジョンに基づいた事業計画の見直しが重要です。
売上や利益の見通し、資金繰り、人材計画などを再検討し、合同会社としての成長戦略を練りましょう。
これにより法人化による変化や課題を明確にすることができます。
また、法人名(商号)や会社の所在地、事業目的、資本金、出資者・役員構成などを事前に決める必要があります。
合同会社設立の具体的な流れ
定款作成と認証
合同会社設立にあたり、まず「定款(会社のルール)」を作成します。
個人事業主と異なり、会社の基本事項(商号、事業目的、事業所所在地、社員=出資者の氏名・住所など)を記載します。
合同会社の場合、公証役場での定款認証は不要ですが、正確に作成する必要があります。
資本金の払い込み
定款の作成後、出資金額を決定し、指定口座へ資本金を払い込みます。
自分一人で設立する場合は、個人口座での資本金の入金が認められています。
払込証明書などの書類を作成し、後日の登記申請に備えます。
設立登記申請手続き
資本金の払い込みが完了したら、本店所在地を管轄する法務局で合同会社の設立登記を行います。
登記申請書、定款、払込証明書、代表社員の印鑑証明書、印鑑届出書などが必要です。
登記が完了すると、正式に法人としての活動が可能となります。
必要書類と費用の目安
設立にはさまざまな書類と費用が発生します。
下の表は合同会社設立時に必要となる主な書類と費用の目安です。
| 必要書類 | 概要 |
|---|---|
| 定款 | 会社の基本規則を記載。認証は不要だが、誤った内容は無効となるため作成に注意。 |
| 設立登記申請書 | 法務局に提出する主たる申請書。 |
| 代表社員の就任承諾書 | 代表社員となる方全員の署名・押印が必要。 |
| 印鑑届出書 | 会社代表印を法務局に提出。 |
| 払込証明書 | 資本金の払い込みがあったことを証明。 |
| 本人確認書類 | 代表社員・出資者の身分証明書の写し等。 |
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 設立登記申請時の登録免許税 | 60,000円(最低額) |
| 会社代表印作成費用 | 3,000~20,000円程度 |
| 定款印紙代 | 合同会社は不要(株式会社は4万円要) |
| 専門家報酬(任意) | 司法書士や行政書士へ依頼する場合は5万~10万円程度 |
合同会社は株式会社より低コストかつ手続きも簡便ですが、念のため書面提出や内容確認は専門家へ相談するのも安心です。
税務署など官公庁への各種届出
設立登記が完了したら、必要な各種届出を官公庁へ行うことを忘れないようにしましょう。
合同会社設立後は、2週間以内に税務署へ「法人設立届出書」、「青色申告の承認申請書」などを提出します。
また、都道府県税事務所や市区町村役場へも「法人設立・設置届」などを提出しましょう。
この他、従業員を雇う場合は、労働基準監督署や公共職業安定所(ハローワーク)へ「労働保険適用事業所設置届」「雇用保険適用事業所設置届」も必要となります。
社会保険に加入する場合は、年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険新規適用届」などが必要です。
各手続きにはそれぞれ期限や必要書類があり、提出し忘れるとペナルティが発生することもあるため、予めチェックリストを作成し、計画的に届け出ることが重要です。
<あわせて読みたい>
個人事業主から合同会社移行の際の注意点
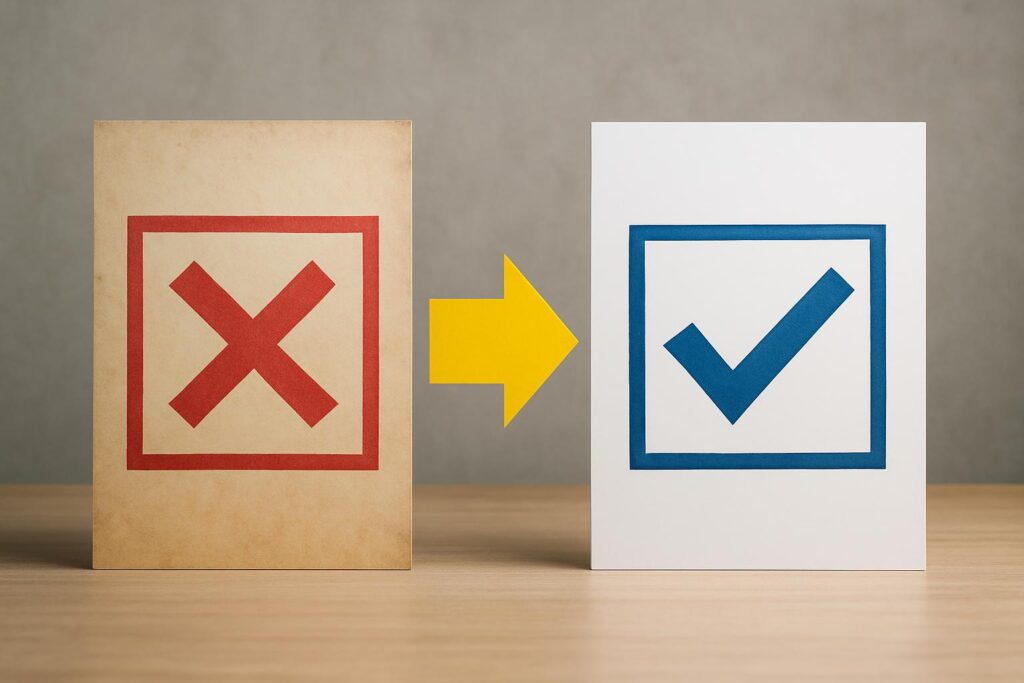
開業・廃業や青色申告の手続き
個人事業主が合同会社へ移行するためには、「個人事業の廃業」と「合同会社の開業」の届け出を税務署等の官公庁へ正確に提出する必要があります。
個人事業主としての青色申告承認申請書や青色事業専従者給与に関する届出は、原則として廃業時点で効力を失うため、法人化後は改めて「青色申告の承認申請書」や「給与支払事務所等の開設届出書」などを提出しましょう。
失念しやすいポイントとして、個人時代の会計期末日と合同会社設立日がずれる場合の確定申告・決算処理があります。
二重税課や必要経費の取り扱いなどにも注意が必要です。
名義変更や銀行口座の切り替え
合同会社設立後は、これまで個人名義で管理していた各種契約や資産、銀行口座を法人名義へ変更する作業が発生します。
主な対象には、取引先との契約書、レンタル・リース品の契約、オフィスや店舗の賃貸契約、電話回線やインターネット回線、ドメイン・サーバー契約、各種クレジットカード、電子マネー、請求書・領収書の発行名義などがあります。
特に銀行口座は、法人設立後に新規に開設する必要があります。
また、引き落とし先や振込先の変更を行う際には証明書類や法人印の提出が求められるケースも多いため、事前に必要書類や手続きの流れを確認しておきましょう。
| 変更が必要な主な名義・契約 | 具体的な注意点 |
|---|---|
| 銀行口座 | 新規に法人口座を開設。残高移動や自動引落、入金先変更手続きが必要 |
| 各種契約書(賃貸・リース等) | 契約先によっては再契約や追加審査書類の提出が必要 |
| 通信・インフラ契約 | 法人口座からの引き落とし対応可否を確認 |
| ドメイン/サーバー契約 | 名義変更不可の場合は新規契約が発生することがある |
許認可事業の対応方法
飲食業や建設業、運送業、古物商など、特定の許認可が必要な業種の場合、法人化によって許認可の名義変更または新規取得手続きが必要となる点に留意しましょう。
個人名義で受けている許可・認可・届出は、原則そのまま法人名義へ簡単に引き継げないケースが多く、各省庁や自治体ごとに求められる提出書類や審査基準も異なります。
| 主な許認可 | 合同会社化時の対応 | 重要なポイント |
|---|---|---|
| 飲食店営業許可 | 保健所へ法人名義で再申請 | 営業者・所在地・責任者変更の届出も同時に必要 |
| 建設業許可 | 都道府県または国土交通省へ法人名義で変更申請 | 経営管理責任者・専任技術者要件の法人適合チェック |
| 古物商許可 | 警察署へ法人名義で新規申請 | 代表社員・役員全員の身分証明書・登記簿謄本の提出 |
| 運送業許可 | 運輸局等へ法人移行届出または新規申請 | 運行管理体制や財務基準の再審査 |
場合によっては一時的に営業停止や追加審査が発生する場合や、申請完了まで時間がかかるケースもあるため、事前に各許認可の窓口に確認し、法人設立と並行して準備・申請ができるようスケジュールを組むことが重要です。
個人事業主から合同会社へのよくある質問

どのタイミングで法人化すべきか
個人事業主から合同会社への法人化を検討するタイミングは、売上や利益の増加が見込まれるときや、事業を拡大するタイミングが一般的です。
具体的には毎年の所得が500万円〜700万円を超える場合、節税効果や社会的信用を得るために法人化が有利になることが多いです。
また、従業員を雇用する予定がある場合や、取引先から法人格を求められた場合も、合同会社設立を検討する良いタイミングです。事業規模や今後の展望に応じて判断しましょう。
合同会社から株式会社へ変更できるか
合同会社から株式会社へは「組織変更」という手続きを行うことで転換が可能です。
組織変更は、法務局での申請や変更登記が必要となり、通常の設立登記よりも複雑な手続きが求められます。
ただし、既存の取引や事業をそのまま維持しながら会社形態だけを変更できるメリットがあります。
資本金や役員構成、目的など多数の確認事項があるため、詳しくは行政書士や司法書士など専門家への相談が推奨されます。
設立後の会計・税務のポイント
合同会社設立後は、会計・税務で以下のポイントに注意が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決算期の設定 | 合同会社は自由に決算期を設定できるため、事業の繁忙期や税負担の分散を考慮して決めることが重要です。 |
| 法人税申告 | 設立後は毎期ごとに法人税や消費税の申告義務が発生します。申告期限を過ぎると延滞税や加算税の対象となるため注意が必要です。 |
| 会計帳簿の整備 | 会社として経理規程に基づいた帳簿作成と保存義務があります。個人時代よりも経理作業が煩雑になるため、会計ソフトの導入や税理士への依頼も検討しましょう。 |
| 消費税課税事業者の判定 | 前々年の売上が1,000万円を超えると消費税課税事業者となります。設立初年度は原則免税ですが、途中で資本金1,000万円以上にすると課税事業者となるので注意しましょう。 |
| 社会保険の加入 | 法人は事業規模にかかわらず、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入義務があります。 |
会社としての決算書作成や各種届出、税務署・都道府県税事務所・市区町村役場への届出も発生しますので、専門家のサポートを積極的に活用しましょう。
まとめ
個人事業主から合同会社への移行は、節税効果や社会的信用の向上、リスク軽減など多くのメリットがある一方、手続きやコスト増加といったデメリットも伴います。
移行のタイミングや手順、注意点を確認し、事業拡大や将来の発展を見据えた判断が重要です。