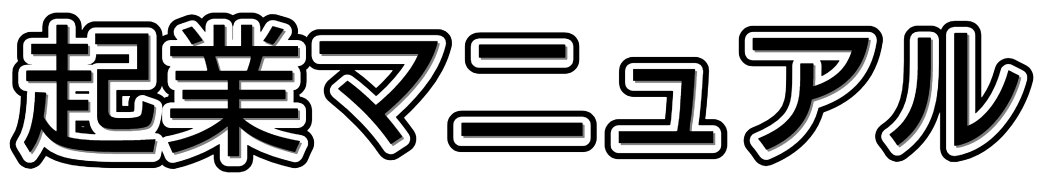法務局での株式会社設立は、手順とポイントさえ押さえれば、初心者でも自分自身で行うことが可能です。
この記事では、会社の設立準備から法務局への登記申請、そして設立完了後に必要な手続きまで、一連の流れを網羅的に解説します。
「何から始めればいい?」「必要な書類は?」「費用はいくらかかる?」といった設立時のあらゆる疑問を解消し、あなたがスムーズに手続きを終えられるよう、具体的な手順を分かりやすく紹介します。
この記事を最後まで読めば、設立手続きの全体像を掴み、自信を持って法務局へ向かうことができるでしょう。
法務局へ行く前に知っておきたい株式会社設立の基礎知識
株式会社の設立と聞くと、法務局へ行って何か難しい手続きをする、というイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
確かに、最終的な登記申請は法務局で行いますが、そこに至るまでには様々な準備が必要です。
この章では、まず株式会社設立の全体像を把握し、法務局がどのような役割を担っているのかを理解することから始めましょう。
ご自身で手続きを進めるか、専門家に依頼するかの判断材料にもなるはずです。
株式会社設立の流れと法務局の役割
株式会社の設立は、大きく分けて「準備段階」と「申請段階」に分かれます。
法務局が登場するのは、すべての準備が整った後の最終ステップである「申請段階」です。
まずは、会社設立が完了するまでの全体像を掴みましょう。
一般的な株式会社設立の流れは以下の通りです。
- STEP1:会社の基本事項の決定
会社の名前(商号)、事業目的、本店所在地、資本金額、役員構成などを決めます。 - STEP2:定款の作成と認証
会社のルールブックである「定款」を作成し、公証役場で認証を受けます。 - STEP3:資本金の払込み
発起人(会社を設立する人)の個人口座に、定められた資本金を払い込みます。 - STEP4:登記申請書類の作成
法務局へ提出するための登記申請書や添付書類一式を作成します。 - STEP5:法務局への登記申請
準備した書類一式を管轄の法務局に提出します。この申請日が会社の設立日となります。 - STEP6:登記完了と各種手続き
登記が完了したら、登記事項証明書や印鑑証明書を取得し、税務署や年金事務所などへの届出を行います。
この流れの中で、法務局の主な役割は「STEP5:登記申請」の受付と審査です。
法務局は、提出された書類が法律(主に会社法や商業登記法)に則って正しく作成されているかを確認し、問題がなければ会社の情報を「登記簿」に記録します。
この登記によって、会社は法人として法的に認められ、社会的な信用を得て取引を行えるようになるのです。
つまり、法務局は「会社の戸籍」を管理する役所と考えると分かりやすいでしょう。
ただし、法務局はあくまで申請書類を審査する機関であり、設立手続きの進め方を手取り足取り教えてくれる相談窓口ではない点に注意が必要です。
自分で設立手続きを行うメリットとデメリット
株式会社の設立手続きは、司法書士などの専門家に依頼せず、自分自身で行うことも可能です。
しかし、それにはメリットとデメリットの両方が存在します。
どちらがご自身の状況に適しているか、以下の比較表を参考にじっくり検討してみてください。
| 項目 | 自分で手続きを行う場合 | 専門家(司法書士など)に依頼する場合 |
|---|---|---|
| 費用 | 設立費用を大幅に抑えられる点が最大のメリットです。 専門家への報酬(数万円~10万円程度)がかかりません。 ただし、定款認証手数料や登録免許税などの法定費用は必要です。 | 法定費用に加えて、専門家への報酬が発生します。 ただし、専門家が電子定款を作成する場合、通常必要な収入印紙代4万円が不要になるため、結果的に自分で紙の定款を作成するより安くなるケースもあります。 |
| 時間と手間 | 書類の作成方法を調べたり、公証役場や法務局へ何度も足を運んだりする必要があり、膨大な時間と手間がかかります。 特に、書類に不備(補正)があると、さらに時間がかかり、事業開始の準備に支障が出る可能性があります。 | 面倒な書類作成や法務局とのやり取りをすべて代行してもらえます。 これにより、ご自身は事業の準備に集中できるという大きなメリットがあります。 |
| 知識・正確性 | 会社法や商業登記の知識を自ら学ぶ必要があります。 手続きをやり遂げることで、会社経営に必要な知識が身につくという側面もあります。 | 法律の専門家が手続きを行うため、書類の不備がなく、迅速かつ確実に設立手続きが完了します。 設立後の各種手続きについてもアドバイスを受けられる場合があります。 |
| 精神的負担 | すべての手続きを自己責任で行う必要があり、「これで合っているだろうか」という不安が常につきまといます。 特に法務局での補正対応は精神的な負担が大きくなりがちです。 | 専門家に任せることで、手続きに関する不安やストレスから解放されます。 安心して本業の準備を進めることができます。 |
費用を最優先するなら自分で手続きを行う選択肢も有効ですが、時間や確実性を重視し、スムーズに事業をスタートさせたいのであれば、専門家への依頼を検討する価値は十分にあると言えるでしょう。
STEP1 株式会社設立の準備編 法務局へ行く前に済ませること

株式会社の設立と聞くと、すぐに法務局へ行くイメージがあるかもしれませんが、実はその前に済ませておくべき準備が数多くあります。
この準備段階を丁寧に行うことが、後の登記申請をスムーズに進めるための最大の鍵となります。
ここでは、法務局へ足を運ぶ前に必ず完了させておくべき4つの重要なステップを、一つひとつ具体的に解説していきます。
会社の基本情報を決定する
会社の設立は、まず「どのような会社にするか」という骨格を決めることから始まります。
ここで決める基本情報は、会社の顔となり、事業の方向性を定める重要な要素です。
後から変更することも可能ですが、その都度、法務局での変更登記手続きと費用が発生するため、設立時に慎重に検討しましょう。
会社の名前(商号)や事業目的を決めよう
会社の名前である「商号」と、何で収益を上げるかを示す「事業目的」は、会社のアイデンティティそのものです。
商号
商号には、必ず「株式会社」という文字を入れなければなりません。
社名の前につける「株式会社〇〇」を「前株(まえかぶ)」、後につける「〇〇株式会社」を「後株(あとかぶ)」と呼びます。
使用できる文字にはルールがあり、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字・小文字)、アラビア数字(0,1,2,3…)のほか、「&」「’」「,」「‐」「.」「・」といった一部の記号も使えます。
商号を決める際に最も注意すべきなのが「商号調査」です。
法律上、同じ本店所在地に同じ商号の会社は登記できません。
また、有名企業と紛らわしい商号を付けると、不正競争防止法などの法律に抵触する恐れもあります。
事前に法務局のオンライン登記情報検索サービスや国税庁の法人番号公表サイトなどを活用し、類似の商号がないか確認することが不可欠です。
事業目的
事業目的は、その会社がどのような事業を行うのかを具体的に示すものです。
定款や登記事項証明書に記載され、誰でも閲覧できる情報となります。
事業目的は、「適法性」「営利性」「明確性」の3つの要件を満たす必要があります。
誰が見ても事業内容を理解できるよう、具体的かつ分かりやすい言葉で記載しましょう。
設立当初の事業だけでなく、将来的に行う可能性がある事業も記載しておくことをお勧めします。
後から事業目的を追加するには、株主総会の決議と法務局での変更登記(登録免許税3万円)が必要になるためです。
また、建設業や飲食業、古物商など、行政の許認可が必要な事業を行う場合は、許認可の要件を満たす文言を事業目的に含める必要がありますので、事前に管轄の行政庁に確認しておきましょう。
本店所在地と資本金額を決めよう
会社が事業を行う拠点となる「本店所在地」と、事業の元手となる「資本金」も、設立前に決めておくべき重要事項です。
本店所在地
本店所在地は、会社の「住所」にあたり、納税地を決定する基準にもなります。
自宅、賃貸オフィス、バーチャルオフィスなど様々な選択肢がありますが、特に賃貸物件を本店にする場合は注意が必要です。
賃貸借契約書で事業利用や法人登記が禁止されていないか、必ず事前に確認してください。
無断で登記すると、契約違反で退去を求められるリスクがあります。
資本金
現在の会社法では、資本金1円から株式会社を設立できます。
しかし、資本金は会社の体力や社会的信用度を示す指標の一つです。
取引先や金融機関は、登記事項証明書で資本金額を確認します。
あまりに少額だと信用を得にくい可能性があるため、初期費用に加えて、少なくとも3ヶ月から半年程度の運転資金を目安に設定するのが一般的です。
なお、資本金を1,000万円未満に設定すると、原則として設立から2事業年度は消費税の納税が免除されるというメリットもあります。
会社の実印を準備する
法務局への登記申請には、会社の実印(代表者印)が必須です。
個人の実印とは別に、会社用の印鑑を作成する必要があります。
商号が決定したら、すぐに印鑑の作成を依頼しましょう。
一般的に、会社設立時には以下の3種類の印鑑をセットで作成することが多いです。
| 印鑑の種類 | 主な用途 | 一般的なサイズ | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 実印(代表者印) | 法務局への登記申請、重要な契約書 | 18.0mm(丸印) | 法務局に印鑑登録する、会社にとって最も重要な印鑑。 二重円の外側に会社名、内側に「代表取締役印」などと彫刻されることが多い。 |
| 銀行印 | 法人口座の開設、手形・小切手の発行 | 16.5mm(丸印) | 実印と区別するため、一回り小さいサイズで作るのが一般的。 財務に関する重要な印鑑。 |
| 角印(社印) | 請求書や領収書、見積書などの日常的な書類 | 21.0mm~24.0mm(角印) | 認印として最も使用頻度が高い印鑑。 「〇〇株式会社之印」と彫刻される。 |
これらの印鑑は、注文から完成までに時間がかかる場合があります。
登記申請のスケジュールに影響が出ないよう、会社の基本情報が固まった段階で、早めに準備を進めることが重要です。
会社の憲法「定款」を作成し認証を受ける
会社の基本情報が決まったら、次はその会社のルールブックである「定款(ていかん)」を作成します。
定款は「会社の憲法」とも呼ばれ、商号、事業目的、本店所在地といった基本事項のほか、株式や役員に関するルールなどを定めた、会社運営の根幹となる非常に重要な書類です。
定款には必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」(商号、事業目的、本店所在地など)があり、一つでも欠けていると定款自体が無効となります。
法務局のウェブサイトにある雛形などを参考に、漏れなく作成しましょう。
作成した定款は、公証役場で公証人による「認証」を受ける必要があります。
この認証手続きを経て、初めて定款が法的な効力を持つことになります。
認証を受ける際には、以下の2つの方法があります。
- 紙の定款:作成した定款を印刷し、製本して公証役場に持ち込む方法です。この場合、収入印紙代として4万円が必要になります。
- 電子定款:PDF形式で作成した定款に電子署名を付与し、オンラインで認証を受ける方法です。電子定款の場合、紙の定款で必要だった収入印紙代4万円が不要になるという大きなメリットがあります。ただし、電子署名のためのICカードリーダーライタや専用ソフトの準備が必要です。
設立費用を少しでも抑えたい場合は、電子定款での認証がおすすめです。
公証役場へは、発起人全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)や実印なども持参する必要がありますので、事前に必要なものを確認しておきましょう。
資本金を個人の銀行口座に払い込む
定款の認証が無事に完了したら、最後の大仕事が「資本金の払い込み」です。
これは、定款で定めた資本金が、発起人によって確かに支払われたことを証明するための手続きです。
手続きは、発起人の代表者個人の銀行口座(既存の口座で構いません)に、各発起人が出資額を振り込む形で行います。
この際、必ず定款の認証日「以降」の日付で振り込みを行う必要があります。
認証日より前に振り込まれたお金は、資本金として認められないため、日付には細心の注意を払ってください。
振り込みが完了したら、以下の手順で「払込証明書」を作成します。
- 通帳の表紙をコピーする
- 通帳の裏表紙(銀行名、支店名、口座番号、名義人が記載されているページ)をコピーする
- 資本金の振り込みが記帳されたページをコピーする
- 資本金の払い込みがあったことを証明する「払込証明書」という書類を作成する
- 「払込証明書」と上記1~3のコピーをまとめてホチキスで綴じ、各ページの綴じ目に会社の実印で契印(けいいん)する
この一式が、資本金が正しく払い込まれたことを証明する公的な書類となり、法務局への登記申請で必要になります。
STEP2 株式会社設立の申請編 法務局での手続き

入念な準備が完了したら、いよいよ株式会社設立の登記申請です。
このステップでは、作成・収集した書類を法務局へ提出します。
申請方法には窓口、郵送、オンラインの3つの選択肢があります。
ご自身の状況に合わせて最適な方法を選び、確実に手続きを進めましょう。
登記申請に必要な書類を揃える
法務局へ提出する書類は、会社の機関設計(取締役会を設置するかどうかなど)によって異なりますが、ここでは一般的な株式会社(取締役会を設置しない、発起人が1名でその人が代表取締役になるケース)を例に、必要な書類を一覧でご紹介します。
書類に不備があると、修正(補正)のために法務局へ出向く必要が生じるため、提出前に何度も確認しましょう。
| 書類名 | 概要と注意点 |
|---|---|
| 登記申請書 | 法務局のウェブサイトでテンプレートをダウンロードできます。 会社の基本情報や登記すべき事項を記載する、申請の核となる書類です。 |
| 登録免許税貼付台紙 | 登録免許税額分の収入印紙を貼り付けたA4の白紙です。 登記申請書とホチキスで綴じ、契印を押します。 収入印紙に割印は絶対にしないでください。 |
| 定款 | 公証役場で認証を受けた、会社の根本規則を定めた書類です。 紙の定款の場合は認証済みの謄本、電子定款の場合はデータを保存したCD-Rなどを提出します。 |
| 発起人の決定書 | 本店所在地、設立時取締役、資本金の額などを発起人が決定したことを証明する書類です。 発起人全員の実印を押印します。 |
| 設立時取締役の就任承諾書 | 取締役に就任することを承諾した旨を記載した書類です。個人の実印を押印します。 登記申請書に就任を承諾した旨を記載し、押印することで省略できる場合もあります。 |
| 印鑑証明書 | 就任承諾書に押印した実印が本人のものであることを証明する書類です。 発行後3ヶ月以内のものを用意する必要があります。 取締役全員分が必要です。 |
| 資本金の払込証明書 | 定款作成後に、発起人個人の銀行口座へ資本金が払い込まれたことを証明する書類です。 通帳のコピー(表紙、1ページ目、振込が記帳されたページ)と、会社代表者が作成した払込証明書をセットにして綴じ、契印します。 |
| 印鑑届書 | 設立する会社の実印(代表者印)を法務局に登録するための書類です。 あらかじめ提出しておくことで、登記完了後すぐに印鑑証明書を取得できます。 |
| 登記すべき事項を記録したCD-Rなど | 登記申請書に記載した「登記すべき事項」をテキストファイルで保存した媒体です。 オンライン申請の場合は不要です。 法務局のウェブサイトで指定のフォーマットを確認しましょう。 |
これらの書類は、一般的に左側をホチキスで2箇所留めし、各ページのつなぎ目に会社代表印(実印)で契印を押します。
管轄の法務局へ登記申請を行う
登記申請は、どの法務局でも行えるわけではありません。
設立する会社の本店所在地を管轄する法務局に提出する必要があります。
管轄は法務局のウェブサイトで確認できるため、事前に必ず調べておきましょう。
申請方法は主に3つあります。
法務局の窓口で直接申請する
最も確実で安心感のある方法が、管轄法務局の窓口へ直接書類を持参して申請する方法です。
法務局の開庁時間(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)に訪問する必要があります。
メリットは、その場で書類の形式的なチェックを受けられる可能性がある点です。
万が一、明らかな記載漏れや書類不足があれば指摘してもらえ、その場で修正できる場合もあります。
また、登記相談窓口が併設されている法務局も多く、不明点を質問できる安心感があります。
郵送やオンライン(gBizID)で申請する
法務局へ行く時間がない方や、遠方にお住まいの方には郵送やオンラインでの申請が便利です。
郵送申請の場合
作成した書類一式を封筒に入れ、管轄の法務局宛に郵送します。
この場合、法務局に書類が到着した日が申請日となります。
会社の設立日にこだわりがある場合は、到着日を計算して発送しましょう。
書類の不備があった際の連絡は電話で、修正は郵送か窓口で行うため、手続き完了までに時間がかかる可能性があります。
送付する際は、必ず「書留郵便」や「レターパックプラス」など、配達記録が残る方法を選びましょう。
オンライン申請の場合
法務省の「登記・供託オンライン申請システム」を利用して、インターネット経由で申請する方法です。
24時間いつでも申請可能で、法務局へ出向く必要がありません。
申請には、マイナンバーカードやICカードリーダライタ、そして「gBizID」プライムアカウントの事前取得が必要です。
PC操作に慣れている方には非常に便利な方法ですが、初めての方にとってはシステムの設定や操作が複雑に感じられるかもしれません。
登録免許税の納付方法
株式会社の設立登記には、登録免許税という税金を国に納める必要があります。
納付額は「資本金の額 × 0.7%」で計算されますが、この金額が15万円に満たない場合は、一律で15万円となります。
例えば、資本金が1,000万円の場合でも税額は7万円なので、最低額である15万円を納付します。
資本金が約2,143万円を超えるまでは、登録免許税は15万円です。
納付方法は申請方法によって異なります。
- 窓口・郵送申請の場合:
郵便局や法務局内の印紙売場で15万円分の「収入印紙」を購入し、A4の白紙などに貼り付けた「登録免許税貼付台紙」を登記申請書と一緒に提出します。前述の通り、収入印紙には割印をしないよう注意してください。 - オンライン申請の場合:
申請後に発行される納付情報をもとに、インターネットバンキングや金融機関のATMからPay-easy(ペイジー)を利用して電子納付します。現金や収入印紙を用意する必要がなく、スムーズに支払いが完了します。
STEP3 株式会社設立の完了編 法務局で受け取るもの

登記申請が無事に受理されると、株式会社の設立手続きは完了です。
しかし、これで終わりではありません。登記完了後に法務局で行うべき重要な手続きが2つあります。
今後の事業運営に不可欠な「登記事項証明書」と「印鑑証明書」を取得するために必要な手続きですので、忘れずに行いましょう。
登記完了後に登記事項証明書を取得する
登記申請時に窓口で伝えられた、またはオンラインで確認した「登記完了予定日」を過ぎたら、会社の「登記事項証明書」を取得できるようになります。
これは、会社が法的に存在することを証明する公式な書類であり、人間でいう戸籍謄本のようなものです。
登記事項証明書は、主に以下のような場面で提出を求められます。
- 銀行で法人口座を開設するとき
- 税務署や都道府県税事務所、市町村役場へ法人設立の届出をするとき
- 社会保険や労働保険の加入手続きをするとき
- 事務所の賃貸契約や融資(ローン)の申し込みをするとき
- 許認可が必要な事業の申請をするとき
一般的に使用されるのは、会社の現在の情報が記載された「履歴事項全部証明書」です。
今後の手続きをスムーズに進めるため、最低でも3通から5通ほどまとめて取得しておくことをおすすめします。
取得方法によって手数料が異なるため、ご自身の都合に合わせて選択してください。
| 取得方法 | 手数料(1通あたり) | 特徴 |
|---|---|---|
| 法務局の窓口で請求 | 600円 | 法務局に設置されている証明書発行請求機を利用するか、申請書を記入して窓口で請求します。 その場で受け取れる最も早い方法です。 |
| オンライン請求(郵送受取) | 500円 | 「登記・供託オンライン申請システム」を利用して請求します。 手数料が最も安く、指定した住所に郵送で届きます。 |
| オンライン請求(窓口受取) | 480円 | オンラインで請求手続きを行い、指定した法務局の窓口で受け取ります。 手数料を抑えつつ、早く受け取りたい場合に便利です。 |
会社の印鑑カードを作成する
登記事項証明書とあわせて、必ず「印鑑カード」の交付請求を行いましょう。
印鑑カードとは、法務局で会社の印鑑証明書を発行してもらう際に必要となる、キャッシュカードのようなカードのことです。
このカードがなければ、会社の印鑑証明書を取得することができません。
印鑑証明書は、不動産取引や融資契約、自動車の購入など、会社にとって重要な契約を結ぶ際に必要となります。
いざという時に困らないよう、登記が完了したらすぐに作成しておきましょう。
登記事項証明書を取得する際に、一緒に手続きを済ませてしまうのが最も効率的です。
交付手数料は無料です。
| 必要なもの | 印鑑カード交付申請書(法務局の窓口またはウェブサイトで入手)法務局に届け出た会社の実印(代表印) |
|---|---|
| 申請場所 | 会社の本店所在地を管轄する法務局の窓口 |
| 手数料 | 無料 |
申請書に必要事項を記入し、会社の実印を押印して窓口に提出します。
手続きは数分で完了し、その場で印鑑カードが交付されます。
印鑑カードを受け取ったら、そのまま会社の印鑑証明書も1〜2通取得しておくと、今後の手続きがよりスムーズになるでしょう。
法務局での株式会社設立でつまずかないためのポイント

株式会社の設立登記は、書類に少しでも不備があると受理されず、修正を求められます。
この修正手続きを「補正」と呼びますが、補正のために何度も法務局へ足を運ぶことになると、時間も労力も大幅にロスしてしまいます。
ここでは、そうした事態を避け、スムーズに登記を完了させるための重要なポイントを解説します。
書類の不備(補正)を防ぐためのチェックリスト
法務局へ申請書類を提出する前に、必ず最終チェックを行いましょう。
特に初心者が間違えやすいポイントをリストアップしました。
一つひとつ確認し、完璧な状態で申請に臨むことが、設立手続きを成功させる鍵となります。
| 分類 | チェック項目 | よくあるミスと注意点 |
|---|---|---|
| 書類全般 | 管轄の法務局は正しいか? | 申請先は、本店所在地を管轄する法務局です。 会社の住所(本店所在地)が決まったら、法務局のウェブサイトで管轄を確認しましょう。 異なる法務局に提出しても受理されません。 |
| 書類全般 | 書類は全てA4サイズで作成・統一されているか? | 印鑑証明書など、役所で発行される書類以外は、全てA4サイズで片面印刷が原則です。 サイズが混在していると補正対象になる可能性があります。 |
| 書類全般 | 捨印は押してあるか? | 書類の上部余白に、会社実印や個人の実印を「捨印」として押しておくと、軽微な誤字脱字であれば法務局の担当者が訂正してくれます。 補正のために法務局へ出向く手間を省ける可能性があるため、押しておくことを強く推奨します。 |
| 登記申請書 | 商号・本店所在地・事業目的は定款の記載と一字一句同じか? | 登記申請書と定款の記載内容は、完全に一致している必要があります。 「株式会社」と「㈱」、「丁目・番・号」と「-(ハイフン)」、「及び」と「および」など、表記の揺れがないかを徹底的に確認してください。 |
| 登記申請書 | 役員の氏名・住所は印鑑証明書の記載と完全に一致しているか? | 取締役などの役員の氏名や住所は、添付する印鑑証明書の記載通りに記入します。 特に旧字体(例:髙、﨑、邉)や、マンション名・部屋番号の有無など、細部まで完全に一致させる必要があります。 |
| 払込証明書 | 資本金の払込日が定款作成日以降になっているか? | 資本金の払込は、定款を作成した日以降に行う必要があります。 それ以前の日付で振り込まれたお金は資本金として認められず、再度振り込みが必要になるため注意してください。 |
| 収入印紙貼付台紙 | 登録免許税分の収入印紙に消印(割印)をしていないか? | 登録免許税として納める収入印紙には、絶対に消印(割印)をしてはいけません。 消印は法務局が行います。 自分で押してしまうと、再購入が必要になる場合があります。 |
設立日はいつになる?法務局に申請書を提出した日
会社の設立日は、創立記念日となる大切な日です。
この設立日がいつになるのか、正確に理解しておくことは重要です。
結論から言うと、会社の設立日は、登記が完了した日ではなく、法務局に登記申請書を提出し、受理された日となります。
申請方法によって、設立日の考え方が少し異なります。
- 窓口申請の場合
法務局の窓口で申請書類が受理されたその日が、会社の設立日になります。 - 郵送申請の場合
申請書類が法務局に到着し、受理された日が設立日となります。発送日ではないため、特定の日を設立日にしたい場合は、配達日数に余裕をもって発送する必要があります。 - オンライン申請(gBizID利用)の場合
申請データが登記・供託オンライン申請システムに到達し、受理された日時が基準となります。24時間申請可能ですが、設立日として記録されるのは法務局の開庁日です。
注意点として、法務局は土日祝日や年末年始は閉庁しているため、これらの日を設立日にすることはできません。
カレンダーを確認し、希望する設立日が開庁日であるかを事前にチェックしておきましょう。
「大安」など、縁起の良い日を設立日にしたい場合は、窓口に直接持参するのが最も確実な方法です。
株式会社設立後に待っている法務局以外の行政手続き

法務局での登記が完了し、会社が誕生したら、手続きは終わりではありません。
事業を開始するためには、法務局以外の様々な行政機関への届出が必要です。
これらの手続きを怠ると、税制上の優遇措置が受けられなくなったり、罰則の対象となったりする可能性があるため、速やかに行いましょう。
主な届出先と手続きは以下の通りです。
登記事項証明書や印鑑証明書が必要になる場面が多いため、登記完了後にまとめて取得しておくとスムーズです。
| 届出先 | 主な届出書類 | 提出期限の目安 |
|---|---|---|
| 税務署 | 法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書 など | 設立後2ヶ月以内 |
| 都道府県税事務所・市町村役場 | 法人設立届出書 | 設立後1ヶ月〜2ヶ月以内(自治体による) |
| 年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届、被保険者資格取得届 など | 設立後5日以内 |
| 労働基準監督署 | 労働保険関係成立届(従業員を1人でも雇用した場合) | 従業員を雇用した日の翌日から10日以内 |
| ハローワーク(公共職業安定所) | 雇用保険 適用事業所設置届、被保険者資格取得届(従業員を雇用した場合) | 従業員を雇用した日の翌日から10日以内 |
これらの手続きは、会社の状況(従業員の有無、資本金の額など)によって必要なものが異なります。
特に税務署への「青色申告の承認申請書」は、提出期限を過ぎると初年度の節税メリットを受けられなくなるため、最優先で対応しましょう。
どの手続きが必要か不明な場合は、税理士や社会保険労務士などの専門家に相談することも有効な手段です。
株式会社設立後に待っている法務局以外の行政手続き
法務局での登記申請が完了し、無事に株式会社が誕生しても、それで全ての手続きが終わったわけではありません。
むしろ、ここからが事業を運営していくための本格的なスタートです。
会社の設立後は、法務局以外のさまざまな行政機関へ届出を行う必要があります。
これらの手続きを怠ると、税制上の優遇措置が受けられなくなったり、罰則が科されたりする可能性があるため、必ず期限内に済ませましょう。
ここでは、主に必要となる手続きを提出先ごとに解説します。
税務署への届出
会社の税金に関する手続きは、本店所在地を管轄する税務署で行います。
特に「青色申告の承認申請書」は、節税メリットが大きいため、忘れずに提出しましょう。
| 届出書類 | 提出が必要な場合 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 法人設立届出書 | すべての会社が必須 | 会社設立の日(登記申請日)から2ヶ月以内 |
| 青色申告の承認申請書 | 青色申告の特典(欠損金の繰越控除など)を受けたい場合 | 設立の日から3ヶ月を経過した日と、最初の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 役員報酬や従業員への給与を支払う場合 | 給与支払事務所を設置した日から1ヶ月以内 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 給与の支給人員が常時10人未満で、源泉所得税の納付を年2回にまとめたい場合 | 特例を受けたい月の前月末日まで |
| 棚卸資産の評価方法の届出書 | 所得金額の計算上、法定評価方法(最終仕入原価法)以外の評価方法を選びたい場合 | 最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで |
| 減価償却資産の償却方法の届出書 | 法定償却方法(定率法 ※建物などを除く)以外の償却方法を選びたい場合 | 最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで |
都道府県税事務所・市町村役場への届出
税金の納付先は国(税務署)だけではありません。
事業を行う都道府県と市町村にも、法人住民税や法人事業税を納める必要があります。
そのため、それぞれの窓口へ会社の設立を届け出る必要があります。
提出する書類は「法人設立設置届出書」ですが、自治体によって様式や名称が異なる場合があります。
提出先は、本店所在地を管轄する都道府県税事務所と市町村役場の2ヶ所です。
東京都23区内に本店を置く場合は、都税事務所への届出のみで問題ありません。
提出期限や添付書類も自治体ごとに定められているため、必ず事前に公式サイトなどで確認しましょう。
年金事務所への届出(健康保険・厚生年金保険)
法人の場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入は法律で義務付けられています。
社長が1人しかいない会社であっても、役員報酬を受け取る場合は加入対象となりますので注意が必要です。
| 届出書類 | 提出が必要な場合 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | すべての会社が必須 | 会社設立(適用事業所となった)の事実があった日から5日以内 |
| 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 役員や従業員など、社会保険に加入する人がいる場合 | 会社設立(資格取得の事実があった)日から5日以内 |
| 健康保険 被扶養者(異動)届 | 社会保険に加入する役員や従業員に扶養家族がいる場合 | 扶養の事実が発生してから5日以内 |
労働基準監督署・ハローワークへの届出(労働保険)
労働保険とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」の総称です。パートやアルバイトを含め、従業員を1人でも雇用した場合には、労働保険の加入手続きが必要になります。
手続きは「労働基準監督署」と「ハローワーク(公共職業安定所)」の2ヶ所で行います。
労働基準監督署での手続き
従業員を雇用したら、まず労働基準監督署へ以下の書類を提出します。
- 労働保険関係成立届:提出期限は、従業員を雇用した日の翌日から10日以内です。
- 労働保険概算保険料申告書:提出期限は、保険関係が成立した日の翌日から50日以内です。
ハローワークでの手続き
労働基準監督署での手続きが終わったら、次にハローワークで雇用保険の手続きを行います。
- 雇用保険適用事業所設置届:提出期限は、事業所を設置した日(従業員を雇用した日)の翌日から10日以内です。
- 雇用保険被保険者資格取得届:提出期限は、従業員を雇用した月の翌月10日までです。
事業内容に応じた許認可の申請
行う事業によっては、国や地方公共団体から「許認可」を得る必要があります。
許認可が必要な事業を、許可や認可、届出なしに開始してしまうと、罰則が科されたり、営業停止処分を受けたりする可能性があります。
自社の事業が許認可の対象かどうかを必ず確認し、必要な場合は設立登記と並行して準備を進めましょう。
以下に許認可が必要な業種の例と、主な申請窓口を挙げます。
- 飲食店営業許可:保健所
- 建設業許可:都道府県知事または国土交通大臣
- 古物商許可:警察署(公安委員会)
- 宅地建物取引業免許:都道府県知事または国土交通大臣
- 一般貨物自動車運送事業許可:運輸局
- 有料職業紹介事業許可:厚生労働大臣(労働局)
これらの手続きは専門的な知識を要する場合が多いため、必要に応じて行政書士などの専門家に相談することも検討しましょう。
まとめ
本記事では、法務局における株式会社の設立手続きについて、準備段階から登記完了後の流れまでを網羅的に解説しました。
株式会社の設立は、会社の基本事項の決定、定款の作成・認証、資本金の払込みといった事前準備が成功の鍵を握ります。
これらの準備を丁寧に行うことが、法務局でのスムーズな登記申請に直結します。
法務局での手続き自体は、必要書類を正確に揃えて提出することが最大のポイントです。
書類に不備があると補正が必要となり、設立日が遅れる原因となります。設立日は法務局が申請書を受理した日となるため、希望の設立日がある場合は、計画的に準備を進めることが重要です。
申請方法は窓口持参のほか、郵送やgBizIDを利用したオンライン申請も選択できます。
ご自身で設立手続きを行うことは、司法書士などに依頼する費用を抑えられるという明確なメリットがあります。
また、一連のプロセスを経験することで、会社経営の基礎知識が身につき、今後の事業運営にも必ず役立つでしょう。
登記が完了しても、税務署や年金事務所への届出など、事業を開始するために必要な行政手続きが続きます。
会社設立はゴールではなく、新たな事業のスタートです。
この記事を参考に、一つひとつのステップを確実にこなし、あなたの会社の設立を成功させてください。