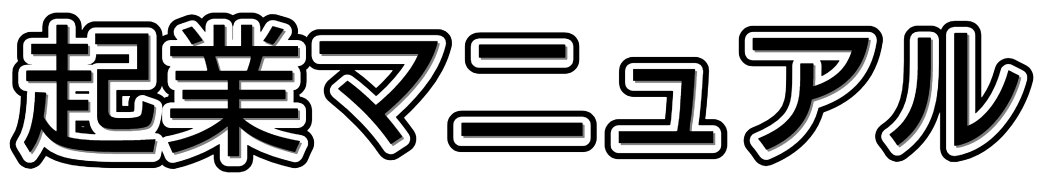合同会社における業務執行社員とは
業務執行社員の定義と役割
合同会社(LLC)における「業務執行社員」とは、会社の業務を実際に執行する権限と責任を持つ社員を指します。
合同会社は株式会社とは異なり、発起人(出資者)が「社員」となり、その中から実際に会社の経営や業務遂行を行う「業務執行社員」が選ばれます。
業務執行社員は、会社の日常的な経営判断や意思決定、契約の締結などを担う中心的な存在です。
そのため、合同会社の経営の実権を持つ重要な役割を果たします。
社員全員が業務執行社員となる場合もあれば、出資者の中から一部の社員のみが業務執行社員に選ばれるケースもあります。
定款で業務執行社員を定め、その権限や範囲を明らかにすることが一般的です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 業務執行社員の地位 | 出資者(社員)のうち、業務を執行する立場 |
| 主な権限 | 会社の業務執行・経営判断・契約締結 |
| 選任方法 | 定款により定めるか、社員の合意で決定 |
| 責任の範囲 | 会社に対して原則として無限責任(ただし出資額を限度とする有限責任社員も存在) |
株式会社の取締役との違い
合同会社の業務執行社員と株式会社の取締役は、経営に関わるという点で似ていますが、その仕組みや権限、責任には明確な違いがあります。
| 項目 | 合同会社の業務執行社員 | 株式会社の取締役 |
|---|---|---|
| 選任者 | 社員(出資者)の中から選任 | 株主総会で選任 |
| 責任 | 出資額を限度とする有限責任 | 原則として有限責任 |
| 経営意思決定の仕組み | 原則として社員全員の合意による。柔軟な運営が可能 | 取締役会または代表取締役による意思決定 |
| 定款での役割の規定 | 定款で細かく業務執行権限を決定可能 | 会社法に定める枠組みが主流 |
| 設置必須人数 | 1名でも可 | 1名でも可 |
合同会社における業務執行社員は、柔軟な意思決定が可能で出資者との距離も近く、会社経営へのダイレクトな関与が特徴です。
一方、株式会社の取締役は組織的なガバナンス体制の中で役割が分担されており、公共性や透明性を意識した運営になっています。
合同会社を設立・運営する際には、この違いを理解した上で、最適な形で業務執行社員を選任することが重要です。
業務執行社員になるための条件と資格
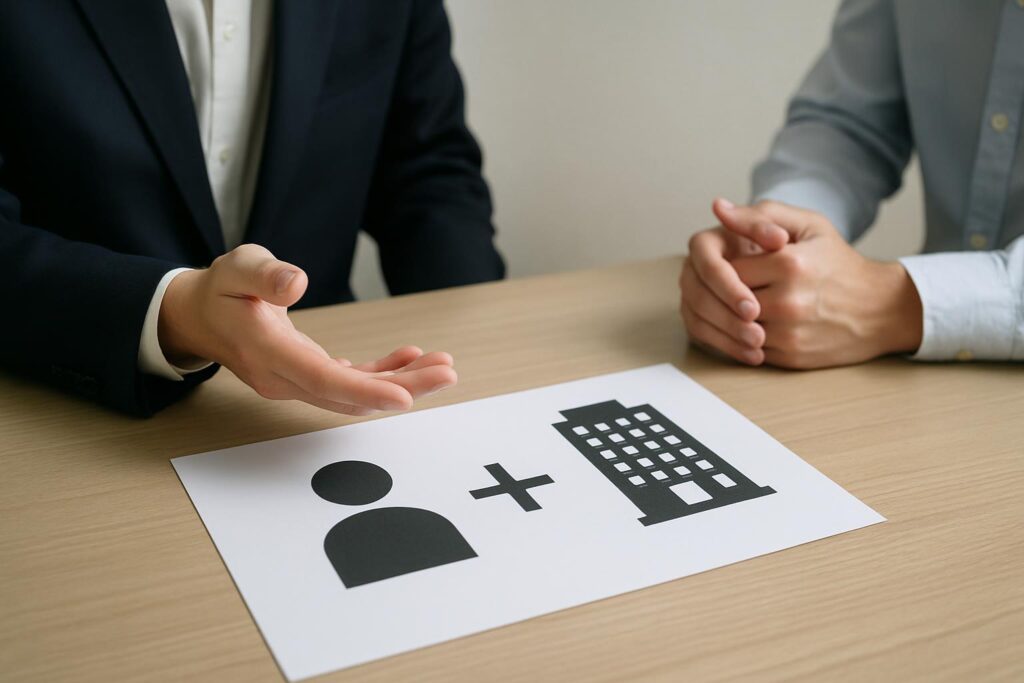
個人・法人が業務執行社員になれるか
合同会社(LLC)における業務執行社員には、原則として個人・法人のいずれもなることができます。
日本の会社法では法人・個人問わず社員(出資者)が業務執行社員になることが認められています。
例えば、他の会社や一般社団法人が業務執行社員となる事例も存在します。
ただし、定款で法人の業務執行社員就任を制限している場合は、その定款に従う必要があります。
| 区分 | 業務執行社員になれるか | 補足 |
|---|---|---|
| 個人 | 可能 | 日本国籍・外国籍どちらも可 |
| 法人 | 可能 | 法人も社員・業務執行社員となることができる |
業務執行社員は定款の定めや総社員の合意によって選任され、会社の実務を担当します。
必要な資格や制限事項
業務執行社員に就任するために必要な国家資格や特定の実務経験はありません。
ただし、以下のような法的な制限事項が存在します。
| 制限事項 | 内容 |
|---|---|
| 成年被後見人・被保佐人 | 成年後見人・保佐人の宣告を受けている人は就任できません。 |
| 会社法上の法定欠格事由 | 刑法等の規定により特定の犯罪で禁錮以上の刑を受け、その執行を終えた後から2年未満の者等、会社法で定められた欠格事由に該当する場合は、業務執行社員になれません。 |
| 法人が業務執行社員となる場合 | 代表権を持たせる場合、登記時に代表者の情報が必要です。 |
業務執行社員となるためには、法的な欠格事由がないこと、そして定款や総社員の同意により承認されることが必須です。
また、未成年者については親権者の同意があれば業務執行社員になることが可能ですが、会社の信用や実務を考えると成人以上が望ましいと言えます。
外国籍の人も就任可能ですが、特に在留資格や日本での居住要件は会社法上は求められていません。
ただし、代表社員として登記する場合には印鑑証明書などが必要になるため、実務面の確認が求められます。
まとめると、業務執行社員には個人・法人ともに原則として就任可能であり、特別な資格は不要ですが、会社法や定款で定める制限事項に該当しないことが条件となります。
業務執行社員になるメリット

経営への関与と裁量権
合同会社の業務執行社員になる最大のメリットは、会社の日々の経営方針や業務運営に深く関与できる点です。
業務執行社員は定款や社員同士の合意によって幅広い権限を持ち、経営戦略の決定や重要事項の決定に直接参加することができます。
株式会社の取締役よりも運営の柔軟性が高く、迅速な意思決定が可能です。
そのため、市場や事業環境の変化にスピーディーに対応できる体制を実現できます。
利益分配と報酬
合同会社では、出資比率や役割を自由に定めて利益分配や報酬額を決定できます。
株式会社のように出資比率に固定されることなく、業務執行社員間で柔軟な合意が可能です。
例えば経営面での貢献度を重視した配分も行えますので、社員それぞれが納得できる形で報酬を得られます。
更に税務面でも、報酬については「給与」ではなく「事業所得」や「分配金」として扱うことができ、税務上の最適な取扱いを追求しやすいのも利点です。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 利益分配 | 出資比率に応じて配当 | 出資比率以外でも自由に設定可 |
| 報酬 | 取締役への役員報酬 | 社員間の合意で柔軟に設定 |
会社運営における自由度
合同会社の業務執行社員は、定款や社員同士の契約内容によって運営ルールを柔軟に設計することができます。
株式会社では会社法の規制や定型的な手続きが多い一方で、合同会社は合意内容を重視し、意思決定方法や利益分配、退社時の対応なども比較的自由に決めることが可能です。
迅速な経営判断や新事業への参入のしやすさ、少人数での運営コストの抑制といった実利面においても、多くの中小企業やスタートアップに支持される理由のひとつとなっています。
業務執行社員として活動するデメリットやリスク

合同会社の業務執行社員は経営の中核を担う一方で、様々なデメリットやリスクも存在します。
以下で、具体的なリスクや注意点について項目ごとに解説します。
責任の範囲と法的リスク
業務執行社員は、会社の業務執行に関して直接的な法的責任を負う立場となります。
合同会社の社員には「有限責任」と「無限責任」の選択肢がありますが、一般的には有限責任社員が多いものの、登記時の設定や業務執行における重大な過失・違法行為があった場合には個人が法的責任を問われることもあります。
| リスク内容 | 具体例 | 発生する可能性 |
|---|---|---|
| 民事責任 | 会社名義での契約違反、不法行為による損害賠償請求 | 会社の業務遂行中に発生しやすい |
| 刑事責任 | 脱税や詐欺など法令違反に基づく責任 | 重大な法令違反があった場合 |
| 行政責任 | 許認可事業における義務違反、行政指導への対応 | 規制業種で特に注意 |
また、誤った経営判断やコンプライアンス違反により、会社全体が損失を被った場合、他の社員や出資者、取引先から法的責任を追及されるリスクがあります。
個人保証や対外的信用への影響
取引銀行やリース会社などとの契約時に、業務執行社員個人が連帯保証人を求められるケースが多いです。
特に設立間もない合同会社や小規模な合同会社の場合、会社自体の信用力が十分でないため、業務執行社員個人の資産や信用が重要視されます。
万一会社が債務不履行に陥った場合、保証人となっている業務執行社員が個人資産で責任を負うリスクが現実化します。
これにより、業務執行社員自身の経済的リスクや生活への影響が生じるおそれがあります。
| シーン | 発生するリスク | 注意点 |
|---|---|---|
| 銀行融資 | 個人保証の要求、信用調査への影響 | 過大な債務保証を回避する交渉が必要 |
| 取引先との契約 | 与信審査での業務執行社員の信用確認 | 個人信用情報の把握が求められる場合がある |
| 倒産や清算時 | 会社の負債を個人で弁済 | 会社規模や契約内容に注意 |
他社員・出資者との意見対立
合同会社は株式会社と異なり、社員全員が原則として経営に関与します。
そのため、業務執行社員間や他の社員・出資者との間で意見対立や経営方針の齟齬が生じやすいという特徴があります。
意見対立が解決できない場合、経営の停滞、出資者からの信頼低下、最悪の場合は社員間訴訟や会社分裂などのリスクに繋がることもあります。
業務量・心理的負担の増加
業務執行社員は会社のあらゆる運営判断に関与し、法的・実務的な責任を担うため、日常的な意思決定や業務対応、コンプライアンス管理まで幅広い負担が求められます。
これにより過度なストレスや業務過多となり、本業との両立やプライベートとのバランスが取りづらくなる場合も少なくありません。
社会保険や税務処理の煩雑さ
業務執行社員は「会社の役員」として社会保険や税務において特殊な扱いを受けます。
報酬の決定や源泉徴収、年末調整など制度運用の煩雑さを理解し、適切な手続きと管理を実施しない場合、税務リスクや追徴課税などの問題が発生する可能性があります。
特に複数の業務執行社員がいる場合、分配や申告に関する手続きが複雑化することに注意が必要です。
業務執行社員の選任・変更・退任の手続き方法
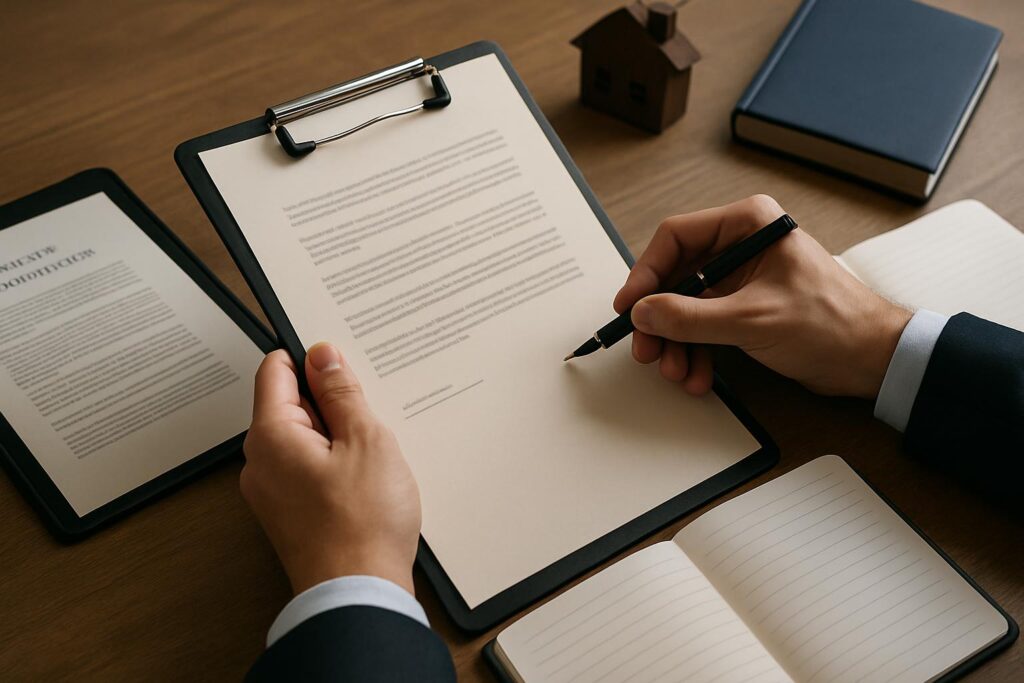
最初の選任手続き(設立時)
合同会社の設立時には、業務執行社員を必ず定款に記載し、設立登記申請時に選任します。
業務執行社員は、合同会社の経営を実際に執行する責任者であり、設立時点で少なくとも1名を定める必要があります。
定款に業務執行社員の氏名または名称・住所(法人の場合は所在地)を明記し、それに基づいて法務局へ登記を申請します。
途中での選任や追加・変更手続き
会社設立後に業務執行社員を追加・変更する場合は、社員総会などの定められた方法で新たな業務執行社員を選任します。
その内容は定款で規定されている場合が多く、選任の際には定款記載事項の変更が必要となることもあります。
定款の変更が必要な場合
業務執行社員を定款で定めている場合、新たな業務執行社員の追加や変更、または退任に当たっては、定款の変更手続きが必要となります。
この場合、社員総会で必要な決議(通常は社員全員の同意)が求められるため、注意が必要です。
定款変更は、会社の根本規則に関わるため、必ず法的な手続きを踏む必要があります。
法務局への登記申請
業務執行社員の追加・変更や退任が発生した場合には、その事実を明らかにするため、2週間以内に法務局で変更登記を行う義務があります。
登記申請を怠ると、過料などのペナルティが課されることがあるため、速やかに対応する必要があります。
| 手続内容 | 必要な場面 | 主な必要書類 | 登記申請先 |
|---|---|---|---|
| 業務執行社員の選任(設立時) | 会社設立時 | 登記申請書、定款、就任承諾書 | 本店所在地を管轄する法務局 |
| 業務執行社員の変更・追加 | 追加・変更時 | 社員総会議事録、就任承諾書、登記申請書、身分証 | 本店所在地を管轄する法務局 |
| 業務執行社員の退任 | 退任・解任時 | 退任届、社員総会議事録(解任の場合)、登記申請書 | 本店所在地を管轄する法務局 |
退任や解任の流れ
業務執行社員が退任または解任される場合は、定款の定めや会社法に従い手続きを行います。
自己都合の場合は退任届を作成・提出し、社員総会またはそれに準ずる方法で承認します。
解任の場合は、定款や社員間契約の規定に基づいた決議・議事録の作成が必要です。
退任または解任の効力発生日から2週間以内に法務局への登記申請を行うことが義務付けられています。
必要書類と費用の目安
業務執行社員の選任、追加、変更、退任・解任の際には、所定の書類を準備して法務局に提出する必要があります。
主な書類と登記費用は次のとおりです。
| 手続内容 | 主な必要書類 | 登録免許税(登記費用の目安) |
|---|---|---|
| 新規選任・変更登記 | 定款、就任承諾書、社員総会議事録(必要に応じて)、登記申請書、印鑑届書 | 1万円 |
| 退任登記 | 退任届、社員総会議事録(必要に応じて)、登記申請書 | 1万円 |
上記の他、状況により追加書類が必要となる場合がありますので、事前に法務局や専門家に相談することをおすすめします。
業務執行社員に関するよくある質問
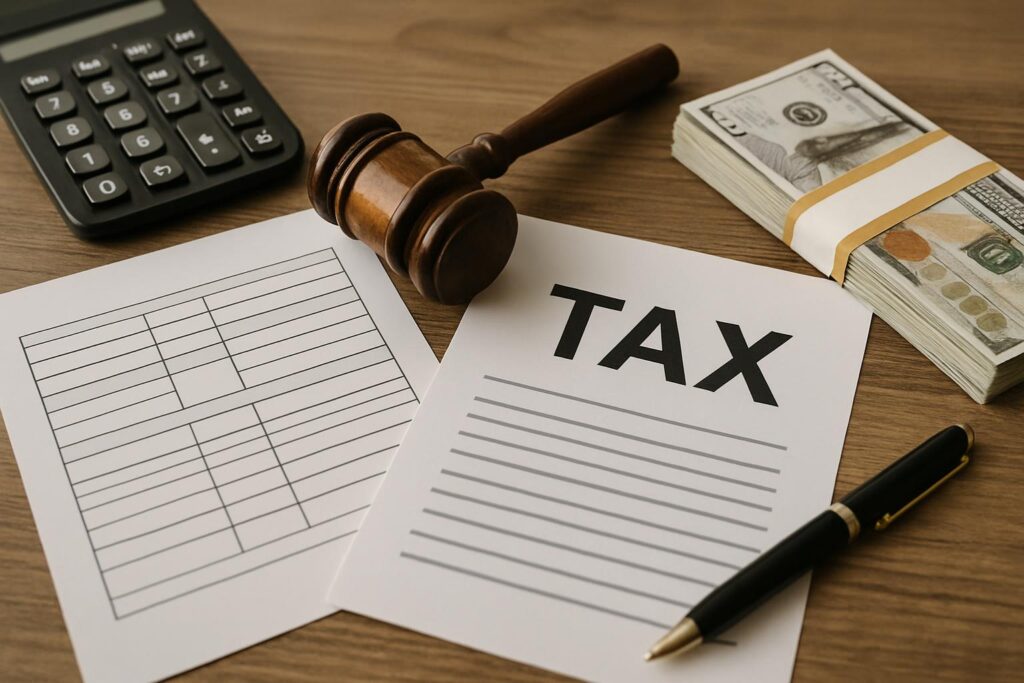
報酬や税金の取り扱いについて
合同会社の業務執行社員が受け取る報酬は、その性質によって「役員報酬」として取り扱われます。
このため、源泉徴収の対象となり、毎月の給与支給時に会社が所得税等を天引きします。
また、業務執行社員が法人である場合、報酬は法人の収入となり、法人税の課税対象になります。
業務執行社員が個人の場合は、所得税の課税対象です。
なお、報酬額は定款または社員総会の決議によって決めるのが一般的です。
| 項目 | 業務執行社員が個人の場合 | 業務執行社員が法人の場合 |
|---|---|---|
| 報酬の性質 | 役員報酬、給与所得 | 役員報酬、法人の事業収入 |
| 税金 | 所得税・住民税 | 法人税 |
| 源泉徴収 | 必要 | 不要(会社間取引のため) |
節税目的で業務執行社員の報酬を設定する場合は、税理士などの専門家に相談することが重要です。
複数人で業務執行社員になれるか
合同会社では、複数人が同時に業務執行社員になることが可能です。
個人だけでなく法人も選任できるため、共同経営や家族経営、グループ企業での運営など、さまざまな形態が認められています。
業務執行社員が複数いる場合は、業務執行の方法や権限配分について定款や業務分掌規程などで明確に定めておくと、将来的なトラブルを防ぐうえで有効です。
| 業務執行社員の人数 | 特徴 |
|---|---|
| 1人 | 迅速な意思決定が可能、意思疎通が容易 |
| 2人以上 | 役割分担や牽制がしやすい、複数の視点を反映できる |
なお、社員の中から業務執行社員を選ぶことが原則です。定款において一部の社員のみ業務執行社員とすることや、全員を業務執行社員とすることも可能です。
他の社員や職務執行者との関係
業務執行社員以外にも、合同会社の運営では「社員」や「職務執行者」といった役割が登場することがあります。
ここでの「社員」とは、出資者として合同会社の構成員(メンバー)のことを指します。
このうちの全員または一部のメンバーが業務執行社員として選任され、日常の会社運営を担います。
業務執行社員の業務執行権限を限定したり、社員間で議決権の割合を定款で自由に設定できることが合同会社の大きな特徴です。
さらに、社員が法人であり、その法人が自ら業務執行できない場合や個人であっても必要な場合、「職務執行者」を選任することができます。
下表に、社員・業務執行社員・職務執行者の主な違いを整理します。
| 区分 | 主な役割 | 選任者 | 登記の要否 |
|---|---|---|---|
| 社員 | 出資・会社の基本的意思決定 | 設立時に定める | 要(出資者は必ず登記) |
| 業務執行社員 | 業務執行・会社代表 | 定款・出資者が決定 | 要(代表社員も登記) |
| 職務執行者 | 実際に業務を遂行 | 社員(主に法人社員) | 要(登記必要) |
それぞれの役割や権限は定款で柔軟に定められるため、実際の運用に合わせて適切に取り決めることが重要です。
まとめ
合同会社の業務執行社員は、経営への大きな裁量権と柔軟な会社運営のメリットがある一方、無限責任を負う点や法的リスクにも注意が必要です。
選任・変更などの手続きには法務局での登記が必須となります。
正しい知識と手続きを踏まえて、合同会社設立や経営判断を慎重に行うことが重要です。