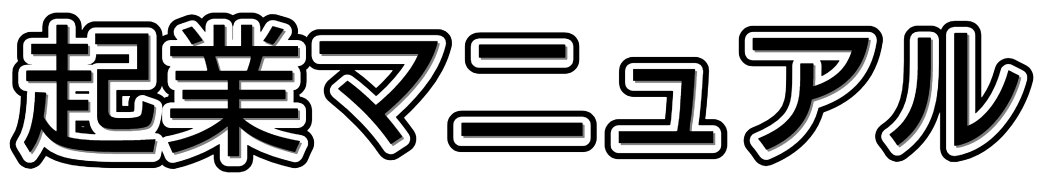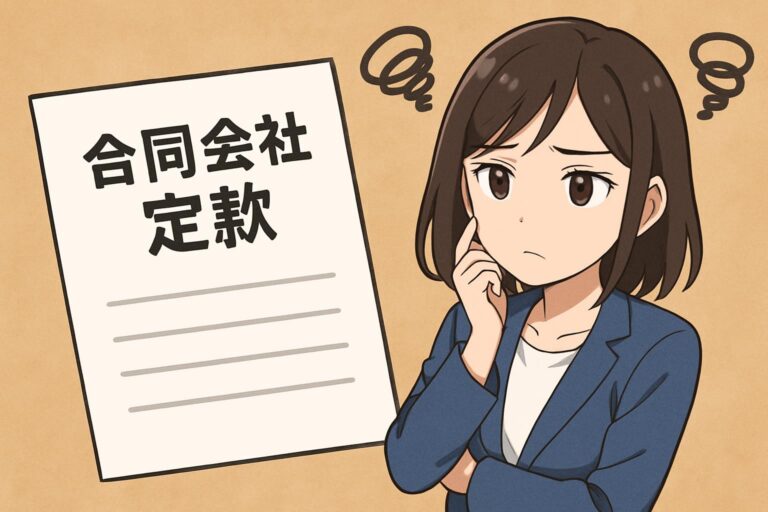合同会社の設立準備を進める中で、最初の関門となるのが「定款」の作成です。
何から手をつければいいのか、どんな項目を記載すればいいのか、費用はどれくらいかかるのか、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、合同会社の定款について、その役割といった基礎知識から、テンプレートを使った具体的な作り方の全手順、費用を4万円節約できる電子定款のメリットまで、初心者の方にも分かりやすく徹底解説します。
株式会社の定款と違って公証役場での認証が不要な合同会社の定款は、ポイントさえ押さえれば専門家に依頼せずご自身で作成することが可能です。
本記事を読めば、必要な準備から設立登記までの流れをすべて理解でき、スムーズに会社設立手続きを進められるようになります。
合同会社の定款とは 会社設立に不可欠な基本ルール
合同会社の設立を考えたとき、必ず作成しなければならない最重要書類が「定款(ていかん)」です。
定款とは、会社の目的、組織、運営、社員の権利義務など、会社の基本的なルールを定めた書類のことです。
その役割から「会社の憲法」とも呼ばれ、会社を設立し、運営していく上でのすべての活動の基礎となります。
この定款を作成し、法務局に登記申請をすることで、会社は「法人格」を得て、社会的な活動を行うことができるようになります。
つまり、定款がなければ合同会社を設立することはできません。
この章では、合同会社の定款が持つ役割と重要性、そして株式会社の定款との決定的な違いについて詳しく解説します。
定款の役割と重要性
定款は、単なる手続き上の書類ではなく、会社の根幹を支える複数の重要な役割を担っています。
その役割は、会社の内部に向けられたものと、外部に向けられたものの両側面があります。
まず、会社の内部に対しては、円滑な会社運営のための「ルールブック」として機能します。
合同会社は、出資者である「社員」が自ら経営を行うのが基本です。
そのため、社員間の意見の対立やトラブルを防ぎ、スムーズな意思決定を行うために、利益の配分方法、業務執行の権限、新たな社員の加入や退社の手続きといったルールをあらかじめ定款で明確にしておくことが極めて重要です。
これにより、健全で安定した会社経営の基盤が築かれます。
一方、会社の外部に対しては、その会社がどのような組織であるかを公的に証明する「自己紹介状」の役割を果たします。
金融機関から融資を受ける際や、取引先と重要な契約を結ぶ際には、定款の提出を求められることがあります。
定款に記載された事業目的や本店所在地、代表者の情報などは、会社の信用性を担保する上で不可欠な情報となるのです。
会社法という法律に基づいて作成されることで、定款は法的な拘束力を持ち、会社と社員の双方を守る盾にもなります。
株式会社の定款との大きな違い 公証役場での認証が不要
会社設立と聞くと、株式会社をイメージする方が多いかもしれません。
株式会社の設立手続きでは、作成した定款を「公証役場」に持ち込み、公証人にその内容が正当な手続きによって作成されたことを証明してもらう「認証」という手続きが必須です。
しかし、合同会社にはこの手続きがありません。
合同会社の定款は、公証役場での認証が不要です。これが株式会社との最も大きな違いであり、合同会社が迅速かつ低コストで設立できる最大の理由の一つです。
認証が不要なため、公証人に支払う約5万円の手数料がかからず、手続きにかかる時間も大幅に短縮できます。
なぜ合同会社では認証が不要なのでしょうか。
それは、合同会社が「人的会社」と呼ばれ、信頼関係のある少人数の社員(出資者)によって運営されることを前提としているためです。
社員間の合意が重視される組織形態であるため、株式会社ほど厳格な設立手続きが求められていないのです。
株式会社と合同会社の定款に関する主な違いを以下にまとめました。
| 比較項目 | 合同会社 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 公証役場での認証 | 不要 | 必要 |
| 認証手数料 | 0円 | 約3万円~5万円 |
| 収入印紙代(紙の定款の場合) | 4万円 | 4万円 |
| 設立にかかる費用(登録免許税を除く) | 紙定款:4万円 電子定款:0円 | 紙定款:約9万円 電子定款:約5万円 |
| 内容の自由度 | 高い(利益配分など自由設計が可能) | 比較的低い(会社法による規定が多い) |
このように、特に設立費用と手続きの手間において、合同会社には大きなメリットがあります。
この手軽さが、個人事業主からの法人成りや、小規模なビジネスを始める際の選択肢として、合同会社が人気を集めている理由です。
合同会社の定款作成を始める前の準備
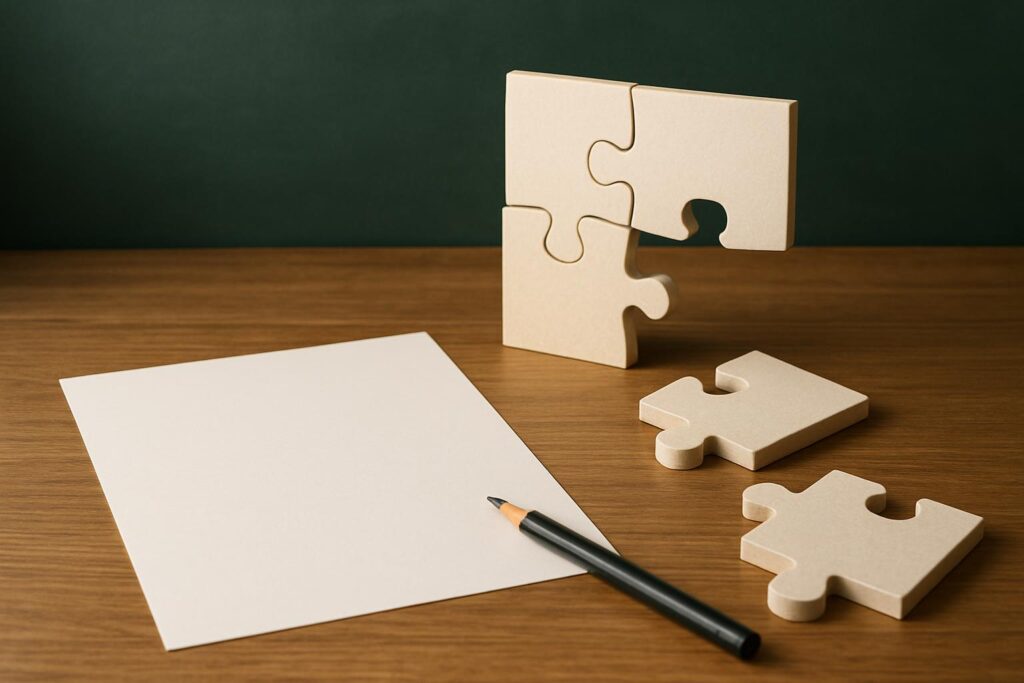
合同会社の定款作成は、パズルのピースを組み立てる作業に似ています。
いきなり作り始めるのではなく、まずは必要なピース(会社の基本情報)を集め、準備を整えることが成功への近道です。
この章では、定款という会社の設計図を描く前に、必ず決めておくべき基本事項と、準備すべきものを具体的に解説します。
ここをしっかり固めることで、後のステップが驚くほどスムーズに進みます。
まず決めるべき会社の基本事項7つ
定款に記載する内容は法律で定められていますが、その土台となるのが会社の基本情報です。
以下の7つの項目は、会社の根幹をなす非常に重要な要素であり、定款の「絶対的記載事項」にも深く関わってきます。
事前にこれらを決定し、メモなどにまとめておきましょう。
商号(会社名)
商号は会社の「顔」となる大切な名称です。
自由に決められますが、いくつかのルールを守る必要があります。
最も重要なルールは、会社の種類を示す「合同会社」という文言を必ず商号に含める必要があることです。
社名の前につけるか(合同会社〇〇)、後につけるか(〇〇合同会社)は自由に選択できます。
使用できる文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字・小文字)、アラビア数字(0,1,2…)、そして「&」「’」「,」「-」「.」「・」の6種類の記号です。
ただし、記号は字句を区切る目的でのみ使用できます。
また、同一の本店所在地に、既に同じ商号の会社が登記されている場合は、その商号を使用することはできません。
トラブルを避けるためにも、事前に法務局の「オンライン登記情報検索サービス」や国税庁の「法人番号公表サイト」で、希望する商号が使用可能か調査しておくことを強く推奨します。
事業目的
事業目的は、その会社が「何をして利益を上げるのか」を具体的に示す項目です。
定款には、実際に行う事業内容を明確に記載する必要があります。
ポイントは、将来行う可能性のある事業も、あらかじめ記載しておくことです。
後から事業目的を追加するには、定款変更の手続きと登記(登録免許税3万円)が必要になり、余計なコストと手間がかかってしまいます。
事業目的を記載する際は、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 適法性:法律に違反する事業や公序良俗に反する事業は記載できません。
- 営利性:ボランティア活動など、利益を目的としない活動は事業目的として認められません。
- 明確性:誰が読んでも理解できる具体的な言葉で記載する必要があります。
また、建設業や飲食業、古物商など、事業を行うにあたって国や都道府県の許認可が必要な業種があります。
その場合は、許認可の要件を満たす文言を事業目的に含めないと、後々の許認可申請が通らない可能性があるため注意が必要です。
最後に「前各号に附帯又は関連する一切の事業」という一文を入れておくと、事業内容の範囲を広くカバーできます。
本店所在地
本店所在地とは、会社の主たる営業所の住所のことです。
納税地を管轄する税務署が決まったり、裁判の管轄が決まったりと、法律上の重要な拠点となります。
定款への記載方法は2通りあります。
- 最小行政区画まで記載する方法(例:「東京都新宿区」)
この方法のメリットは、同じ市区町村内で移転する場合、定款を変更する必要がない点です。登記の変更だけで済むため、手間とコストを抑えられます。 - 地番まで詳細に記載する方法(例:「東京都新宿区西新宿二丁目8番1号」)
この場合、少しでも場所が移転すると、その都度定款変更の手続きが必要になります。
特別な理由がない限り、最小行政区画(市区町村)までの記載にしておくと、将来の移転に柔軟に対応できるためおすすめです。
なお、自宅や賃貸オフィス、バーチャルオフィスでも登記は可能ですが、賃貸物件の場合は契約書で法人登記が禁止されていないか、事前に必ず確認してください。
資本金の額
資本金は、社員(出資者)が事業を始めるために会社に払い込む資金のことです。
会社の体力や信用度を示す指標の一つとなります。
会社法上は1円からでも会社を設立できますが、設立直後は売上がすぐには立たないことも多いため、当面の運転資金(少なくとも3ヶ月~6ヶ月分)を目安に設定するのが一般的です。
法律上は1円から設立可能ですが、会社の信用度や初期の運転資金を考慮して適切な金額を設定することが肝心です。
資本金の額は、金融機関から融資を受ける際の審査や、取引先との与信調査でチェックされることがあります。
また、資本金が1,000万円未満の場合、原則として設立から2事業年度は消費税の納税が免除されるというメリットもあります。
資本金は現金だけでなく、パソコンや自動車、不動産といった「モノ」で出資する「現物出資」も可能です。
社員の構成
合同会社における「社員」とは、一般的に使われる「従業員」のことではありません。
合同会社の「社員」とは、従業員ではなく会社への出資者のことを指します。
株式会社における「株主」にあたる存在です。
定款には、出資者である全社員の情報を記載する必要があります。
具体的には、以下の項目を正確に記載します。
- 社員の氏名(または名称)
- 社員の住所
- 各社員がいくら出資するのか(出資価額)
社員が個人の場合は氏名と住所、法人の場合はその名称と本店所在地を記載します。
一人で合同会社を設立する場合は、ご自身の情報を記載することになります。
事業年度
事業年度とは、会社の利益などを計算するための会計期間のことです。
この期間の最終日を「決算日」と呼びます。事業年度は1年以内の期間であれば、自由に設定することができます。
日本の多くの企業は「4月1日から翌年3月31日まで」としていますが、法人の場合は「1月1日から12月31日まで」や、設立日から1年後の前月末までなど、自由に決めることが可能です。
決算月を決める際は、以下のような点を考慮すると良いでしょう。
- 会社の繁忙期と決算・申告業務が重ならないようにする。
- 消費税の免税期間を最大限活用するため、設立日からできるだけ遠い月を決算月にする。
- 大きな売上が見込める月の直後を決算月にして、役員報酬の決定などに役立てる。
一度決定すると変更には手間がかかるため、自社の繁忙期や資金繰りを考慮して慎重に決定しましょう。
決算日から2ヶ月以内に、法人税などの確定申告と納税を行う必要があります。
代表社員と業務執行社員
合同会社では、原則として出資者である「社員」全員が会社の業務を行う権利(業務執行権)と、会社を代表する権利(代表権)を持ちます。
しかし、社員が複数いる場合、全員が代表権を持つと意思決定が煩雑になる可能性があります。
そこで、定款で役割分担を定めることができます。
- 業務執行社員:会社の業務を実際に行う権限を持つ社員。定款で一部の社員のみを業務執行社員と定めることができます。
- 代表社員:業務執行社員の中から選ばれ、会社を代表して契約などの法律行為を行う権限を持つ社員。株式会社の「代表取締役」に相当する役職です。
社員が複数いる場合は、役割と責任を明確にするため、定款で業務執行社員や代表社員を定めておくことが推奨されます。
なお、業務執行社員を特に定めない場合は、社員全員が業務執行社員となります。
一人合同会社の場合は、その社員が自動的に業務執行社員であり、代表社員となります。
定款作成に必要なものリスト
会社の基本事項が決まったら、実際に定款を作成するために必要なものを揃えましょう。
事前に準備しておくことで、作業をスムーズに進めることができます。
| 必要なもの | 用途・補足説明 |
|---|---|
| 決定した会社の基本事項 | 上記7項目(商号、事業目的、本店所在地など)をまとめたメモ。 定款のひな形に転記する際の元情報となります。 |
| 社員全員の印鑑証明書 | 設立登記申請時に必要となりますが、定款に記載する氏名や住所が印鑑証明書の内容と完全に一致している必要があるため、この段階で準備しておくと間違いを防げます。 発行から3ヶ月以内のものが必要です。 |
| 会社の実印(法人実印) | 法務局に登録する会社の代表印です。 設立登記申請書への押印に必要となるため、このタイミングで作成しておくとスムーズです。 |
| パソコン、プリンター | 定款のデータ作成や、紙の定款を作成する場合の印刷に利用します。 |
| (電子定款の場合) 追加で必要なもの | マイナンバーカード、ICカードリーダーライタ、PDFファイルを作成・編集できるソフト(Adobe Acrobatなど)が必要です。 |
特に社員全員の印鑑証明書は、記載内容の正確性を確認するためにも早めに準備しましょう。
これらの準備が整えば、いよいよ定款の具体的な作成ステップに進むことができます。
合同会社の定款に記載すべき3つの重要事項

合同会社の定款を作成するにあたり、記載すべき事項は会社法によって3つの種類に分類されています。
それが「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」です。
これらはそれぞれ重要度が異なり、記載を怠ると定款自体が無効になったり、定めたルールが法的に認められなかったりする場合があります。
会社の憲法ともいえる定款を正しく作成するために、それぞれの違いと内容を正確に理解しておきましょう。
必ず記載する絶対的記載事項
絶対的記載事項とは、その名の通り、定款に必ず記載しなければならない事項です。
会社法第576条第1項で定められており、もしこのうちの一つでも記載が漏れていると、作成した定款そのものが無効となってしまいます。
会社の根幹をなす最も重要な情報であり、合同会社設立の際には細心の注意を払って記載する必要があります。
合同会社の絶対的記載事項は、以下の6項目です。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 商号 | 会社の名称のことです。 会社の名前の前か後ろに必ず「合同会社」という文字を入れなければなりません。 |
| 事業目的 | 会社がどのような事業を行うのかを具体的に記載します。 将来的に行う可能性のある事業も記載しておくことが可能です。 適法性、営利性、明確性が求められます。 |
| 本店所在地 | 会社の本拠地となる住所です。 定款には最小行政区画(例:「東京都新宿区」)までの記載で足りますが、設立登記申請までには地番までの詳細な住所を決定する必要があります。 |
| 社員の氏名又は名称及び住所 | 会社に出資する全社員の氏名(法人の場合は名称)と住所を記載します。 個人の場合は印鑑証明書、法人の場合は登記簿謄本に記載されている通りに正確に記述します。 |
| 社員が有限責任社員であること | 合同会社の社員は、株式会社の株主と同様に、会社の債務に対して出資額の範囲内でのみ責任を負う「有限責任」です。 このことを明確に記載します。 |
| 社員の出資の目的及びその価額又は評価の標準 | 全社員がそれぞれいくら、何を(金銭または現物)出資するのかを記載します。 金銭で出資する場合はその金額を、不動産やPCなどの現物で出資する場合はその価額を記載します。 |
定めなければ効力が生じない相対的記載事項
相対的記載事項とは、定款に記載がなくても定款自体の効力には影響しませんが、記載しなければその定め(ルール)の効力が法的に認められない事項を指します。
絶対的記載事項とは異なり、必ず定めなければならないわけではありません。
しかし、会社の運営方針や社員間のルールを明確にするために、多くの会社がこれらの事項を定款に記載しています。
合同会社でよく定められる相対的記載事項の例は以下の通りです。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 代表社員の定め | 会社の代表者を特定の社員に定める場合、その氏名(名称)と住所を記載します。 定めがない場合、原則として社員全員が会社の代表権を持つことになります。 |
| 業務執行社員の定め | 会社の業務執行権を持つ社員を特定の者に限定する場合に記載します。 定めがない場合は、原則として社員全員が業務執行権を持ちます。 |
| 社員の退社事由 | 会社法で定められている事由(事業年度の終了時の予告など)以外に、独自の退社事由(例:他の社員全員の同意)を設ける場合に記載します。 |
| 持分の譲渡に関する定め | 社員がその持分を他人に譲渡する際のルールを定めます。 原則は他の社員全員の同意が必要ですが、定款で「業務執行社員の過半数の同意」など、別の定めを置くことができます。 |
| 会社の存続期間や解散事由 | 会社の存続期間を限定したり、特定の事由が発生した場合に会社を解散するといったルールを設けたりする場合に記載します。 |
任意で定められる任意的記載事項
任意的記載事項とは、定款に記載しなくても定款の効力に影響がなく、たとえ記載しなくても会社のルールとして有効な事項です。
ただし、会社法などの法律(強行法規)に違反する内容は定めることができません。
定款に記載することで、会社の運営ルールをより明確にし、社員間のトラブルを未然に防ぐ役割を果たします。
任意的記載事項として一般的に定められることが多い項目には、以下のようなものがあります。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 事業年度 | 会社の会計期間(決算期)を定めます。 例えば「毎年4月1日から翌年3月31日まで」のように記載します。 法人税の確定申告時期に関わるため、ほとんどの会社が定款で明確に定めています。 |
| 社員の報酬の決定方法 | 業務執行社員の報酬をどのように決定するか(例:社員の過半数の同意をもって決定する)を定めます。 報酬に関するルールを明確にすることで、将来的なトラブルを防ぎます。 |
| 社員総会の招集・議決方法 | 会社の重要事項を決定する社員総会の招集手続きや議決要件などを定めます。 |
| 公告方法 | 会社が重要な情報を知らせる(公告する)際の方法を定めます。 「官報に掲載する方法とする」「電子公告とする」などがあります。 定款に定めがない場合は、自動的に「官報」が公告方法となります。 |
【全手順】合同会社の定款の作り方を5ステップで解説
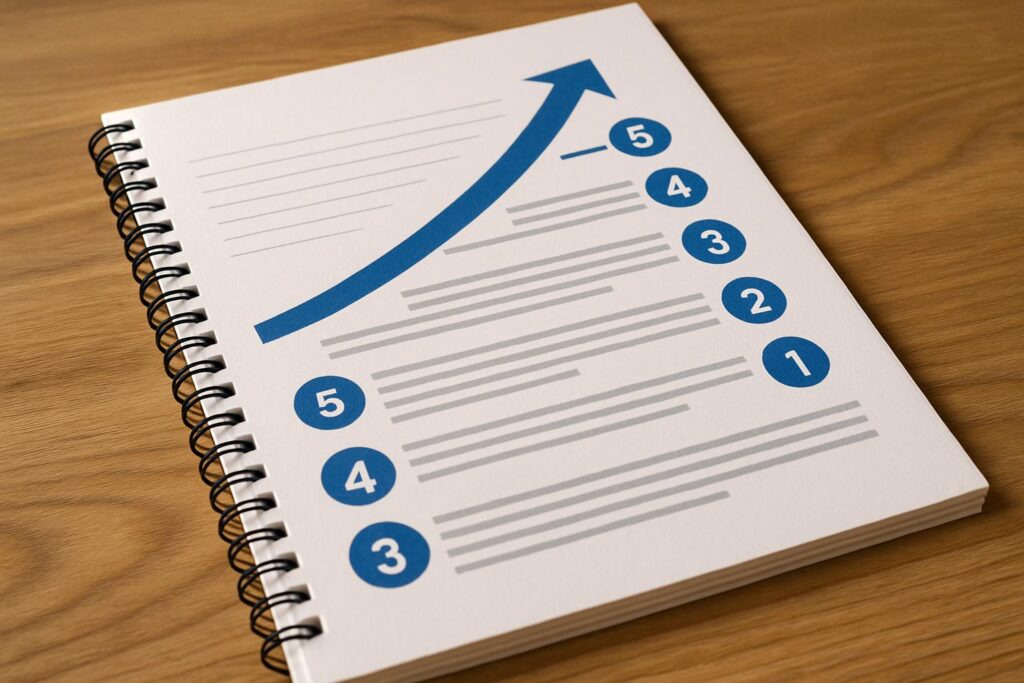
合同会社の定款作成は、専門知識がなくても手順に沿って進めれば、ご自身で完成させることが可能です。
ここでは、初めての方でも迷わずに定款を作成できるよう、具体的な5つのステップに分けて全手順を詳しく解説します。
ひな形を活用し、一つずつ着実に進めていきましょう。
ステップ1 定款のひな形(テンプレート)を用意する
定款をゼロから作成するのは非常に手間がかかり、記載漏れのリスクも高まります。
まずは、信頼できる機関が提供しているひな形(テンプレート)を入手することから始めましょう。
ひな形は主に以下の場所で入手できます。
- 法務局のウェブサイト: 国の機関である法務局が提供する基本的な様式です。最もシンプルで、自社の状況に合わせてカスタマイズするのに適しています。
- 日本公証人連合会のウェブサイト: 公証役場の連合会が提供しており、こちらも信頼性が高いひな形です。株式会社のものが中心ですが、合同会社の定款作成の参考になります。
- 会社設立支援のクラウドサービス: 「マネーフォワード クラウド会社設立」や「会社設立freee」などのサービスでは、質問に答えるだけで自社に合った定款を自動で作成できます。電子定款の作成まで一貫してサポートしてくれる点が魅力です。
- 書籍やウェブサイト: 会社設立に関する書籍の付録や、専門家が監修するウェブサイトでも、Word形式などでダウンロードできるテンプレートが提供されています。
どのひな形を選ぶ場合でも、Word(.docx)など編集しやすい形式のものを選ぶと、後の作業がスムーズに進みます。
まずはこれらの方法で自社に合ったひな形を手元に準備してください。
ステップ2 会社の基本事項をひな形に反映させる
ひな形が準備できたら、次に「合同会社の定款作成を始める前の準備」の章で決めた会社の基本事項を、ひな形の該当箇所に正確に記入していきます。
これらは定款の根幹をなす「絶対的記載事項」が中心となります。
誤字脱字がないよう、慎重に入力しましょう。
具体的には、以下の項目をひな形に反映させていきます。
| 記載事項 | 記載例 | ワンポイントアドバイス |
|---|---|---|
| 商号 | 第1条(商号) 当会社は、合同会社〇〇と称する。 | 会社の種類(合同会社)を必ず商号の前か後ろに付けます。 使用可能な文字や記号のルール(法務局のサイトで確認)も守りましょう。 |
| 事業目的 | 第2条(目的) 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. Webサイトの企画、制作及び運営 2. 経営コンサルティング業務 3. 前各号に附帯関連する一切の事業 | 将来行う可能性のある事業も具体的に記載しておくと、後で定款変更する手間が省けます。 適法性、営利性、明確性を意識して記載します。 |
| 本店所在地 | 第3条(本店の所在地) 当会社は、本店を東京都新宿区に置く。 | 最小行政区画(市町村、東京23区)までの記載で構いません。これにより、同じ市区町村内での移転であれば定款変更が不要になります。 |
| 社員の氏名・住所 | (社員及び出資) 社員の氏名及び住所、各社員の出資の価額は次のとおりである。 住所 東京都〇〇区〇〇一丁目2番3号 氏名 〇〇 〇〇 金100万円 | 社員全員の氏名と住所を記載します。 この情報は登記申請時に提出する印鑑証明書と一字一句同じである必要があります。 |
| 社員の出資 | (社員及び出資) 当会社の社員は、すべて有限責任社員とする。 | 合同会社の社員は全員が有限責任社員であることを明記します。 出資の目的が金銭のみの場合は「金銭」、現物出資がある場合はその旨と価額を記載します。 |
| 資本金の額 | (資本金の額) 当会社の資本金の額は、金100万円とする。 | 全社員の出資額の合計金額を記載します。 この金額が登記上の資本金となります。 |
ステップ3 相対的記載事項と任意的記載事項を追記する
ひな形はあくまで基本的な骨格です。会社の運営を円滑にし、将来のトラブルを避けるためには、自社の実情に合わせて相対的記載事項や任意的記載事項を追加することが重要です。
特に社員が複数いる場合は、社員間のルールを明確に定めておくことが、安定した会社経営の鍵となります。
以下のような項目について、追記を検討しましょう。
追記を検討すべき相対的記載事項の例
- 代表社員の定め: 社員が複数いる場合、誰が会社を代表するのかを定めます。「社員の互選による」「特定の氏名を指定する」などの方法があります。
- 業務執行社員の定め: 業務を執行する社員と、出資のみを行う社員を分ける場合に定めます。
- 社員の退社事由: 会社法で定められた事由以外にも、独自の退社事由(例:他の社員全員の同意)を追加できます。
- 持分の譲渡制限: 社員が持分を第三者に譲渡する際のルールを定めます。「他の社員全員の承諾を要する」といった定めが一般的です。
追記を検討すべき任意的記載事項の例
- 事業年度: 「当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。」のように定めます。決算期や法人税の申告時期に関わる重要な項目です。
- 利益の配当: 利益を配当する際の基準や手続きについて定めます。
- 役員報酬の決定方法: 業務執行社員の報酬をどのように決定するか(例:総社員の過半数の同意)を定めておくと、後のトラブル防止になります。
これらの項目は、社員全員で十分に話し合い、合意の上で定款に盛り込むようにしてください。
ステップ4 作成した定款に不備がないか最終チェック
すべての記載が終わったら、最後に全体を隅々まで見直し、不備がないか最終チェックを行います。
ここでの見落としは、法務局での登記申請が受理されない原因となり、設立手続きが遅れてしまう可能性があります。
最低でも以下の項目は必ず確認してください。
- 絶対的記載事項(商号、目的、本店所在地、社員の氏名・住所、有限責任社員である旨、出資の価額)に漏れはないか?
- 会社の基本情報(商号、目的、本店所在地など)に誤字脱字はないか?
- 社員全員の氏名・住所は、印鑑証明書の記載と完全に一致しているか?
- 各社員の出資額の合計と、定款に記載した資本金の額は一致しているか?
- 条文の番号は、第1条から順番に正しく振られているか?
- 定款の末尾に、作成年月日と社員全員の署名(または記名押印)欄が用意されているか?
自分一人だけでなく、他の社員にも読んでもらうなど、複数人の目でダブルチェック、トリプルチェックすることをおすすめします。
ステップ5 定款を製本または電子ファイル化する
最終チェックが完了したら、定款を正式な形に整えます。
定款には「紙の定款」と「電子定款」の2種類があり、どちらを選ぶかによって最後の仕上げ方が異なります。(詳細は次の章で解説します)
紙の定款の場合
- 作成した定款をプリンターで印刷します。登記申請用に最低3部(法務局提出用、会社保存用、謄本)印刷しておくと安心です。
- 印刷した書類をすべて重ね、左側をホッチキスで2箇所留めます。
- 全ページの見開き部分に、社員全員の実印で「契印」を押します。または、製本テープで袋とじにして、裏表紙とテープの境目に「割印」を押します。
- 最終ページの末尾にある署名欄に、社員全員が署名または記名し、実印を押印します。
- 法務局へ提出する原本1部の表紙または収入印紙貼付台紙に、4万円分の収入印紙を貼り、消印(実印で押印)をします。
電子定款の場合
- 作成した定款(Wordファイルなど)をPDF形式で保存します。
- PDFファイルに、社員全員分の電子署名を付与します。これには、マイナンバーカードとICカードリーダライタ、専用のソフトウェア(Adobe Acrobatなど)が必要です。
電子定款は収入印紙の4万円が不要になるという大きなメリットがあります。
必要な機材やソフトウェアの準備が必要ですが、コストを抑えたい場合は電子定款の作成を強くおすすめします。
これで、合同会社設立の最重要書類である定款の作成は完了です。
電子定款と紙の定款 どちらを選ぶべきか
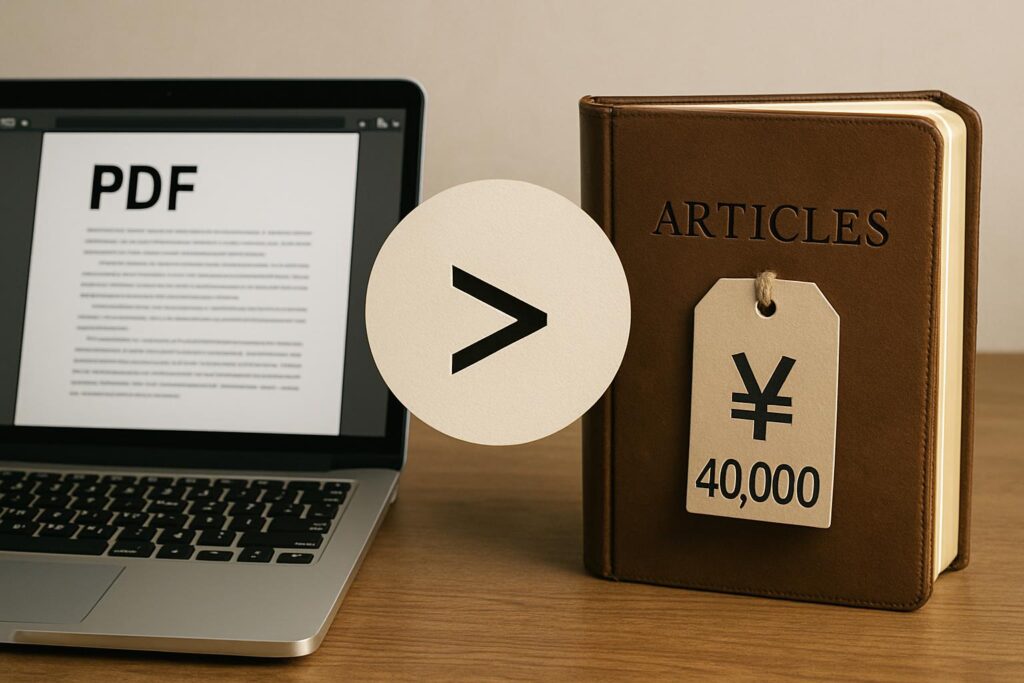
合同会社の定款を作成する方法には、「電子定款」と「紙の定款」の2種類があります。
どちらの方法を選ぶかによって、設立にかかる費用や手間が大きく異なります。
結論から言うと、設立費用を少しでも抑えたいのであれば、電子定款が圧倒的におすすめです。
ここでは、それぞれのメリット・デメリットを比較し、どちらがご自身の状況に適しているかを判断するための情報を提供します。
まずは、両者の違いを一覧で確認してみましょう。
| 比較項目 | 電子定款 | 紙の定款 |
|---|---|---|
| 収入印紙代 | 不要(4万円節約) | 必要(4万円) |
| 作成方法 | PDFファイルを作成し、電子署名を付与する | 印刷して製本し、押印・割印する |
| 必要なツール | パソコン、マイナンバーカード、ICカードリーダライタ、特定ソフト(Adobe Acrobatなど) | パソコン、プリンター、ホッチキス、製本テープ |
| メリット | ・設立費用を大幅に削減できる ・オンラインで手続きが完結できる ・データの保管や共有が容易 | ・特別な機材やソフトが不要 ・手順が直感的で分かりやすい |
| デメリット | ・ICカードリーダライタ等の初期投資が必要 ・電子署名の設定に手間がかかる場合がある | ・収入印紙代4万円のコストがかかる ・製本や押印、割印の手間がかかる |
この比較からもわかるように、コスト面でのメリットは電子定款が非常に大きいです。
以下で、それぞれの作成方法について詳しく解説します。
収入印紙4万円が不要な電子定款のメリット
電子定款を選択する最大のメリットは、収入印紙代の4万円が不要になることです。
印紙税法では、課税対象となるのは「紙の文書」と定められています。電子定款はPDFなどの電子データであり、紙の文書ではないため、印紙税の課税対象外となります。
この1点だけでも、電子定款を選ぶ価値は十分にあると言えるでしょう。
その他にも、電子定款には以下のようなメリットがあります。
- 手間の削減: 紙の定款で必要な印刷、製本、社員全員の押印・割印といった物理的な作業が一切不要です。作成から登記申請まで、すべての手続きをパソコン上で完結させることも可能です。
- 保管・管理の容易さ: 作成した定款は電子データとして保管できます。紙のように保管場所を取らず、紛失や劣化のリスクも低減できます。また、データの複製や共有も簡単です。
- 修正が比較的簡単: 電子署名を付与する前であれば、内容の修正はWordなどの元データを編集するだけで済みます。紙のように一から印刷し直す必要がありません。
電子定款の作成方法と必要なツール
電子定款を作成するには、いくつかの専用ツールを準備する必要があります。
すでに持っているものもあれば、新たに購入が必要なものもあるかもしれません。
電子定款の作成に必要なもの
- パソコン: Windows、Macのどちらでも作成可能です。
- マイナンバーカード: カードに格納されている「電子証明書」を利用して電子署名を行います。事前に市区町村の役所で発行手続きを済ませておきましょう。
- ICカードリーダライタ: マイナンバーカードを読み込むための機器です。家電量販店やオンラインストアで数千円程度で購入できます。
- ソフトウェア:
- PDF作成ソフト: 電子署名機能が付いたPDF作成ソフトが必要です。一般的には「Adobe Acrobat」の有料版が利用されます。
- 法務省の申請用総合ソフト: 登記・供託オンライン申請システムからダウンロードできる専用ソフトです。PDFファイルへの電子署名付与やオンライン申請に利用します。
これらのツールを揃えるのに初期費用がかかる点が、電子定款の唯一のデメリットと言えるかもしれません。
ただし、4万円の収入印紙代が節約できることを考えれば、十分に元が取れる投資です。
司法書士などの専門家に設立手続きを依頼する場合、専門家はこれらのツールをすべて揃えているため、ご自身で用意する必要はありません。
紙の定款の作り方と製本方法
特別なツールを準備せずに定款を作成したい場合は、従来通りの紙の定款を選択することになります。
ただし、前述の通り4万円の収入印紙が必要になる点は理解しておきましょう。
紙の定款の作成と製本の手順
- 印刷: 作成した定款のデータをA4用紙に印刷します。登記申請用に法務局へ提出する「原本」、会社で保管する「謄本」の2部を作成するのが一般的です。
- 製本: 印刷した用紙をページの順番通りに重ね、左側をホッチキスで2〜3箇所留めます。
- 押印: 最後のページの末尾に、商号(会社名)と社員全員の氏名を記載し、各自の実印を押印します。
- 割印(契印): 定款の抜き取りや差し替えを防ぐため、すべてのページにまたがるように、見開きの境目に社員全員が実印で割印(契印)を押します。
- 製本テープ: ホッチキスで留めた背表紙部分を製本テープで覆い、見た目を整えます。
- 収入印紙の貼付と消印: 法務局へ提出する原本の表紙の裏などに、4万円分の収入印紙を貼り付けます。そして、印紙と台紙にまたがるように実印で消印を押します。消印を忘れると印紙税を納付したことにならないため、注意が必要です。
このように、紙の定款は物理的な作業が多く、特に社員が複数人いる場合は、全員の押印や割印を取りまとめる手間がかかります。
これらの手間とコストを考慮した上で、どちらの方法で定款を作成するかを慎重に検討しましょう。
合同会社の定款作成後から設立登記までの流れ
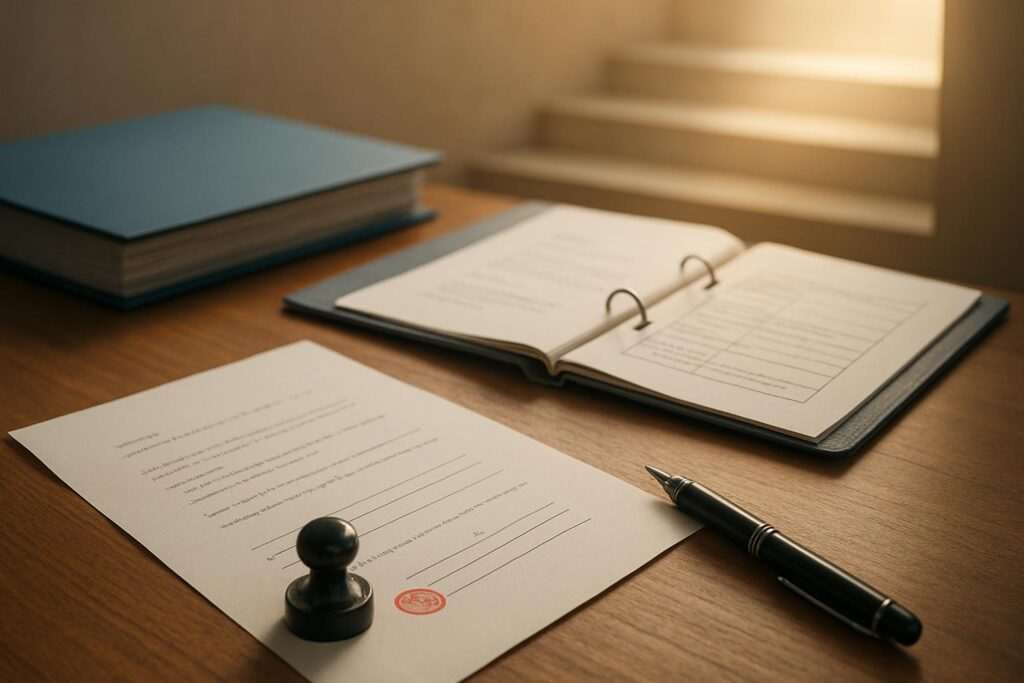
定款の作成が完了しても、それだけで会社が設立されたわけではありません。
定款は会社のルールブックであり、これを基に法務局へ「会社の設立登記」を申請し、受理されることで初めて法的に会社が成立します。
ここでは、定款作成後から設立登記完了までの具体的なステップを詳しく解説します。
定款以外の設立書類を準備する
設立登記を申請するには、作成した定款の他にもいくつかの書類が必要です。
抜け漏れがないように、以下のリストを参考にして一つずつ丁寧に準備を進めましょう。
特に資本金の払込を証明する書類は、手続きが簡単な合同会社のメリットが表れる部分です。
| 必要書類 | 概要と注意点 |
|---|---|
| 設立登記申請書 | 法務局のウェブサイトからひな形をダウンロードできます。 商号や本店所在地、代表社員の氏名・住所、登録免許税額などを記載する、登記申請の中心となる書類です。 |
| 定款 | 作成した会社の定款です。紙の定款の場合は製本・押印したもの、電子定款の場合はCD-Rなどに保存したデータを提出します。 |
| 代表社員の印鑑証明書 | 発行から3ヶ月以内のものが必要です。 代表社員個人の実印に関する証明書で、市区町村役場で取得します。 |
| 資本金の払込証明書 | 株式会社と異なり、金融機関の証明は不要です。 代表社員個人の銀行口座に資本金全額を振り込み、その通帳の「表紙」「1ページ目(口座名義人などが記載されたページ)」「振込が記帳されたページ」のコピーをまとめて作成します。 |
| 本店所在地決定書 | 定款で「東京都新宿区」のように市区町村までしか定めていない場合に、具体的な地番までの所在地を決定したことを証明する書類です。 業務執行社員全員の合意が必要です。 |
| 業務執行社員の就任承諾書 | 定款で業務執行社員を定めていない場合や、定款作成者以外の人物が業務執行社員に就任する場合に必要となります。 |
| 印鑑届書 | 会社の実印(代表者印)を法務局に登録するための書類です。 この届出により、会社の印鑑証明書が発行できるようになります。 |
法務局へ設立登記申請を行う
すべての書類が揃ったら、いよいよ法務局へ設立登記の申請を行います。
申請手続きが完了して初めて、あなたの会社が社会的に認められることになります。
申請先は、会社の本店所在地を管轄する法務局です。
管轄は法務局のウェブサイトで確認できますので、事前に調べておきましょう。
申請方法は、以下の3つから選ぶことができます。
- 窓口申請:管轄の法務局へ直接書類を持参する方法です。不備があればその場で修正を求められるため、確実性が高いのがメリットです。
- 郵送申請:管轄の法務局へ書類を郵送する方法です。法務局へ出向く手間が省けますが、書類に不備があった場合、修正に時間がかかる可能性があります。
- オンライン申請:「登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと)」を利用してインターネット経由で申請する方法です。電子定款と組み合わせることで、すべての手続きをオンラインで完結させることも可能です。
ここで最も重要な点は、法務局が申請書を受理した日が「会社の設立日」になるということです。
特定の日を設立日にしたい場合は、その日に合わせて申請する必要があります。
また、申請時には登録免許税として最低6万円(資本金の額の0.7%と比較し、高い方)を収入印紙で納付する必要があります。
申請から登記が完了するまでは、通常1週間から2週間程度かかります。
設立後の定款の保管方法
無事に設立登記が完了したら、作成した定款を適切に保管しなければなりません。
会社法では、定款を会社の本店に備え置くことが義務付けられています。
紙の定款の場合
製本し、社員全員が記名押印した定款の「原本」を、本店事務所の金庫など安全な場所に保管します。
金融機関での口座開設や各種許認可の申請時には、この原本をコピーして提出することが一般的です。
電子定款の場合
電子定款は、電子署名が付与されたPDFファイルそのものが「原本」となります。
そのため、印刷した紙はあくまで「写し」としての扱いです。
原本データは、パソコンやサーバー、クラウドストレージなどに厳重に保管し、必ずバックアップを取っておきましょう。
法務局へ提出したCD-RやDVD-Rも大切に保管してください。
各種手続きで定款の提出を求められた際は、この電子定款のデータを印刷して提出します。
定款は会社の根幹をなす重要な書類です。
設立後も様々な場面で必要となるため、いつでも取り出せるように大切に管理しましょう。
合同会社の定款に関するよくある質問

合同会社の定款作成にあたって、多くの方が疑問に思う点をQ&A形式でまとめました。
設立手続きを進める上での不安や疑問をここで解消しましょう。
定款の内容は後から変更できますか
はい、合同会社の定款は、会社設立後でも変更することが可能です。
会社の成長や事業内容の変化に合わせて、定款も柔軟に見直していく必要があります。
定款の変更には、原則として「総社員の同意」が必要となります。
社員全員で話し合い、合意が得られたら「総社員の同意書」または「業務執行社員の過半数の一致を証する書面」など、定款で定めた方法に従って決議の証明書類を作成します。
ただし、変更した内容によっては、法務局での「変更登記」手続きが別途必要になる点に注意が必要です。
変更登記が必要な主な項目と、その際に発生する登録免許税は以下の通りです。
| 変更する項目 | 変更登記の要否 | 登録免許税 |
|---|---|---|
| 商号(会社名) | 必要 | 3万円 |
| 事業目的 | 必要 | 3万円 |
| 本店所在地(移転) | 必要 | 3万円(管轄法務局内) 6万円(管轄法務局外) |
| 資本金の額(増資) | 必要 | 増加資本金額の1000分の7(最低3万円) |
| 社員の加入・退社 | 必要 | 3万円(資本金の額が増加しない場合) |
| 事業年度 | 不要 | – |
| 利益の配当に関する規定 | 不要 | – |
変更登記が必要な項目を変更したにもかかわらず、変更があった日から2週間以内に登記申請を怠ると、代表社員が100万円以下の過料(罰金)に処せられる可能性があるため、速やかに手続きを行いましょう。
一人合同会社の定款作成で注意する点はありますか
一人合同会社(社員が1名のみの合同会社)の定款作成は、基本的な記載事項は複数人いる場合と変わりませんが、特有の注意点がいくつか存在します。
後々のトラブルを避けるために、以下の点を考慮しておきましょう。
社員の死亡と事業承継への備え
最も重要な注意点が、唯一の社員が死亡した場合の事業承継です。
定款に特別な定めがない場合、社員が死亡するとその合同会社は原則として「解散」となり、事業を継続するには複雑な手続きが必要になります。
このリスクを回避するため、定款の任意的記載事項として「社員が死亡した場合には、その相続人が当該社員の持分を承継し、社員となる」という趣旨の規定を加えておくことを強く推奨します。
この一文があることで、万が一の際に相続人がスムーズに事業を引き継ぐことが可能になります。
意思決定プロセスの明確化
一人合同会社では、すべての意思決定を自分一人で行います。
しかし、金融機関からの融資審査や許認可の申請、税務調査などの場面で、会社の意思決定がどのように行われたかを客観的に示す書類が求められることがあります。
そのため、重要な決定(例:高額な資産の購入、事業目的の追加など)を行った際には、「決定書」といった形式で書面に残し、定款と一緒に保管しておくと、対外的な信用を高める上で役立ちます。
利益相反取引の記録
代表社員個人と会社との間で取引(例:個人所有の車を会社に売却する)を行う場合、これは「利益相反取引」に該当する可能性があります。
合同会社では株式会社のように取締役会の承認は法律上要求されませんが、取引の価格や条件が適正であったことを証明できるように、契約書や決定書をきちんと作成しておくことが望ましいでしょう。
専門家(司法書士など)に作成を依頼する費用は
合同会社の定款作成や設立登記は自分で行うことも可能ですが、専門家(主に司法書士)に依頼することもできます。
専門家に依頼した場合、報酬(手数料)が発生しますが、時間と手間を大幅に削減できるメリットがあります。
依頼する際の費用は、「専門家への報酬」と「実費(登録免許税など)」の合計額となります。
司法書士に設立手続きをすべて依頼した場合の費用相場は、一般的に5万円~15万円程度です。
以下に、自分で設立する場合と専門家に依頼する場合の費用の目安を比較しました。
| 項目 | 自分で作成(電子定款) | 自分で作成(紙の定款) | 専門家に依頼(電子定款) |
|---|---|---|---|
| 専門家への報酬 | 0円 | 0円 | 5万円~15万円程度 |
| 登録免許税 | 6万円 | 6万円 | 6万円 |
| 収入印紙代 | 0円 | 4万円 | 0円 |
| 合計 | 6万円 | 10万円 | 11万円~21万円程度 |
専門家に依頼するメリットは、単に書類を作成してもらうだけではありません。
- 時間の節約:面倒な書類作成や法務局とのやり取りをすべて任せ、本業の準備に集中できます。
- 正確性と確実性:法的な不備や記載漏れのリスクがなく、確実に会社を設立できます。
- 専門的な助言:事業目的に関する適切な表現や、将来を見据えた定款内容についてアドバイスを受けられます。
特に、設立手続きに時間をかけられない方、法的な手続きに不安がある方、許認可が必要な事業を始める方などは、専門家への依頼を検討する価値が十分にあるでしょう。
まとめ
本記事では、合同会社の定款について、作成前の準備から具体的な作り方の手順、設立登記までの流れを網羅的に解説しました。
定款は会社の基本ルールを定める、いわば「会社の憲法」であり、合同会社設立に不可欠な書類です。
合同会社の定款は、株式会社と違って公証役場による認証が不要なため、ポイントを押さえればご自身で作成することも十分に可能です。
作成にあたっては、まず商号や事業目的などの基本事項を決め、「絶対的記載事項」を漏れなく記載することが最も重要です。
ひな形を活用し、本記事で紹介した手順に沿って進めることで、スムーズに作成できるでしょう。
また、設立費用を抑えたい場合は、収入印紙代4万円が節約できる「電子定款」での作成が結論としておすすめです。
ご自身での作成に不安がある方や、時間を節約したい方は、司法書士などの専門家へ依頼することも検討しましょう。
この記事を参考に、あなたの会社設立を成功させてください。