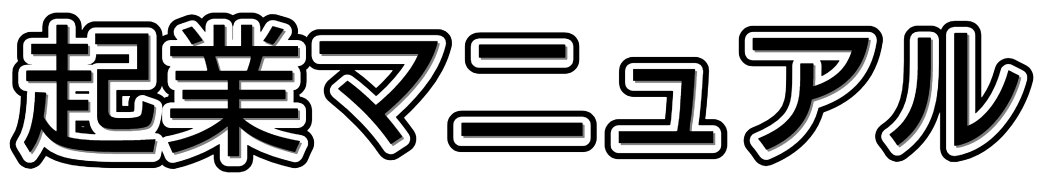「とりあえず会社を作りたい」と考えている方へ。
その勢いは大切ですが、安易な法人化は税金や維持費で後悔する可能性があります。
本記事では、会社設立のメリット・デメリットから、株式会社・合同会社別の費用、初心者でも分かる設立手順、設立後の運営までを網羅的に解説。
この記事を読めば、本当に今が法人化すべきタイミングか判断でき、失敗しない会社設立の知識が身につきます。
とりあえずで会社を作ると失敗する?知っておくべき注意点
「個人事業主からステップアップしたい」「何となく格好いいから」といった理由で、深く考えずに「とりあえず会社を作る」ことを検討していませんか?
勢いで法人化すると、思わぬ落とし穴にはまり、かえって経営を圧迫してしまうケースは少なくありません。
会社設立はゴールではなく、スタートです。
後悔しないためにも、まずは法人化に伴うデメリットや注意点をしっかりと把握しておきましょう。
安易な法人化で税金が高くなるケース
法人化のメリットとして「節税」がよく挙げられますが、事業の利益(所得)が低い段階で法人化すると、個人事業主時代よりも税金の負担が重くなる可能性があります。
特に注意すべきは、赤字でも支払い義務が生じる税金と、社会保険料の負担です。
個人事業主と法人の主な税金・社会保険の違いを見てみましょう。
| 項目 | 個人事業主 | 法人(会社) |
|---|---|---|
| 利益にかかる税金 | 所得税(累進課税:5%~45%) | 法人税(所得800万円以下は15%など) |
| 赤字の場合の税金 | 所得税・住民税は発生しない | 法人住民税の均等割(最低でも年間約7万円)が発生する |
| 社会保険 | 国民健康保険・国民年金(全額自己負担) | 健康保険・厚生年金(会社と役員で折半負担) |
最も大きな違いは、赤字でも発生する「法人住民税の均等割」です。
これは会社の規模に応じて課される税金で、資本金1,000万円以下、従業員50人以下の会社でも、最低年間約7万円の支払い義務があります。
つまり、売上がゼロでも会社を維持するだけでコストがかかるのです。
また、法人化すると経営者自身も役員として社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務付けられます。
保険料は会社と個人で折半しますが、国民健康保険や国民年金に比べて負担額が大幅に増えるケースがほとんどです。
一般的に、法人化による節税メリットが大きくなるのは、課税所得が800万円~900万円を超えてからと言われています。
ご自身の事業の利益状況を冷静に分析することが重要です。
設立後の維持費が負担になる
会社設立には、定款認証や登記申請で数十万円の初期費用がかかりますが、見落としがちなのが設立後の「維持費(ランニングコスト)」です。
事業が軌道に乗る前から、以下のような固定費が継続的に発生します。
- 法人住民税の均等割:前述の通り、赤字でも毎年最低約7万円がかかります。
- 税理士の顧問料:法人の決算申告は非常に複雑なため、税理士への依頼が一般的です。顧問契約を結ぶと、月額顧問料と決算料で年間30万円~60万円程度の費用が発生します。
- 社会保険料の会社負担分:役員や従業員の社会保険料の半分を会社が負担します。これは経営にとって大きなコストとなります。
- 登記変更の費用:役員の交代(任期満了による再任も含む)、本社の移転など、登記事項に変更があった場合はその都度、登記申請が必要となり、数万円の登録免許税や司法書士への報酬がかかります。
これらの維持費は、個人事業主時代にはなかった、あるいはもっと少額だった費用です。
売上が不安定な時期にこれらの固定費が重くのしかかり、資金繰りを悪化させるリスクがあることを忘れてはいけません。
事務手続きの煩雑さに驚く
法人化すると、お金の面だけでなく、事務的な負担も格段に増加します。
個人事業主であれば開業届一枚で済んだ手続きも、法人ではそうはいきません。
まず、会社設立手続き自体が複雑です。定款の作成・認証、登記書類の準備、法務局への申請など、専門知識がなければスムーズに進めるのは難しいでしょう。
さらに大変なのが、設立後の経理・労務手続きです。
- 会計処理:個人事業主の簡易的な帳簿とは異なり、複式簿記による厳格な会計処理が求められます。
- 決算申告:年に一度、貸借対照表や損益計算書などの複雑な決算書を作成し、法人税の申告を行う必要があります。この手続きは専門家でなければ困難です。
- 社会保険・労働保険の手続き:役員報酬の決定や従業員の雇用に伴い、社会保険や労働保険の加入手続き、毎月の保険料の計算・納付、年末調整など、非常に煩雑な事務作業が発生します。
- 議事録の作成・保管:法律で定められた会議(株主総会など)を開催した際には、議事録を作成し、会社に保管する義務があります。
これらの膨大な事務作業に追われ、本来注力すべき事業活動の時間が奪われてしまうことは、経営者にとって大きなデメリットと言えるでしょう。
専門家に外注するにも、当然ながら費用がかかります。
それでも会社を作るべき理由とメリット

「とりあえず」で会社を作ることの注意点を知ると、法人化に二の足を踏んでしまうかもしれません。
しかし、多くの起業家が個人事業主から法人へとステップアップするには、それを上回るだけの明確な理由とメリットが存在します。
事業の成長を加速させ、新たなステージへ進むために、会社設立がもたらす3つの大きなメリットを具体的に見ていきましょう。
社会的信用度が格段に向上する
法人化がもたらす最も大きなメリットの一つが、社会的信用度の向上です。
個人事業主と比較して、法人は「公的な存在」として認知され、ビジネスのあらゆる場面で有利に働きます。
なぜなら、会社は法務局に登記されることで、商号、本店所在地、役員、資本金といった情報が公開され、誰でもその存在を確認できるからです。
この透明性が、取引先や金融機関、そして顧客からの信頼につながります。
具体的には、以下のようなメリットが期待できます。
- BtoB取引の拡大
大企業の中には、コンプライアンスや与信管理の観点から、取引相手を法人のみに限定しているケースが少なくありません。法人化することで、これまで取引の機会がなかった大手企業との契約や、より規模の大きなプロジェクトに参画できる可能性が広がります。 - 人材採用における有利性
求職者にとって、法人は個人事業主よりも安定した組織という印象を与えます。また、社会保険への加入が義務付けられているため、福利厚生の面でも安心感があります。これにより、優秀な人材を確保しやすくなり、組織としての成長基盤を強化できます。 - 各種契約の円滑化
事業用のオフィスや店舗を借りる際の賃貸借契約、あるいはリース契約など、法人名義の方が審査に通りやすい傾向があります。個人としての信用情報だけでなく、事業そのものの将来性や安定性が評価されるためです。
節税の選択肢が広がる
事業の利益が一定額を超えてくると、個人事業主のままでは税負担が重くなりがちです。
法人化することで、多様な節税策を活用できるようになり、手元に残る資金を最大化できる可能性があります。
個人事業主の所得税が、所得が増えるほど税率も高くなる「累進課税」であるのに対し、法人税は原則として一定の税率です。
そのため、所得が800万円~900万円を超えるあたりから、法人化した方がトータルの税負担を抑えられる-ケースが多くなります。
具体的にどのような節税が可能になるのか、個人事業主と比較してみましょう。
| 項目 | 法人 | 個人事業主 |
|---|---|---|
| 自分への給与 | 役員報酬として経費計上可能。 給与所得控除が適用される。 | 経費にできない(事業主勘定で処理)。 |
| 経費にできる範囲 | 生命保険料(退職金準備)、社宅家賃、出張手当など、経費として認められる範囲が広い。 | 事業に直接関連するものに限定される。 |
| 赤字の繰越 | 欠損金を最大10年間繰り越せる。 | 青色申告で最大3年間。 |
| 退職金 | 役員や従業員への退職金を経費として計上可能。 受け取る側も税制上優遇される。 | 原則として退職金の概念はない(小規模企業共済などで備える)。 |
| 消費税 | 資本金1,000万円未満の場合、原則として設立から最大2年間は納税が免除される可能性がある。 | 前々年の課税売上高が1,000万円を超えた場合、またはインボイス登録事業者になった場合に課税事業者となる。 |
このように、役員報酬の設定や経費計上の幅広さを活用することで、戦略的な節税対策を講じることが可能になります。
資金調達で有利になる
事業を拡大していく上で、資金調達は避けて通れないテーマです。
法人化は、この資金調達の選択肢を大きく広げ、より多額の資金を円滑に集めるための強力な武器となります。
金融機関は融資の審査において、事業の透明性や客観的な財務状況を重視します。
法人は会計処理が法律で厳格に定められており、決算書などの信頼性が高いため、個人事業主よりも有利な条件で融資を受けやすい傾向にあります。
- 融資制度の活用
日本政策金融公庫の「新創業融資制度」や、地方自治体が窓口となる「制度融資」など、創業者向けの融資制度は多数存在します。法人格を持つことで、これらの制度をより有利な条件で活用できる可能性が高まります。事業が軌道に乗れば、信用保証協会を通さない銀行独自の「プロパー融資」への道も開けます。 - 出資による資金調達
ベンチャーキャピタル(VC)やエンジェル投資家から出資を受ける「エクイティファイナンス」は、個人事業主にはできない、株式会社ならではの資金調達方法です。株式を発行する対価として大規模な資金を得ることで、製品開発やマーケティングに一気に投資し、事業の急成長を目指すことができます。 - 補助金・助成金の活用
国や地方自治体が提供する補助金や助成金の中には、応募資格を「法人」に限定しているものが数多くあります。法人化することで、活用できる制度の幅が広がり、返済不要の貴重な資金を得るチャンスが増えます。
これらのメリットは、単に「とりあえず」会社を作っただけですぐに享受できるものではありません。
しかし、事業の将来を見据えたとき、法人化が成長への扉を開く重要な鍵となることは間違いないでしょう。
会社設立の費用を種類別に徹底解説

「とりあえず会社を作りたい」と思っても、まず気になるのが費用ではないでしょうか。
会社設立には、法律で定められた「法定費用」と、それ以外に必要となる「その他の費用」があります。
法定費用は設立する会社の種類によって異なり、自分自身で手続きを行うか専門家に依頼するかでも総額は変わってきます。
ここでは、最も一般的な株式会社と合同会社を例に、設立にかかる費用を具体的に解説します。
株式会社の設立費用総額
株式会社は社会的信用度が高い法人形態ですが、合同会社に比べて設立費用は高くなります。
最低でも約20万円の法定費用がかかることを想定しておきましょう。
主な内訳は以下の通りです。
| 項目 | 費用 | 説明 |
|---|---|---|
| 定款認証手数料 | 3万円~5万円 | 会社の根本規則である定款を、公証役場で認証してもらうための手数料です。資本金の額によって変動します。 |
| 登録免許税 | 最低15万円 | 法務局で設立登記を行う際に納める税金です。資本金の額×0.7%で計算され、最低でも15万円が必要です。 |
| 定款の謄本手数料 | 約2,000円 | 認証された定款の写し(謄本)を発行してもらうための手数料です。1ページあたり250円程度かかります。 |
| 合計 | 約18万2,000円~ | 資本金の額によって変動しますが、最低でもこの金額が必要になります。 |
ここで注意したいのが、定款の作成方法です。
従来の紙の定款で作成・認証する場合、上記に加えて収入印紙代として4万円が別途必要になります。
しかし、電子定款を利用すればこの印紙代は不要になるため、設立費用を抑える上で非常に重要なポイントです。
現在では電子定款が主流となっており、専門家に依頼する場合もほとんどがこの方法で手続きを進めます。
法定費用以外にも、会社の代表印(実印)や銀行印、角印といった印鑑の作成費用(1万円~3万円程度)や、設立後の手続きで必要となる会社の登記簿謄本・印鑑証明書の取得費用などがかかります。
これらを合計すると、株式会社の設立にはおよそ20万円から25万円程度を見込んでおくと良いでしょう。
合同会社の設立費用総額
合同会社(LLC)は、株式会社に比べて設立費用を大幅に抑えられるのが最大のメリットです。
スタートアップや小規模な事業を始める際に人気の法人形態で、法定費用は最低6万円から設立が可能です。
| 項目 | 費用 | 説明 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 最低6万円 | 法務局で設立登記を行う際に納める税金です。資本金の額×0.7%で計算され、最低でも6万円が必要です。 |
| 定款認証手数料 | 0円 | 合同会社は株式会社と異なり、公証役場での定款認証が不要です。 |
| 合計 | 6万円~ | 株式会社に比べて、法定費用を10万円以上安く抑えられます。 |
合同会社も株式会社と同様に、紙の定款を作成する場合は収入印紙代4万円が必要となります。
費用を最小限に抑えたいのであれば、電子定款での作成が必須です。
また、合同会社は定款認証が不要なため、公証役場へ行く手間と費用がかからない点も大きな魅力です。
印鑑作成費用などを考慮しても、合同会社の設立費用は総額で約6万円から10万円程度に収まります。
「とりあえず会社を作って事業を始めたい」という方にとって、初期費用を抑えられる合同会社は非常に有力な選択肢となるでしょう。
専門家に依頼した場合の費用相場
会社設立の手続きは複雑で時間がかかるため、司法書士や行政書士、税理士といった専門家に代行を依頼することも可能です。
専門家に依頼すると代行手数料(報酬)が発生しますが、それ以上に大きなメリットがあります。
最大のメリットは、専門家は電子定款に対応しているため、自分で紙の定款を作成する場合に必要な収入印紙代4万円が不要になる点です。
そのため、専門家への手数料が4万円以下であれば、自分で手続きするよりも結果的に費用が安くなるケースも少なくありません。
| 依頼先 | 手数料の相場 | 主な業務内容 |
|---|---|---|
| 司法書士 | 5万円~10万円 | 定款作成から登記申請まで、設立に関するすべての法的手続きを代行可能。 |
| 行政書士 | 3万円~8万円 | 定款作成や必要書類の準備を代行。ただし、登記申請の代行はできないため、申請は自分で行うか司法書士に別途依頼する必要がある。 |
| 税理士 | 0円~5万円 | 設立後の顧問契約を条件に、設立手数料を無料または格安で請け負う場合が多い。税務関連の届出も一括で依頼できる。 |
どの専門家に依頼するかは、どこまでのサポートを求めるかによって変わります。
設立手続きを丸ごと任せたいなら司法書士、設立後の税務も見据えるなら税理士、というように目的に合わせて選ぶと良いでしょう。
時間と手間を節約し、確実に手続きを完了させたい場合は、専門家への依頼を積極的に検討することをおすすめします。
初心者でも簡単 会社を作る手順をわかりやすく解説

「会社を作る」と聞くと、複雑で専門的な知識が必要だと感じるかもしれません。
しかし、正しい手順とポイントさえ押さえれば、初心者でもご自身で会社を設立することは十分可能です。
この章では、会社の設立準備から登記申請、そして設立後の届出まで、一連の流れをステップバイステップでわかりやすく解説します。
会社の骨格を決める
会社設立の第一歩は、会社の基本的なルールやプロフィールとなる「基本事項」を決めることです。
ここで決めた内容は、後の「定款(ていかん)」という会社の憲法ともいえる書類に記載する重要な項目となります。
まずは以下の項目を具体的に決めていきましょう。
- 商号(会社名):会社の顔となる名前です。同一住所に同じ商号の会社は登記できないなどのルールがあります。
- 事業目的:その会社がどのような事業を行うのかを具体的に記載します。将来行う可能性のある事業も入れておくと良いでしょう。
- 本店所在地:会社の住所です。自宅やレンタルオフィスでも登記可能です。
- 資本金の額:会社の元手となる資金です。
- 発起人(ほっきにん):会社を設立する人(出資者)のことです。
- 役員構成:会社の経営を行う取締役などを決めます。
- 事業年度:会社の会計期間(決算期)を決めます。一般的には4月1日から翌年3月31日が多いですが、自由に設定できます。
これらの基本事項は、会社設立後の運営にも大きく影響します。
特に資本金と役員構成は重要なポイントですので、詳しく見ていきましょう。
資本金はいくらにするべきか
現在の会社法では、資本金1円から株式会社を設立できます。
しかし、「とりあえず1円で」と安易に決めてしまうのはおすすめできません。
資本金の額は、会社の信用度と初期の運転資金に直結するからです。
資本金を決める際のポイントは以下の2つです。
- 対外的な信用度
資本金の額は登記事項証明書(登記簿謄本)で誰でも確認できるため、会社の体力や規模を示す指標の一つと見なされます。資本金が極端に少ないと、金融機関からの融資審査や、新規取引先との契約で不利になる可能性があります。 - 当面の運転資金
会社を設立しても、すぐに売上が立つとは限りません。売上がなくても、事務所の家賃や光熱費、仕入れ費用などの経費は発生します。少なくとも、事業が軌道に乗るまでの3ヶ月から6ヶ月程度の運転資金’mark>を資本金として用意しておくと安心です。
また、建設業など許認可が必要な事業を始める場合、その許認可の要件として一定額以上の資本金が定められていることがありますので、事前に確認が必要です。
なお、設立時の資本金を1,000万円未満にすると、原則として設立から最大2事業年度は消費税の納税が免除されるという大きなメリットもあります。
役員構成をどうするか
会社の運営方針を決め、業務を執行するのが「役員」です。
株式会社の場合、最低でも取締役1名がいれば設立できます。
一人で会社を始める場合は、ご自身が発起人兼株主兼取締役となる「一人社長」の形が最もシンプルです。
複数人で会社を設立する場合は、それぞれの役員の役割分担や責任の範囲を明確にしておくことが重要です。
後々のトラブルを避けるためにも、誰が代表取締役になるのか、他の取締役の権限はどうするのかなどを事前に話し合っておきましょう。
なお、会社の業務や会計を監査する「監査役」については、株式の譲渡に制限を設けている非公開会社(中小企業のほとんどが該当します)では、設置は義務付けられていません。
定款作成から登記申請までの流れ
会社の基本事項が決まったら、いよいよ法的な手続きに進みます。
ここでは、定款の作成から法務局への登記申請までの具体的なステップを解説します。
- STEP1:会社の実印を作成する
登記申請には会社の実印(代表者印)が必須です。法務局に登録するための印鑑なので、早めに準備しておきましょう。あわせて銀行印や角印も作っておくと、その後の手続きがスムーズです。 - STEP2:定款を作成する
定款とは、会社の組織や運営に関する基本的なルールを定めた書類です。先ほど決めた商号、事業目的、本店所在地などの基本事項を盛り込んで作成します。 - STEP3:定款の認証を受ける(株式会社の場合)
作成した定款が法的に正当なものであることを証明してもらうため、公証役場で「定款認証」という手続きを行います。なお、合同会社の場合はこの定款認証は不要です。電子定款で認証を行えば、収入印紙代の4万円が不要になるというメリットがあります。 - STEP4:資本金を払い込む
定款認証後、発起人個人の銀行口座に、定められた資本金を振り込みます。この時、通帳の表紙、裏表紙、そして振込が記帳されたページをコピーしたものが「払込証明書」となり、登記の際に必要となります。 - STEP5:登記書類を作成する
法務局に提出するための登記申請書類一式を準備します。
主に以下の書類が必要です。
・登記申請書
・登録免許税納付用台紙
・定款
・発起人の決定書
・役員の就任承諾書
・印鑑証明書(取締役など)
・払込証明書
・印鑑届書 - STEP6:法務局で登記申請を行う
すべての書類が揃ったら、本店所在地を管轄する法務局へ提出します。書類を法務局が受理した日が、会社の設立日となります。申請から登記が完了するまで、1週間から10日ほどかかります。
会社設立後に必須の届出リスト
法務局での登記が完了しても、手続きは終わりではありません。
事業を開始するためには、税務署や年金事務所など、さまざまな行政機関への届出が必要です。
これらの届出を怠ると、ペナルティが課されたり、税制上の優遇措置が受けられなくなったりする可能性があるため、必ず期限内に済ませましょう。
設立後に必要な主な届出は以下の通りです。
| 提出先 | 書類名 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 税務署 | 法人設立届出書 | 設立後2ヶ月以内 |
| 税務署 | 青色申告の承認申請書 | 設立後3ヶ月以内 or 第1期事業年度終了日のいずれか早い日 |
| 税務署 | 給与支払事務所等の開設届出書 | 開設後1ヶ月以内 |
| 都道府県税事務所 市町村役場 | 法人設立届出書 | 各自治体の条例による(設立後15日〜2ヶ月以内など) |
| 年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 設立後5日以内 |
| 労働基準監督署 (従業員を雇用した場合) | 労働保険関係成立届 | 雇用日の翌日から10日以内 |
| ハローワーク (従業員を雇用した場合) | 雇用保険適用事業所設置届 | 設置の日の翌日から10日以内 |
特に「青色申告の承認申請書」は、欠損金の繰越控除など節税面で非常に大きなメリットがあるため、提出期限に遅れないよう注意してください。
これらの手続きは多岐にわたりますが、一つひとつ着実にこなしていくことが、スムーズな事業運営の第一歩となります。
会社を作ったら終わりではない 設立後の運営について

無事に会社の登記が完了しても、それはゴールではなくスタートラインに立ったに過ぎません。
会社を設立した後は、事業を円滑に進めるための様々な手続きや運営業務が待っています。
特に「法人口座の開設」と「役員報酬の決定」は、会社の信用と資金繰りに直結する重要なステップです。
ここでは、会社設立後に必ず対応すべき運営の基礎知識について、初心者にも分かりやすく解説します。
法人口座の開設と会計ソフトの導入
会社の財産と個人の財産を明確に分けるため、法人口座の開設は必須です。
また、日々の取引を正確に記録し、決算申告に備えるために会計ソフトの導入も欠かせません。
これらは事業運営の根幹をなすため、設立後すみやかに行いましょう。
法人口座の開設
法人口座は、取引先からの入金や経費の支払いなど、会社のすべてのお金の流れを管理するための専用口座です。
個人事業主時代に使っていた個人口座をそのまま流用することはできません。
法人口座を持つことで、会社の信用度が高まり、融資や取引がスムーズに進むという大きなメリットがあります。
口座を開設する金融機関は、主にメガバンク、地方銀行、ネット銀行の3種類に分けられます。
それぞれに特徴があるため、自社の事業内容に合わせて選びましょう。
| 金融機関の種類 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| メガバンク | 知名度と信用度が高い、支店が多く利便性が高い、大規模な融資に対応可能 | 口座開設の審査が厳しい、手数料が比較的高め |
| 地方銀行・信用金庫 | 地域密着型で親身な相談が可能、審査が比較的柔軟、地元の情報に強い | 全国的な知名度は低い、他県での利便性が低い場合がある |
| ネット銀行 | 手数料が安い、24時間オンラインで取引可能、口座開設がスピーディー | 実店舗がないため対面での相談ができない、社会保険料の引き落としに対応していない場合がある |
口座開設には、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、法人の印鑑証明書、代表者の本人確認書類などが必要です。
金融機関によって必要書類が異なるため、事前にウェブサイトなどで確認しておきましょう。
会計ソフトの導入
法人には、年に一度の決算と法人税の申告が義務付けられています。
日々の取引を正確に帳簿に記録(記帳)しておかなければ、正しい決算書を作成することはできません。
手作業での記帳は非常に手間がかかり、ミスも起こりやすいため、会計ソフトの導入が一般的です。
特に、近年主流のクラウド型会計ソフトは、初心者でも直感的に操作できるものが多くおすすめです。
| ソフトの種類 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| クラウド型 | インストール不要でどこでも使える、銀行口座やクレジットカードと連携して自動で記帳できる、法改正に自動でアップデート対応する | 月額利用料がかかる、インターネット環境が必須 |
| インストール型 | 買い切り型でランニングコストが抑えられる、オフラインでも作業できる | PCへのインストールが必要、法改正の際はアップデート費用がかかる場合がある、データのバックアップを自分で行う必要がある |
代表的なクラウド会計ソフトには「freee会計」「マネーフォワード クラウド会計」「弥生会計 オンライン」などがあります。
無料お試し期間を利用して、自社に合ったソフトを選ぶと良いでしょう。
役員報酬の決定方法
役員報酬とは、取締役などの役員に対して支払われる給与のことです。
自分の会社だからといって、好きな時に好きな金額を引き出せるわけではありません。
役員報酬には税務上の厳格なルールがあり、このルールを守らないと会社の税金が高くなってしまう可能性があります。
役員報酬の基本ルール「定期同額給与」
法人税法上、役員報酬を会社の経費(損金)として認めてもらうためには、原則として「定期同額給与」というルールを守る必要があります。
これは、毎月同じ日に同じ金額を支払うというルールです。
つまり、一度決めた役員報酬の金額は、原則としてその事業年度が終わるまで変更できません。
このルールを守らずに報酬額を途中で変更したり、賞与(ボーナス)を支払ったりすると、その分は経費として認められず、結果的に法人税の負担が増えてしまいます。
そのため、役員報酬の金額は慎重に決定しなければなりません。
役員報酬額を決める際の注意点
役員報酬の金額は、会社設立日から3ヶ月以内に決定し、株主総会(合同会社の場合は社員総会)で議事録を作成する必要があります。
金額を決める際は、以下の3つのバランスを総合的に考慮することが重要です。
- 会社の利益と資金繰り
まず最も重要なのが、会社の利益予測です。売上から経費を差し引いた利益の範囲内で、無理のない金額を設定しましょう。役員報酬を高く設定しすぎると、会社の現金が不足し、資金繰りが悪化する原因になります。 - 社会保険料の負担
役員報酬を支払うと、会社と役員個人は社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する義務が生じます。社会保険料は会社と個人が折半で負担するため、役員報酬の金額が大きくなるほど、双方の負担額も増加します。この負担額も考慮して報酬額を決定する必要があります。 - 個人の税金(所得税・住民税)
役員報酬は個人の給与所得となるため、所得税や住民税がかかります。所得税は累進課税のため、報酬額が高くなるほど税率も上がります。会社の法人税率と個人の所得税率のバランスを見ながら、会社と個人の手元に最も多くお金が残る最適な金額を見つけることが節税のポイントになります。
これらの要素を考慮し、税理士などの専門家に相談しながら、自社にとって最適な役員報酬額を決定することをおすすめします。
まとめ
「とりあえず会社を作る」という安易な考えは、税金や維持費の負担増といった失敗に繋がる可能性があります。
一方で、社会的信用の向上や節税など、法人化には事業を加速させる大きなメリットがあるのも事実です。
株式会社や合同会社といった選択肢ごとの費用と手順を正しく理解し、設立後の運営まで見据えて計画的に準備を進めることが重要です。
本記事を参考に、あなたの事業にとって最適な選択をしてください。